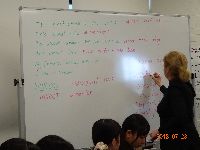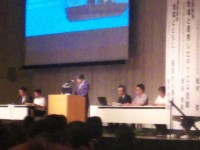2018年度 高大接続事業 神戸大学 報告
1.日時 2018年7月18日(水) 14:00~16:30
2.場所 神戸大学 鶴甲第2キャンパス
3.連携 神戸大学 国際人間科学部 原田和弘 准教授
4.内容
14:00~15:00 【講義】
・大学学部選択や大学の仕組みついて
・神戸大学での専門・研究について
・神戸大学の高齢者研究、原田先生の研究について
15:10~16:00 【発表と質疑応答】
・芦屋高校ボランティア部の活動報告とシミュレーション発表
・今年度から始めた地域の高齢者宅への訪問の発表と質問
・原田先生から高齢者の心理や健康を考慮して回答いただく

16:00~16:30 【キャンパス内見学】
図書館・大講義室・研究室・障害者運営のカフェ等

【生徒の感想から】
今回の高大接続事業でたくさんの驚きや発見がありました。
高齢者の方で声が届きにくい時に、僕は高音の方がよく聞こえるだろうと思っていました。しかし、今日教えてもらったことは低音の方が聞き取りやすいということです。このことにはとても驚きました。僕にはとても耳の悪い祖母がいるのでお盆に帰った時には声をいつもより低くして話したいと思います。
話を聞く時は、受容、共感、傾聴が大切ということも教わりました。
このことは高齢者だけでなく誰とでも話す時に大切だと思うので今後このことに気をつけて話を聞きます。
今回の高大接続事業で今後の自分に役立つようなことをたくさん教えてもらいました。
僕はボランティア部に入り、1年生から3年生まで続けてきました。
2年前を振り返ると今の自分があるのはボランティア部で活動してきたことがとても活かされていると思います。本日は貴重な経験、ありがとうございました。3年男子
高大接続事業で神戸大学を訪問し、まずは私たちの知らない大学の事、原田先生の紹介をしていただきました。原田先生の行なっている事の中で興味深かったものが「鶴甲いきいきまちづくりプロジェクト」というものであまり繋がりのなかった鶴甲の人がこのプロジェクトに約100人参加したと聞いて驚きました。11月には県政150周年のイベントがありますがどうすれば多くの人に参加していただけるかという課題はこれから必ず考えなければならないことなので参考になりました。
芦高ボランティア部の活動報告、シミュレーション発表とお宅訪問の説明をした後には私達の質問に答えていただきました。質問の答えの中で印象深かったものは高齢者の方が話す話題への反応のポイントは受容、共感、傾聴ということです。私たちが反応に困るような話題でも話す方は話したくて話しているので敏感になりすぎず3つのポイントで会話しようと思いました。原田先生の鶴甲のプロジェクトを進めている時の話を聞いて、私たちのお宅訪問も全ての人が賛成して参加していただいてるわけではありませんが大切な取り組みだと信じて進めて行きます。
原田先生の専門外の事も質問してしまいましたが、先生としてだけでなく子供の親としての目線で答えてくださってこれからプロジェクトを進めていく上で必要な事を聞けました。ありがとうございました。2年女子
【学んだこと】
・呼び方をおじいちゃんとかではなく、しっかりと名前で呼ぶこと。
・声が聞こえない時は、相手の方に聞こえる方の耳を伺い、お話すること。
・席を譲る時は、2回ほど聞いて反応に応じること。
・運動として、スクワットなどを取り入れること、など
【印象に残ったこと】
原田先生が、よく沢山怒られると言っておられたのには驚きました。
善意で行っていることでも、やはり色々な考え方の人がいて、よく思われない方もやはり少なからずいるんだなと思いました。
それに対しても丁寧に対応されてるという話を聞いて、すごくかっこよく感じました。
【感想】
普段高齢者の方の事を専門的に研究されている方のお話を伺う機会は無いので、今回このような場を設けさせて頂いて、これからの人生に役にたつようなことを沢山聞けました。
本当にありがとうございました。
これからのお宅訪問などに生かさせて頂きたいと思います。1年男子

文責:ボランティア部顧問