人間科学類型は、地域課題の解決やグローバルリーダーとしての資質を育成することを目標に課題研究活動に取り組んでいます。その取り組みの一環として、1年生の夏休みに3日間の「京大-HGLC科学者育成プログラム」を実施しています。
2日目(8/2)は、「原子力科学の未来と可能性」と題して、午前中に大阪市立自然史博物館・植物園(大阪市東住吉区)、午後から京都大学複合原子力科学研究所(大阪府泉南郡熊取町)を訪れました。
午前中は、人間をとりまく「自然」について、その成り立ちやしくみ、その変遷や歴史を学ぶために、大阪市立自然史博物館・植物園を訪れました。開館時間に合わせ、子供連れを含む多くの人たちが列をなし、博物館の人気の高さがうかがえました。館内はとても広く、数多くの展示物や標本が所狭しと並んでいました。学校の生物の授業では難しくなかなか理解できなかったことが、実物を直接目で見て学べるので、理解が深まりました。隣接する植物園も含め、見学時間があっという間に過ぎていきました。
午後からは、大阪府泉南郡熊取町に場所を移して、京都大学複合原子力科学研究所を訪れました。原子力エネルギー関連および放射線・粒子線や放射性同位元素などの利用に関する研究・教育を行う研究所として、1963年にこの地に設置されました。それ以降、研究用原子炉や加速器を利用して多くの研究が行われ、日本のみならず世界の科学技術の進歩に大きく貢献しているそうです。そして、この研究所では先端科学技術を扱っていることに加え、人体に有害な放射線を扱っていることから、入所前から何重もの厳重なセキュリティ管理が求められ、その度に緊張を強いられたことを覚えています。
最初は、原子力基礎工学研究部門の山村朝雄教授から、『原子力発電、放射性廃棄物と、新しい科学へ』と題する講演をしていただきました。その講演では、原子力発電に伴って生じる放射性廃棄物(マイナーアクチノイド)について教えて頂きました。正直言って、講演の内容が難しすぎて高校生には理解できない部分が多くありました。しかし、その研究がどれほど人々の役に立つのかや、その研究の価値は理解できた気がしました。
講演の後はいよいよ原子炉の見学です。しかしその前に、担当者から見学時における持ち込み物の確認や注意事項とともに放射線の被ばくを測定する線量計がグループに1つずつ配られました。原子炉の建物に入る前にも被ばく量の測定とオーバーシューズの着用が義務付けられました。減圧された原子炉建屋の中に入り、いざ原子炉を目の前にすると、さすがに緊張が高まり、心臓の鼓動が高まったのを思えています。また、私たちが訪れたときはちょうどフルパワーで稼働している最中だったようです。テレビなどを通して私たちが良く目にするのは発電用の原子炉、いわゆる原子力発電所とは少し違い、私たちが目にしているのは出力の小さな研究用の原子炉でした。それでも十分に大きく、放射能の危険性に違いはないと聞きました。さらに驚いたのは、原子炉の周りを取り囲むように研究室が配置され、原子炉から作り出される中性子を使って今まさに実験が行われていることでした。
それまでは、原爆や原子力発電所の事故などから、危険で恐ろしいものとしか認識していなかった原子力が、使い方によっては非常に役に立つものであることが分かった。まさにその研究に今日触れることができました。帰りのバスの中では、原子炉を見学した興奮がいつまでも冷めず、いつまでも友達と感想を語り合っていました。
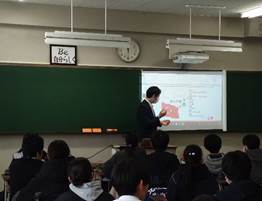




④-300x224.jpg)
③-300x224.jpg)
②-300x225.jpg)
①ー1-300x224.jpg)
①ー2-300x220.jpg)



























