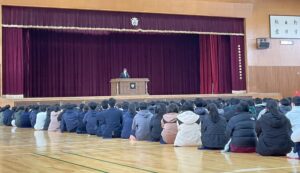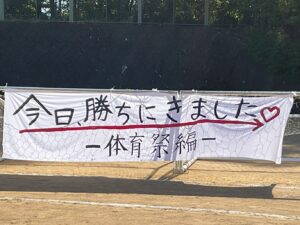〇問
「丙午」(ひのえうま)という年はどんな年か
「丙午」の年である1966年生まれの人口はなぜ少ないのか
〇答え
干支(えと)というのは12あって、子丑寅兎辰巳午未申酉戌猪があり、この順番に巡ってきます。古代中国から日本に伝わったもので、時刻や方角など、ものの順序を表す時に用いられてきました。日本では現在ほとんど使用されなくなりましたが、年末年始になると、「来年は〇〇年、今年は〇〇年」と、この時期だけクローズアップされます。
古代中国には、干支の他に、もう一つものの順番を表すものがあります。それは甲乙丙丁戊己庚辛壬癸です。こちらは漢字が10並びますから十干(じっかん)と呼びます。これも古代中国からものの順番を表すものとして日本に伝わり使われてきました。
中国や日本の年暦つまり年の呼び名は、この「十干」と「十二支」とを組み合わせて呼ぶようになりました。例えば、西暦672年に起こった事件を「壬申の乱」、西暦1868年に起こった戦争を「戊辰戦争」と呼びます。この組み合わせは、60年に1回やってきます。
だから、生まれた年の組み合わせは60歳になる年に巡ってきます。60歳を迎えることを還暦と言うのは、この組み合わせ、つまり年暦が一周りするからなのですね。
では、今年は十干でいえば何にあたる午年なのか。「丙」です。干支は午ですから「丙午」(へいご)の年となります。丙午(へいご)は「ひのえうま」とも読みます。
実はこの丙午、江戸時代から特別な年として扱われてきました。「丙午」の年に生まれた女性は気性が荒く、一家を不幸にするという迷信が信じられてきたのです。この迷信の元になった実在の人物がいます。それは江戸の八百屋の娘として生まれた「お七」という女性です。
当時の江戸は木造家屋ばかりで、しょっちゅう火事が起こりました。大火事のたびに人々は地域のお寺に避難し、家が再建されるまで寺で共同生活をしていました。天和の大火(1683年)により、お七が暮らしていた家も大火に巻き込まれたのですが、寺で避難生活をしていた時に彼女は庄之助という一人の男性と恋仲になったのです。しかし、街が復興し、二人はそれぞれ自宅に戻り離れ離れとなりました。「また火事になったら庄之助と生活ができる」と思ったお七は、自宅に放火をしました。当時、放火は最も重い罪でした。その後、お七は放火の罪でとらえられ処刑されたのです。この話は井原西鶴によって「八百屋お七」という物語にされています。
お七が丙午の年の生まれであったことから、江戸の街では、丙午の年に生まれた女性が良く思われなくなったと言われています。いずれその迷信が全国に拡がり、子どもの出生にも大きな影響をもたらすようになったのです。
私が生まれた1966年は、実は「丙午」の年です。高度経済成長期に入っても日本ではまだ、このいい加減な迷信が信じられていて、多くの夫婦が子どもを作ることを控えたのです。新生児の数が前年に比べなんと25パーセントも減少しました。
迷信というのは、人が勝手に作り上げたもので、そのほとんどが確かな根拠に乏しいものです。信じるかどうかは人の勝手かも知れませんが、その迷信を人への差別や偏見につなげることはいけません。また、迷信が社会現象となって人々の生活に影響をもたらすことがあってはならないのです。
SNSが普及したことで、迷信や噂があっという間に広がってしまう世の中になりました。その迷信や噂を用いて、人を攻撃し傷つけようとする人たちもいます。また、時には、その迷信や噂がSNSを介して拡大し、まるで真実であるかのように人々を動揺させることもあります。
迷信や噂に振り回されず、常に冷静に真実を求めること。
私が「丙午」の話から学んだことです。