いよいよ始まるスキーに向けて、ばっちり栄養補給!!


朝からいい笑顔を見せてくれました!
怪我なく楽しんできてね!

いよいよ始まるスキーに向けて、ばっちり栄養補給!!


朝からいい笑顔を見せてくれました!
怪我なく楽しんできてね!



食後に、昨日バースデーだった3組担任の野村先生にクラスの生徒からサプライズのプレゼントが贈られました。

道路事情により予定より少し遅れましたが、無事に宿泊先のヒルトンニセコに到着しました!

ややタイトになってしまいましたが、ウェアとブーツ合わせをして夕食となります。
札幌での班別研修を終え、宿泊先のヒルトンビレッジに到着しました。
辺り一面雪景色で、北海道に来た!と心がワクワクします。
事前発送した大荷物を受け取り、部屋へ移動します。
12時30頃に札幌のテレビ塔前に到着しました。
到着後は、各クラスで編成した班ごとに事前作成した行動計画表の通りに研修へ行きました。
引率教員が生徒に出会えなかったので、タイムラグが生じてしまいましたが、生徒から提供してもらった写真を投稿します。



あるクラスでは、ほとんどの生徒が味噌ラーメンを食べたそうです。


明日は、いよいよスキー実習です。天気予報が終日雪とのことで、不安もありますが、たくましい39回生ならきっと有意義な実習になると思っています。
伊丹空港出発組と神戸空港出発組が無事に新千歳空港で合流し、北海道に到着しました。


諸連絡の後、バスに乗って札幌観光へ向かいます!
神戸空港組、無事に到着して北海道へ向かいます!

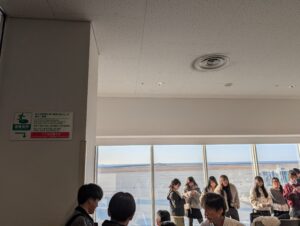

大きなトラブルなく、無事にバスに乗車することができました。学校と新三田駅前から空港へ向かいます。

1月17日 8:50より修学旅行の結団式を行いました。
初めに、団長の教頭先生から「高校生活最大のイベントである修学旅行を最高の思い出になるようにしよう」という話をしていただきました。

学年主任挨拶では、「ルールを守って楽しみましょう」という話をしていただきました。

修学旅行委員長の挨拶では、「一歩踏み出して、新しいチャレンジをしよう」という話をしていただきました。

その後、引率団の紹介を経て、最終の諸連絡を受けました。

いよいよ当日を迎えますね!体調管理に留意してまずは全員無事に集合できますように!
1月14日、39回生の修学旅行に向けて、大荷物の発送が、滞りなく完了しました。
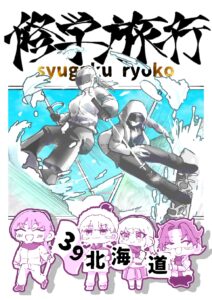
1月17日(土)に結団式を行い、1月19~22日の日程で北海道に行きます。
今後、随時ブログの更新行いますので、ぜひご覧ください。