令和5年11月25日(土)
GS科1年生の学校設定科目「GSⅠ」の授業を行いました。今回の授業は化学室にて生化学に関わる探究でした。GS科1年生は2年生から生物の授業が始まるため、未知の分野に対して班員で協働しながら取り組みました。仮説を立てながら予備実験を行い、反応に最適な要因を探りました。最後は10分間で、どれだけ反応を進ませることができるかコンテストを行いました。多くの班が、実験の適条件を作り出すことができていました。GS科1年生は、このように探究基礎実習を繰り返しながら、「気づく力」「繋ぐ力」「伝える力」「見通す力」「挑戦する力」の5つの力を伸ばしていきます。

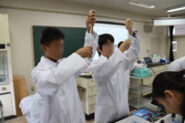


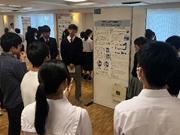
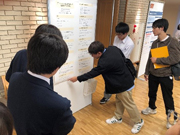
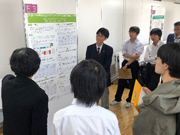


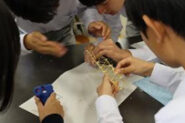






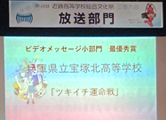

 11月12日(日)
11月12日(日)



