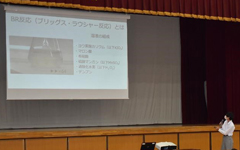令和5年2月9日(木)
普通科2年生の「総合的な探究の時間」において、全体発表会が行われました。テーマごとに分かれた6講座内での各発表で選ばれた代表計15班が、体育館にてポスターセッションを行います。時間の都合により、今回聴衆が聞くことのできるは15班のうち4班の発表のみ。セッション開始前から、どのプレゼンを聞きに行くのかを考えている姿が見られました。


各代表班のテーマは、
「方言に宣伝効果はあるのか~方言の経済効果の可能性~」「洋楽においての方言の活用について」「小学校の英語教育は小学生の英語力を向上させるのか」(ゼミA)
「匂いと心」「ストレス」「ストレスの解消方法」(ゼミB)
「視覚または聴覚のみの記憶力」「国境を超えるオノマトペ」「登下校時のバス停での効率化について」(ゼミC)
「音の波形の類似性に関する研究」「結露しにくい表面条件の特定」「ダ・ヴィンチの橋の仕組み~耐荷重の限界~」(ゼミD)
「心拍数と体調の関係性」「ブルーシートの破片を追う!!」「モチベーション維持向上」(ゼミE)
先週までに各講座内での発表で用いたスライドを大きく印刷し直したポスターを見た時は、発表者たち自身も歓声を上げていました。



生徒の中には、大学主催の研究発表会に参加し、他校生の指摘を受けるなどして自身の探究をブラッシュアップした者もいます。
1年間取り組んできた成果を発表する代表者、プレゼンを聞いて更なる疑問をもつ聴衆、学友の取組みを通して自分自身の学びに刺激を受ける生徒たち。宝塚北高生として、意義ある学びの時間となりました。