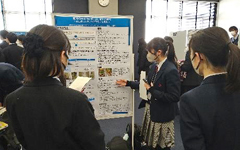2023年3月3日(金)
GS科2年生がシスメックス株式会社(Sysmex)へ企業見学に行きました。初めにシスメックスの概要説明をしていただき、その後、会社内を見学させていただきました。最後に、がんゲノム医療のことについて講義をしていただきました。
国内だけでなく、海外でのシェアも高く、会社の中で海外の方も多く働いている様子も見学させていただき、広く世界で展開するためには多様でグローバルな視点が必要だと感じました。
これまでGS科の校外学習会では企業見学は行われておらず、初めての試みでありましたが、大学卒業後の進路への視野を広げる良い機会となりました。シスメックス株式会社の皆様、ありがとうございました。