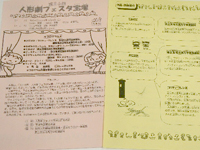4月18日(木) 於 ピッコロシアター大ホール
卒業公演を2ヶ月後に控えた演劇科3年生が、上演会場となるピッコロシアター大ホールの下見を行いました。まずは、劇場職員の方より、ピッコロシアターの成り立ちや劇場の特徴について説明を受けました。その後、それぞれの担当ごとに上演を想定し、舞台の隅々まで、気になることを念入りにチェックしていきます。講師の先生方からも機構の説明や実際の見え方・見せ方についてのアドバイスをいただきながら、確認していきました。
実際に舞台に立ってみて分かったことも多く、これから考えるべき課題も明確になってきました。ぜひ、この経験を上演に生かしてほしいと思います。
なお、今年の卒業公演は6月15日(土)を予定しています。
中学生及びその保護者の方で観劇を希望される場合は、5月上旬に本校ホームページにおいて、観劇申込みのご案内を開始する予定です。
本校生徒及び保護者の方については、後日、ご案内いたします。