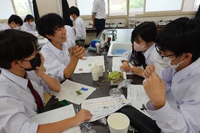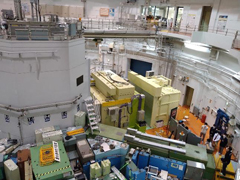令和5年6月18日(日)
GS科の3年生による「課題研究発表会」を兵庫県立人と自然の博物館ホロンピアホールで実施しました。GS科では1年生の時に、自分たちでテーマを設定し、2年生から本格的に研究を開始し、3年生の6月にその成果を発表します。各研究班はステージでの口頭発表(英語によるアブアストラクトの発表を含む)とホワイエでのポスターセッションを行いました。
次の方々に審査員として来場していただきました。
口頭発表審審査
・大阪大学理学研究科 教授 久保 孝史 先生
・兵庫県立大学減災復興政策研究科 教授 馬場美智子先生
・関西学院大学工学部 教授 山本 倫也 先生
・神戸大学大学院理学研究科准 教授 佐倉 緑 先生
・兵庫県立人と自然の博物館 研究員 鈴木 武 先生
ポスター審査
・京都大学理学研究科 名誉教授 馬場 正昭 先生
・甲南大学理工学部 教授 山本 常夏 先生
・神戸女子大学文学部 特任教授 宮垣 覚 先生
さらに、本校生の保護者、卒業生6名、本校教員が審査を行いました。
発表テーマは次の通りです。
・安定性の高いジャイロ2輪車の製作
・ダイラタンシー流体の剪断増粘性による周期的な応力の検証
・尾翼の形状と迎え角の関係
・黄金比と白銀比の考えを用いた西洋数学に対する和算の利点
・「碁石拾い」の解法数を算出できるプログラムの作成
・竹林の拡大と地理的要因の関連性
・アスファルトへの遮熱性舗装と白い塗装の性質の違いと最適な舗装方法の検討
・ヤドカリの交替性転向反応
・障害物に接した時に植物が見せる挙動
・植物の再生後の変化に関する研究
・ホウレンソウ葉表面の白色顆粒の生成過程および虫に与える影響
・芯切り不要な和蝋燭の開発
・硝酸銅(Ⅱ)水溶液が電気分解で緑色に変化した理由を探る
3年生はこの後、研究内容を論文にまとめ、様々な科学コンクールに応募していく予定です。
審査に来ていただいた方々に厚くお礼申し上げます。