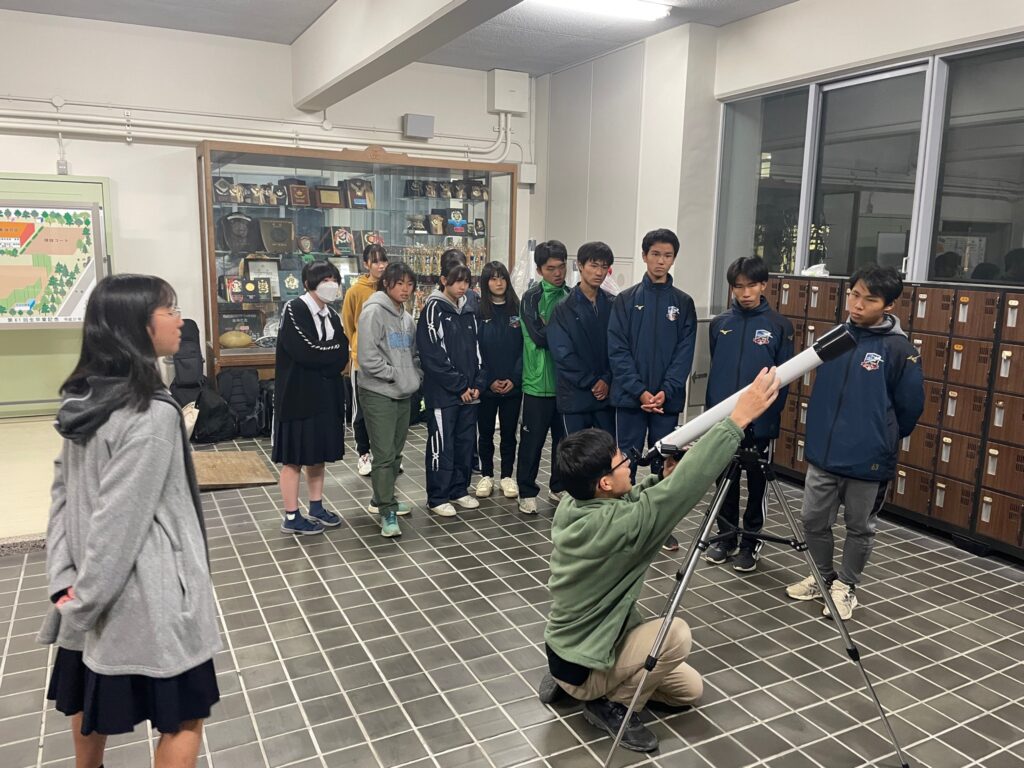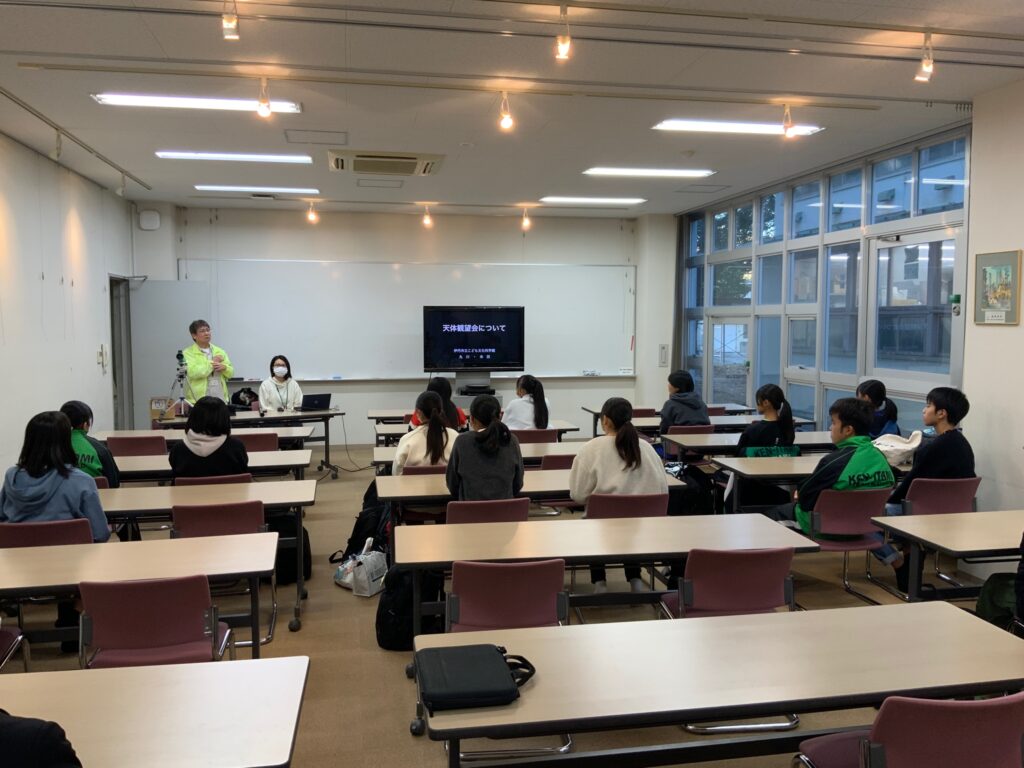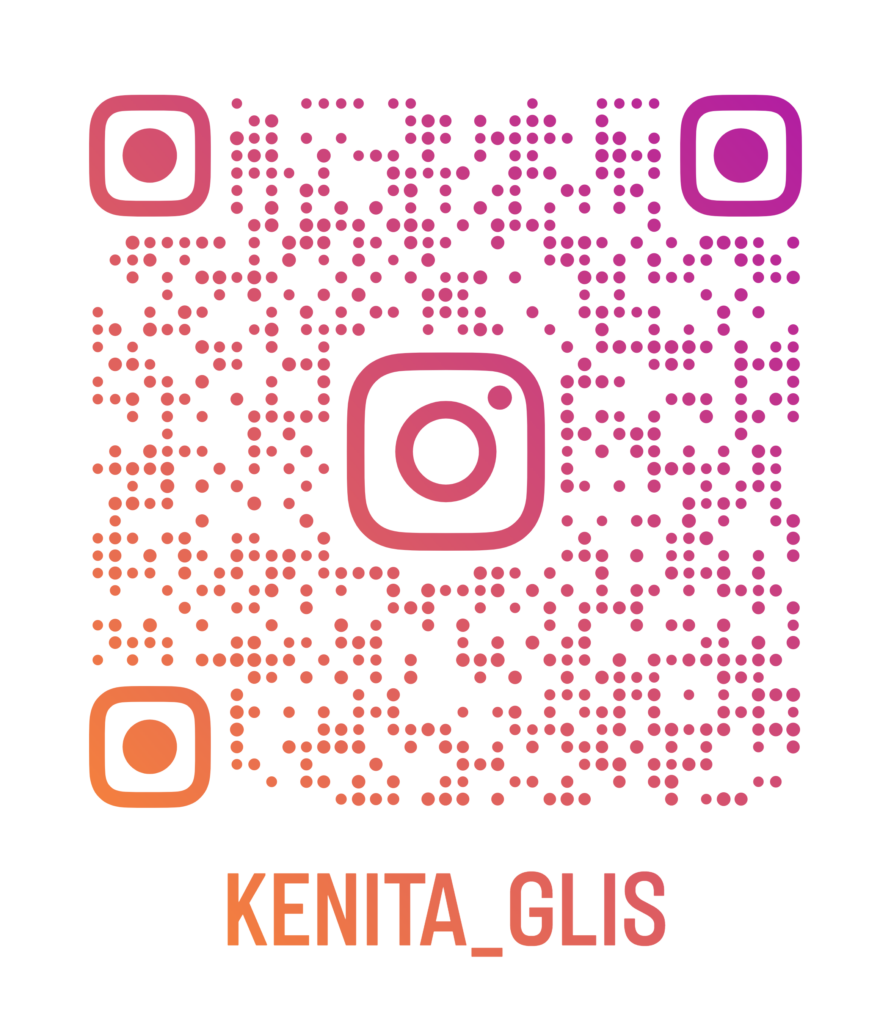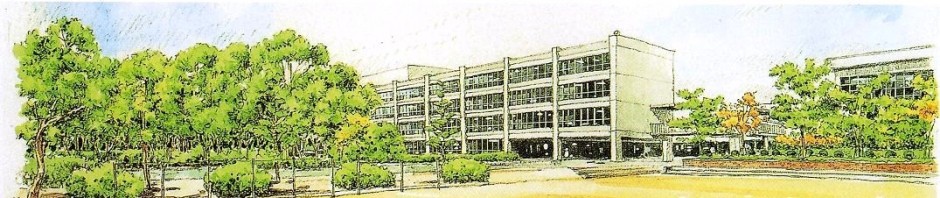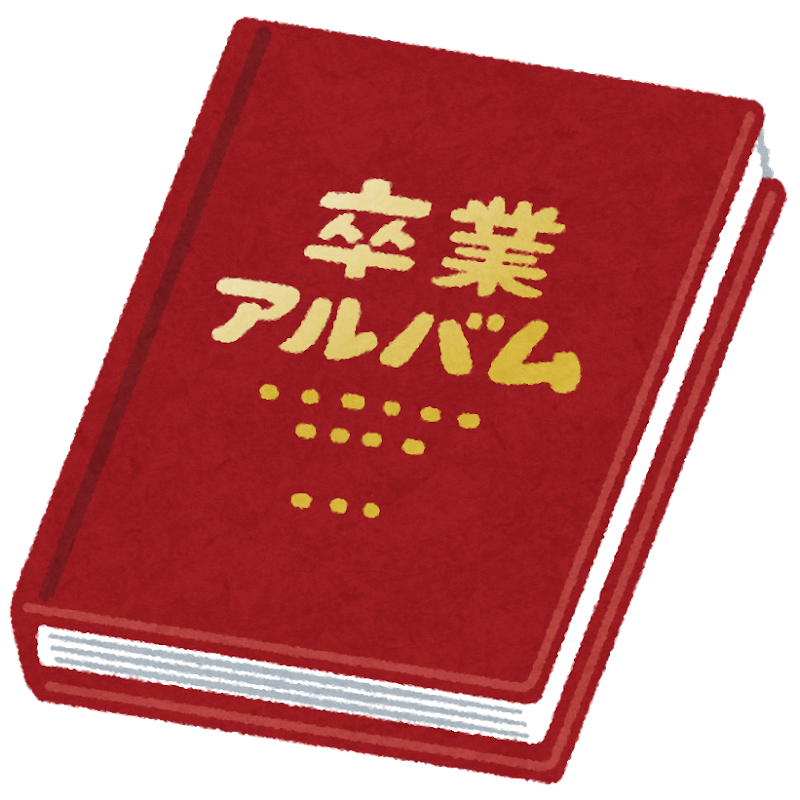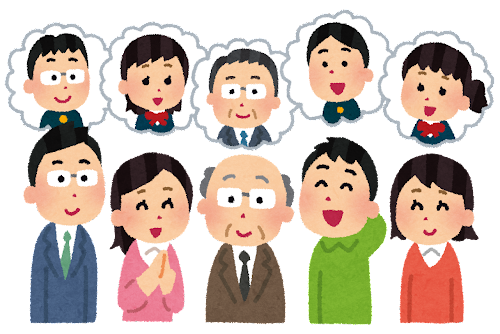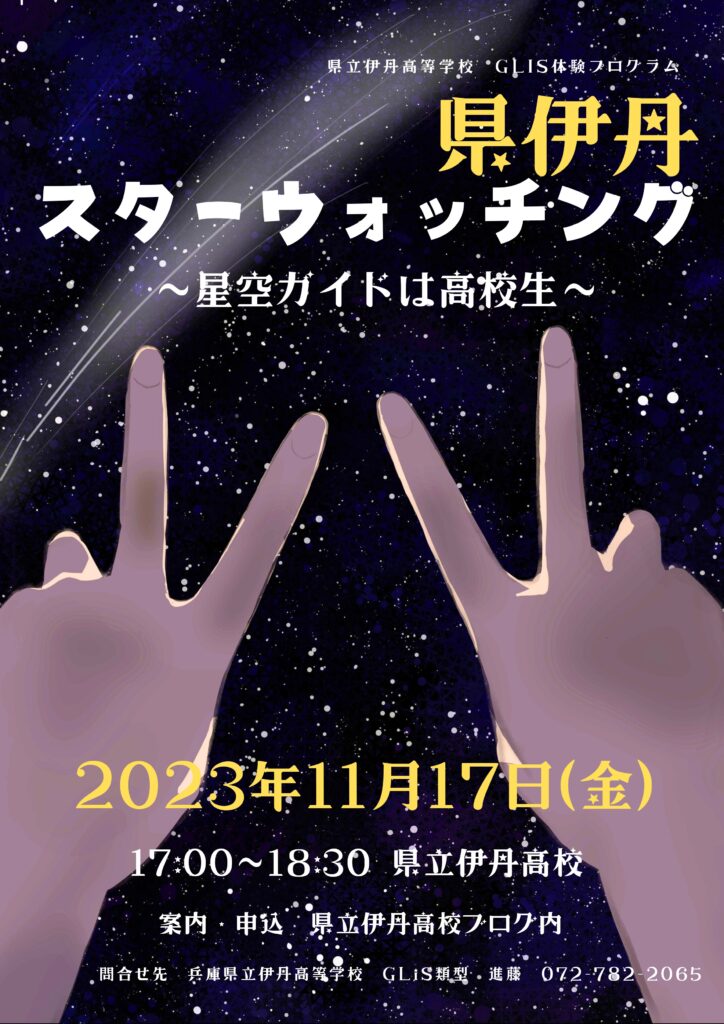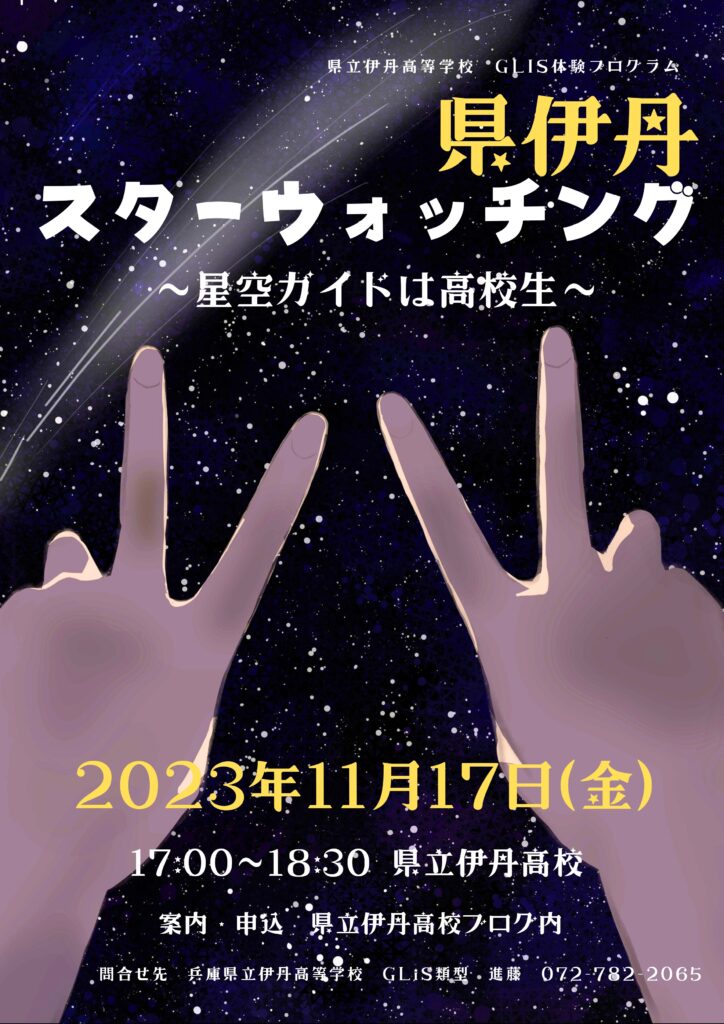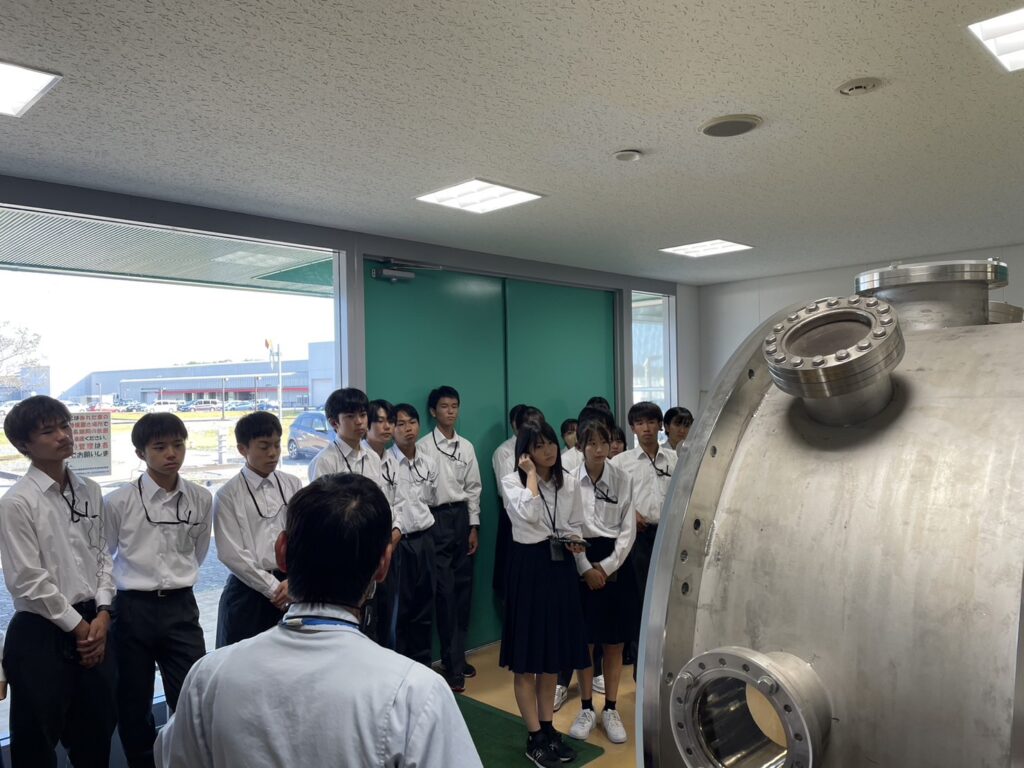関東緑窓会に参加してきました
10月29日(日)に関東緑窓会親睦の集いが催されました。
新宿のホテルに前泊していた私は、窓を打つ雨の音で目が覚めました。思わずテレビで天気の確認。昼からは晴れの予想。傘を買う必要がなくなり、ほっと一安心。
会場の日本製鉄代々木倶楽部は日本製鉄の保養と研修の施設ということで、大きな窓から緑の庭が望める大広間は格式とモダンさを兼ね備えた素敵な会場でした。
 伊丹の思い出
伊丹の思い出
関東緑窓会名誉会長でいらっしゃる中学44回生の加藤様(御年93歳)とお話しする機会を得、県高への熱い思いと懐かしいお話を伺うことができました。高校17回生で現会長の正賀様も関東緑窓会では若手の部類とのこと、みなさんが「校長先生は60歳ですか。お若いですね」とおっしゃる理由が飲み込めました。
11月1日(水)にコロナ禍が明けて初の全校朝礼を行いました。そのときに関東緑窓会でお世話になったお話を校長講話として以下のように話しました。
全校朝礼 校長講話
みなさんおはようございます。久しぶりの全校朝礼ということなので、この機会に私からいくつかの報告と、みなさんへのお願いをしたいと思います。
この日曜日、10月29日に東京で「関東緑窓会親睦の集い」が催され、出席してきました。関東で活躍されている本校の卒業生が年に一度、総会を兼ねて行う会ですが、コロナ禍もあって4年ぶりの開催ということでした。中学44回生で93歳の大先輩から県高への熱い思いを聞かせていただき、遠い関東の地でもみなさんが母校を愛し、応援してくださっていることを知り、ありがたさと心強さを感じました。現在会長をされている正賀様は高校17回生で、「私の年齢でも関東緑窓会の中では真ん中より下です」、「校長先生は60歳ですか。お若いですね」とおっしゃったのがとても印象的でした。どこの学校もそうですが、同窓会が高齢化しています。若い卒業生が同窓会活動に参加されることを切に願っておられました。
参加されている方の中で、築山広場の「天仰石」と60周年記念碑に刻まれた詩の作者である甲川様のお嬢様がおられました。懐かしそうに「家の庭にあった石を寄付するって持って行った」と、天仰石のお話を聞かせてくださいました。甲川様の思いと、その思いが脈々と受け継がれている築山が整備されたことをたいへん喜んでおられました。
今年は日曜日と重なったため、お話しする機会がありませんでしたが、10月15日は本校の創立記念日でした。121年目を迎え、その記念事業である「築山の整備」が終わりました。生徒のみなさんには是非築山頂上の広場に上がって、天仰石と60周年記念碑に刻まれた先輩方の思い、そして県高の伝統のすごみを感じてもらえたらと思います。
帰りの新幹線。まどろみながらもふと車窓に目を向けると、頂に雪を湛えた富士が雲間から姿を現しました。関東緑窓会の皆様との宴の余韻を、壮麗な富士とともに楽しむことができました。皆様本当に有り難うございました。