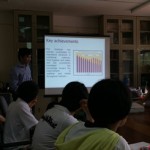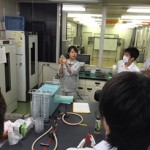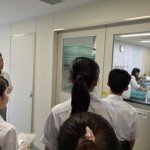神戸市立真陽小学校において、「地震に強いまちづくり」をテーマに研究をしている3班が、真陽防災コミュニティー・長田消防団第七分団が主催する水難救助訓練にボランティアとして参加しました。以下は生徒の感想です。
僕たちは真陽小学校にて水難救助について学んできました。実際の防災訓練に参加して感じたことは、防災をしていく上でも人とのつながりは、大切だということがわかりました。今回の防災訓練はたくさんの子供たち、大人の方々が参加されており、地域のひとのつながりがこのようにたくさんのひとを呼んできているのだとおもいますし、実際に体験したことを子供は親に伝え、大人は同僚などに伝えることでさらに防災意識が広がっていくということを実感しました。参加した側としては、自分の身を自分で守ることは難しく、周りの手助けがあることで初めて生存できるのでは?となりました。今後の活動方針としては防災教育にいきたいと思っています。地震に強い町というテーマとは少し違うかもしれませんが、班員との話し合いで防災教育をしていくときめました。