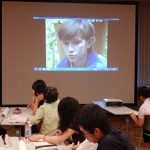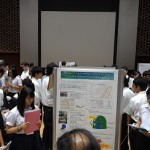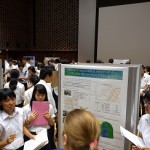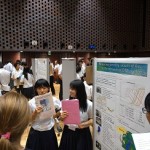大阪国際交流センターにおいて、グロバルリサーチⅡ受講生(2年)2名が、「ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 2016」の高校生実行委員として、第1回高校生実行委員会に参加しました。今回は2日間連続で実施し、ワンフェスユースの実行委員としての基礎的な力を育みました。また、2015年の実行委員も参加し、昨年の引き継ぎも行われした。
〈1日目のおもなプログラム〉
ワンフェスユースと高校生実行委員会の概要説明、NGOや国際協力活動の概論、昨年度の改善案や本年度の目標設定・共有、実行委員長、副委員長、書記の決定
〈2日目のおもなプログラム〉
NGOスタッフによる活動紹介(①「テラ・ルネッサンス」②「日本国際民間協力会(NICCO)」)、イベントの全体テーマの決定、プログラム案と担当の決定
今年のテーマは「見方が変わる!世界も変えちゃう!」に決まり、本校生徒の役割は広報担当&広報のミニプログラムになりました。
〈生徒の感想〉
今回感じたことは主に4つあります。1つ目に、一見バラバラで共通点が無いように見える17の目標も、よく見てみるとほぼ全部が繋がっていて、『この問題を解決すると必然的にこれも視野に入ってくる』といった考えがみんなで話し合うことで出てきて、他の人の違う視点を知れるのがすごく新鮮でした。2つ目に、衝撃的な内容もあったし、腕や足を地雷でなくしてしまった子供の写真には心が痛みました。私が今ポスターセッションで調べているのも子供の義務教育を受けられない問題なので、世界的にもっと子供の待遇が良くなればいいと思ったし、私自身も何か活動したいと思いました。3つ目に、一つ一つの話がとても細かくて、中でも井戸建設をしたあと、井戸から漏れたあまり水を井戸の隣につくった畑に供給されるよう水路を作るのは、無駄も無くなるし作物も育てられるのでとても有効な案だと思いました。発展途上国で難しい作物の生産が続かないのは手間がかかるからという理由を知り、この解決法を見つけていかなければいけないと感じました。最後に、テーマを決めるのにとても時間がかかって、どういったものが興味の無い人を惹きつけるワードになるかを考えるのが予想以上に苦労しました。また、ターゲットを 興味が無い人・興味はあるが自分から行動しない人・将来国際関係の仕事に就きたい人 の三段階に分け、それぞれが満足して終わるようなプログラムを考えるのも大変でした。
今日の会議では最初にアイスブレイクという簡単なゲームをしました。そのおかげで場の空気が少し和み、人の顔も少しは覚えられたかなと思います。途中の講義で、NGOの説明をされました。その中でODAの話も出てきました。NGOとODAのことがどっちがどっちかわからなくなりODAとは何ですか?という質問に応えられませんでした。なので、ちゃんと自宅等でもう1度把握し直す必要があるなと思いました。昨年の先輩方のワンフェスの振り返りを聞いて、やはり大変そうだな、自分にできるのかな、と不安に思いましたが、なんだかんだで形にはなるとも言われたので、自分に出来ることをしようと思います。また、書記にもなったので、どのような仕事をすればいいのかはまだよくわかりませんが、良いワンフェスを作っていけるよう尽力したいと思います。