バツー洞窟


また、ヒンドゥー教の大祭タイプーサムもこの洞窟が舞台となり、信者たちが体のあちこちに針や串鉄を刺して行列する様は圧巻です。

インド風のパン、ロティ。日本でも馴染みのナンと違って、もう少し薄く弾力があります。
テータリッの作り方も独特ですが、ロティの作り方も見ていて飽きません。
生地を伸ばして薄くなってくると、そこにクルクルと回す技が盛り込まれ、ひっくり返しては天板にひっつけることを繰り返しながら、最後には広げた生地をスピーディーに四角に折りたたんでいきます。
これを焼き用の鉄板の上に投入し焼いていく行程には作り手独特のリズムがあり、それだけで食指が動きます。
とどめには、焼きあがったロティを天板の上で水平方向に左右の手でバコンと叩いてつぶすのです。
このロティをちぎって様々な種類のカレーソースにつけて食べるのがロティチャナイ。
カレーソースも、辛いのから辛さ控えめのものまで店によっていろいろ。
写真のセットは、ロティチャナイとテータリッで合わせて約50円という安さ。
マレーシアでは朝食やおやつとして食べるのがポピュラーな食べ方です。

1911年時点での人口比率は、マレー人53%、華人34%、インド系10%。独立後最初の内閣はマレー人6、華人3、インド系2で構成され。人口比とほぼ同じです。
「ラーマンとマハティール」(岩波書店)によると、多民族国家形成の裏側には以下のような歴史があります。
英国人:200年続いた英国の植民地支配。独立後も貿易・金融を握る。
中国系:英国とのアヘン戦争で敗戦した中国からの移民が認められ、スズ採掘の出稼ぎに来て定着し、その勤勉さからマレーシアの商工業を支配する。
インド系:英国は、アマゾンから持ち込んだゴム苗木でマレーシアを世界一の天然ゴム産出国に変えたが、ゴム農園の労働者として英国植民地から連れてこられた。
◎植民地支配とスズ・ゴムの2大産業により多民族国家は形成された。
<中国の佛教寺院>




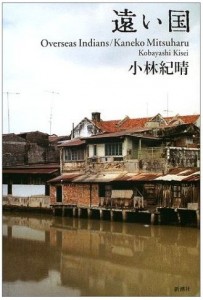
女たち。
チリッと舌をさす、辛い、火傷しさうな
野糞。
金子光晴の詩が突然文中にあらわれる。
その詩に使われている言葉は簡単なものであるけれど、わたしには容易に理解しがたく、それが気持ちの落ち着かない理由となっていた。
小林紀晴の旅は、金子光晴の追憶の旅でもあった。
わたしは「遠い国」で初めて金子光晴という詩人の名を知り、読み終えた後、今度は金子の旅を追いかける。