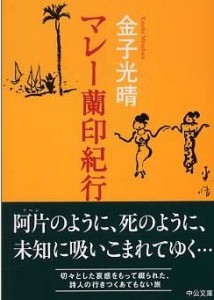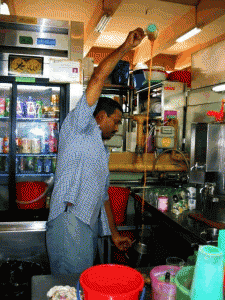「遠い国」(小林紀晴)には、アジア各地のインド人街でのはなしが編みこまれている。
華僑は中国本土以外で生活する中国人を呼ぶ時によく使われるが、「印僑」という言葉をあまり耳にすることはない。(ちなみに日本語変換をしてみても、かきょう(華僑)はすぐに出るが(いんきょう)では一発変換してくれない)
ざっとみて、中国の人口12億、インド10億、日本1億2千万、マレーシア2300万。
こうしてみても面白い並びになるけれど、インド人は東アジアに住む日本人にとっては中国人と比較しても身近さはあまり感じられない。
マレーシアに渡ってきたインド人は南インドからの人達が多く、タミール語がよく話されているとのこと。インドではヒンドウー語がポピュラーな中、マレーシアのインド人たちには、文字も丸くなるタミール語となる。これも不思議なことだ。
自国ではない土地に中国人と似たような境遇でインド人がマレーシアに渡り住み着く歴史を知ると旅での感じ方も少し違ったものになってくる。
「遠い国」には、昭和初期、放浪する日本人詩人がマレーシアに流れ、どんな時間を過ごし、何を考えていたかということがところどころに描写してある。
「金子光晴」という名前だけは知っていたこの詩人は、中国人とインド人がやってきたマレー半島に同じように流れ着いた日本人、すなわち自分自身のことを書き残している。
小林紀晴は、金子光晴の文庫本「マレー蘭印紀行」を手に、金子が過ごしていたというジョホール州バトウパハの元日本人クラブを訪れる。
しかしながら、幾年もの時間が過ぎ、ようやくたどり着いたその場所で、小林は金子の幻影を見ることはできなかった。