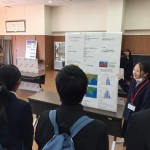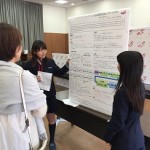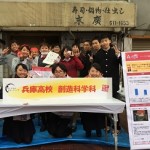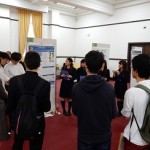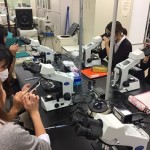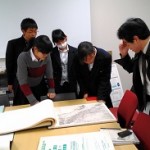【数学】
本校の学科コース準備室において、本校教員による7回目の探究活動を行いました。数学Bの教科書を利用して、前回に予定していた正規分布についての授業する予定でしたが、生徒2人の研究の進捗状況を尋ねてみると、11月2日の状態とほとんど変わっていないということで、また急遽、パソコンによってネットを利用しデータを取る作業を行うことになりました。アメリカ大統領選挙開票の時間であったために、インターネットの動きが鈍く、操作がやりにくいというハプニングもありました。生徒の一人は、サザエさんのじゃんけんのデータを取っていました。もう一人は卓球の試合のポイント取得のデータを取っていました。データが揃い次第、統計的な処理を行っていく予定です。

【化学】
本校化学教室にて行われた化学7回目の探究活動は、神戸大学大学院理学研究科准教授 大堺利行氏に来校していただき、前回と同様の実験を行いました。正極探究チームは、ポンプから供給する酸素の還元反応の進行を促進するために、酸性溶液である硫酸・酢酸・シュウ酸の溶液を用いて実験しました。その結果、シュウ酸溶液中でポンプから酸素を供給すると約0.7Vの電圧を確認することができました。そこから、シュウ酸を多く含む身近な溶液を考え、緑茶、紅茶、ぶどうジュース等での測定も行いました。負極探究チームは、付近の山や川から採集した泥を還元剤としてKCL溶液に混ぜたものを用いて測定を行いました。結果、電圧値が約0.2Vしか得られませんでした。泥の採集日が古く、酸化がすすんでしまったためだと仮定し、近くの公園で泥を採集しなおし、再び測定を行いましたが、大きな電圧値の変化は得られませんでした。


【物理】
物理を研究している6名は大阪大学大学院理学研究室の下田研究室を訪問し、前回の授業で滴下する高さや液体の深さ、液体の粘性など、条件を変えて撮影した映像を用いて、ミルククラウンの数を数え、エクセルを用いてデータを分析しました。最後にデータをまとめたグラフを全員で解析し、クラウンの数と滴下する高さ、液体の深さに相関関係がみられることを発見し、物理的な見解について話し合いました。また液体の粘性にも何か関係性があるようにも考えられ、次週以降、さらに条件を変えてクラウン数との関係性について考えていくことにしました。最後に下田先生からのアドバイスで、クラウンができるときの円の直径にも関係があるかもしれないと指摘を受け、次回考察していく予定です。6名の男子が役割分担をしっかり行い、質の高い実習ができました。


【生物】
神戸大学洲崎研究室を訪問し、同大学大学院理学研究科准教授 洲崎敏伸氏と共に、電子顕微鏡によるミドリムシの構造観察を行いました。多数のミドリムシ切片像のなかから、研究テーマに合致した、眼点や光受容体を持つサンプルを探しだし映像を保存する作業をしました。慣れない顕微鏡操作に苦労しながらも、必死でサンプルを探し、適当な映像をみつけ出しました。次回からは、兵庫高校にて顕微鏡観察、および具体的な実験デザインを作成していく予定となります。



【都市工学】
本校同窓会館ゆ~かり館において、本校教員による7回目の探究活動を行いました。先週の大阪大学でのプレゼンに対する助言をふまえて、研究テーマ案ごとに、実際に実行する項目を確認しました。特に、現地の方々とのコンタクトおよびヒアリングにおいて、現状を具体的に把握し、今後の進め方に反映したいことが、両テーマで挙げられました。必要項目として、「傾斜市街地のモビリティ」では、生活動線や住民の方の不便だと考える点など、「長田区の防災について」では、自治会での役割分担や、避難ルートの確認、避難訓練の有無などが挙げられ、再確認できました。今後は、区役所を通じて紹介いただいた代表者とのコンタクトを行って、ヒアリングの仕方を検討してきます。一方で、自分たちで統計データを入手したり、傾斜地の地形について具体的に計算をするなど、できることを進めていく予定です。