1年生理数科の「自然科学基礎演習」の授業で、大学・研究機関からの出張講義として、かがく教育研究所(ファラデーラボ)より講師の先生に来ていただき、ファラデーの講演「ロウソクの科学」の再演を行っていただきました。
1860年にロンドンでマイケル・ファラデーが行った有名な講演を、ファラデーが話した言葉を忠実に再現し、全て英語で講演してくださいました。
1年生理数科の「自然科学基礎演習」の授業で、大学・研究機関からの出張講義として、かがく教育研究所(ファラデーラボ)より講師の先生に来ていただき、ファラデーの講演「ロウソクの科学」の再演を行っていただきました。
1860年にロンドンでマイケル・ファラデーが行った有名な講演を、ファラデーが話した言葉を忠実に再現し、全て英語で講演してくださいました。
1年生理数科自然科学基礎演習でミニ課題研究のポスター発表会が行われました。
10班がそれぞれの研究をポスターにまとめ発表し、活発な質疑応答も行われました。
各班の課題研究タイトル:
自然科学部地学班真砂土チームが第9回益川塾シンポジウムで塾頭賞を受賞し、18日に京都産業大学で表彰式・発表会に参加しました。
タイトルは「花崗岩の風化度基準の定量化を目指して」です。
※ノーベル賞受賞者の益川先生より直接表彰されました。
:真砂土チーム
東森碧月(2)・田村笙(2)・岩本南美(2)・田島晴香(2)
中野美玖(1)・尾藤美樹(1)・中野勝太(1)
自然科学部物理班粉粒体チームが、第11回朝永振一郎記念「科学の芽」賞(高校生部門)を受賞し、17日に筑波大学で表彰式・発表会に参加しました。
作品タイトルは「『粉体時計』の実現報告及びそのメカニズムの数理的考察」です。
※「科学の芽」賞は、全国3,000件超えの応募の中から3件が選出されました。
:粉粒体チーム
國澤昂平(3)・友野稜太(3)・伊東陽菜(3)
三俣風花(2)・岡部和佳奈(2)・荒谷健太(2)・大西巧真(2)・籠谷昌哉(2)
平成28年度SSH講演会が開催されました。
今年度は東京大学大気海洋研究所の佐藤克文教授に、「バイオロギングで探る海洋動物の行動と環境」と題して講演をしていただきました。
動物搭載型の記録装置を使って動物の行動や周辺環境を測定するBio-Logging(バイオロギング)という手法を使って分かったウミガメやオオミズナギドリ等の行動生態について、大変興味深いお話を聞かせていただきました。
最後の質疑応答では、多くの生徒の質問に丁寧にわかりやすく答えて頂き、大変有意義な講演会でした。
12月考査最終日、1年生理数科の生徒が兵庫県立人と自然の博物館へ研修に行きました。
収蔵庫を見学させていただいたり、学芸員の方から様々なお話を聞かせていただき、大変有意義な研修でした。
平成28年8月26日(金)に、中国文化大学(台湾台北市)で開かれた国際都市計画シンポジウムで、3年理数科の研究チーム一班が口頭発表を行いました。
発表タイトルは
Using Hydrodynamic Modeling and Simulation to Advance
Proposed Greening Activities of the Kakogawa Riverside
(加古川河川敷の緑地計画について)で、メンバーは以下の通りです。
瀧本真裕君、友野稜太君、長谷川夏海さん、原菜月さん、福田幸音さん、藤原彩菜さん。
今回参加したAsian-Pacific Planning Societies 2016国際会議(ICAPPS)とは、1994年以降、国際的な学術交流活動の一環としてアジア・オセアニアを中心とした各地域、各都市の研究者、および実務者の参加によって実施されている国際都市計画シンポジウムです。シンポジウムの参加者は、アジア・オセアニアにおける都市・地域計画分野をリードする研究者で、論文発表をする学生・大学院生にとっては、当該分野の第一人者と直接議論することができ、国際的に最先端の研究現況を理解する契機となります。
日頃からの生徒たちの努力により、事前の英語論文審査を見事通過し、学術誌に研究論文が全文掲載されました。さらに、初の高校生発表のため、主催者側から特別に口頭発表を依頼され、発表内容は参加者や台湾の関係者より高い評価を受けました。これに伴いステージでは急遽記念品授与も実施されるなど、今回のシンポジウムで重要な役割を担いました。

2年生理数科は水曜日に課題研究の時間が設けられています。
この班は地学班で「付加体(大陸のプレートとプレートの間に溜まった堆積物)で知る地質と水の関係」~おいしい水を求めて~という研究をしています。この研究が上手くいけば、地層を見るとおいしい水が出るかどうか分かるようになるそうです。


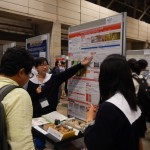



5月22日に幕張メッセ国際会議場にて行われた日本地球惑星連合大会2016、「高校生ポスター発表」の部に地自然科学部より地学班と物理班が参加しました。
それぞれの班の発表内容は
地学班:真砂土チーム「花崗岩の風化が及ぼす土砂災害への影響」
物理班:微小重力チーム「宇宙実験用ピペット開発のための、校内微重力実験装置の改良」
です。そのうち真砂土チームの「花崗岩の風化が及ぼす土砂災害への影響」が
本校2年連続となる優秀賞を受賞しました。
また、会場ではNASAによる講演もあり、ポスター発表していたところ来場していたNASAの職員に質問を投げかけられました。大変貴重な体験もすることができました。


京都教育大学より村上教授をお招きし、1年生理数科へ自然科学基礎演習特別講義を行っていただきました。
内容は、紙コップにお湯を入れると底面にくもりが生じる現象の原因を探るという実習、講義です。
色々な方法を試したり議論しながら各班、結論を導き出していたようです。