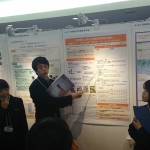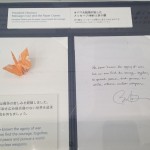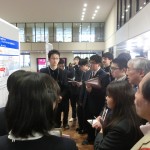大阪YMCAにおいて、「 ワンワールドフェスティバル for Youth2017」が開催され、普通科グローバルリサーチⅡ受講生(2年)の2名が実行委員を、1名がボランティアリーダー務めました。これまで、月1~2回の実行委員会で企画を練り、本日イベントの当日を迎えました。実行委員を務めた本校生徒は、講演プログラム「子どもたちへの教育支援~途上国を救え~」を企画担当し、当日は司会およびパネラーとして講演に参加しました。
また、創造科学科2期生(1年)10名、普通科グローバルリサーチⅠ受講生(1年)25名が、当日の運営を手伝うボランティアとして参加しました。
イベントについては以下のホームページをご覧ください。
ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 〈外部サイト〉
当日、たくさんの方にご参加いただき、ありがとうございました。
〈生徒の感想〉
去年は当日ボランティアとして参加したワンフェスに、今年は実行委員として関わることが出来ました。実行委員として7月から準備を進め、なかなかうまくいかないことも多く苦労しました。兵庫が担当するプログラムでは、当初予定していた内容から2転3転し、最後の1週間まで調整を続けました。苦労も多かったですが、ワンフェス当日は、たくさんの方が私たちのプログラムに参加して下さり、心から頑張ってよかったと思いました。そしてなにより私たちが楽しむことが出来たのが良かったです。去年はただ参加するだけでしたが、今回企画する側に回って、はじめて一つのイベントを作り上げる大変さや、難しさ、苦労や、達成感を味わうことが出来ました。今回のワンフェスに実行委員として参加することができ、とてもいい経験になりました。
7月から高校生実行委員として集まるようになって最初は「当日しっかりできるかなあ」という不安しかありませんでした。企画を考えるうえで様々な困難にぶつかりました。講師依頼を受けてくれなかったり、なかなか企画内容に納得がいかなかったり。当日の内容は7月に考えていたものとは全然違うものでした。でもそれが最良のものであることに間違いはないと思うし、このイベントが成功してよかったと思います。また、自分たちの企画のアンケートで「参考になった」という回答が多かったこと、参加者数が多かったことも本当にうれしかったです。やりがいを感じました。いろいろな面において、自分を成長させてくれたイベントでした。この経験は決して無駄にならないと思います!!
今回僕は、8月からワンフェスのボランティアリーダーとして関わらせてもらいました。はじめの1ヶ月は自分の役割も決まらず、正直苦労しましたが、この12月に入ってからリーダーに一体感が生まれ、当日は責任をもって活動することができました。当日は全体の司会進行と音響を担当し、恐ろしく忙しい1日になったと思っています。今回のように、長い期間をかけて取り組んできたイベントは、達成感も段違いだなと感じました。この経験を生かして、将来いろいろなところでリーダーシップを発揮できたらなと思います。
1日ボランティアとして、各ブースのお手伝いをさせていただきました。僕たちの班は、カフェで、食券の受け取り、配膳などの仕事をさせていただきました。どの店でも様々な国の、普段見たことのない料理を食べることができ、とても楽しかったです。お店の方とお話しすることもでき、いい経験になりました。ボランティアの仕事以外の時間は、各ブースを周りました。どのブースも国際問題について深く考えることができ、多くのことを学ぶことが出来ました。また、機会があれば参加したいなと思いました。
今回、ワン・フェス・ユースに参加してまず、想像以上にたくさんの団体が、難民問題や世界の貧困問題を良くしようと活動しているということに驚きました。2階のブース展示では多くの団体の活動内容を自由に回れたので良かったです。実際に私もフェアトレードの製品を購入したり、プロジェクトに参加したりして、少しだけだけど、活動に携われたので嬉しかったです。特に私が印象に残ったのは、ボランティア中に聞いた、タイにインターンされた学生さんのお話です。歳は私の1つ上なのに、母国であるタイにインターンして日本語教室を開いたり、SNSで世界の問題や出来事を発信したりしていて、本当にすごいなぁと思いました。今日聞いたお話は同年代の方が多く、私ももっと頑張ろうと刺激を受けました。たくさんのことを知れた良い機会だったので、来年の活動に向けてさらに考えていきたいです。