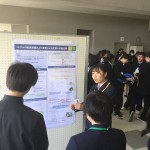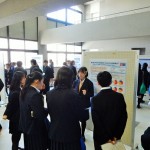8月行事予定
13(火)~15(水) 閉校日
21(水)~22(木) オープンハイスクール
9月行事予定
2(月) 始業式・課題実力考査
3(火) 課題実力考査
13(金) 体育祭予行
17(火) 体育祭予行(予備日)
19(木) 体育祭
20(金)、24(火)、25(水) 体育祭(予備日)
球技大会
昨年は警報による休校の影響で中止になった1学期
球技大会ですが、今年は大丈夫でした...
が、グランド状態不良のため、サッカーは残念ながら
中止。男女とも体育館でドッジボールを行いました。
結果は....(実施日 7月17日)
1位 7組
2位 5組
3位 2組 でした。


まずは準備体操


さあいくぞ 試合開始!


熱戦を繰り広げました
合唱コンクール
10(水) 合唱コンクールの学年予選を行いました。
結果は....
1位 8組
2位 2組
3位 4組 でした
クラス紹介の部...
1位 2組 でした


1組 2組


3組 4組


5組 6組


7組 8組

2組のクラス紹介
12(金) 合唱コンクールの決勝が行われました。
2年生代表は、予選を勝ち抜いた8,2,4組。
結果は....
4位 2組
5位 8組
6位 4組 でした。


2組 8組

4組
保護者会・クラス懇談会
7月4日(水)に実施しました。お忙しい中、
多数のご参加ありがとうございました。
ご欠席のご家庭にはお子さまを通じて資料を
配布させていただきました。
ご不明な点などがありましたら、お知らせください。
7月行事予定
2(火)~8(月) 期末考査
4(木) 保護者会・クラス懇談会【出欠のお返事は6/21締切です】
9(火) 英語試行テスト
10(水) 合唱コンクール学年予選
11(木) 学年集会
12(金) 合唱コンクール決勝
13(土) 全国模試
16(火) 避難訓練
17(水) 球技大会
18(木)ワックス掛
19(金) 終業式
22(月)~30(火) 前期講習(希望者)
大学・学部学科説明会
6月13日、大阪大学から講師の先生をお招きし、文系・理系別にお話を伺いました。これから具体的な学部や学科を決めていく時の手がかりとしていきたいと思います。


文系 理系
春季定期戦
5月8日春季定期戦が実施されました
勝ちました!!
_________ 兵庫 神戸
ソフトテニス(男) ○4 1
ソフトテニス(女) 2 ○3
バレーボール(男) 0 ○2
バレーボール(女) ○2 1
サッカー 2 ○4
野球 ○11 4
柔道 (オープン競技)
3-3ですが、メイン競技の野球が勝ちましたので、
総合優勝は兵庫。



開会式 ソフトテニス(男)



ソフトテニス(女) バレーボール(女) バレーボール(男)


サッカー 野球


応援風景
文化祭
4月26日(金)に校内祭、27日(土)に一般祭が実施されました。
2年生は例年通りに校舎内での食品販売、遊戯場、お化け屋敷での参加でした。
熱心に準備に取り組み、当日も大きな混乱もなく、来場者に楽しんでいただくことができました。
来年は、屋台での参加となります。パワーアップ大いに盛り上げていきましょう!



1組 ワッフル 2組 綿菓子 3組 えびせん



4組 シューアイス 5組 パフェ 6組 ドーナツ


7組 お化け屋敷 8組 遊戯場(ゲーム)
歓迎遠足
4月12日(金) 須磨海浜公園・須磨水族園にて新入生歓迎遠足が実施されました。やや肌寒さも感じましたが、好天の中、新入生歓迎はもちろん、2年生になっての初めての行事でクラス内の親睦も深めることができました。



歓迎行事


クラス対抗行事



クラスアワーでは大嵐とハンカチ落とし

カピバラ(水族園にて)
4月行事予定
8(月) 始業式・着任式(標準服)、大掃除
9(火) 離任式・対面式(標準服)、課題実力考査(英)
10(水) 課題実力考査(国、数、理)
11(木) 平常授業開始
12(金) 歓迎遠足(須磨海浜公園・水族園)
18(木) 午前:短縮授業(40分×4)、
午後:一斉検診(内科・歯科・身体計測)
19(金) 文化祭衛生講習会
25(木) 文化祭準備
26(金) 文化祭(校内祭)
27(土) 文化祭(一般祭)
5月行事予定
7(火) 定期戦壮行会(7限目)
8(水) 春季定期戦(於 神戸高校)
14(水) 金曜日の時間割
23(木)~29(水) 中間考査