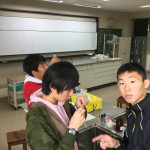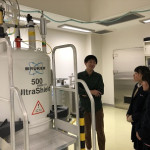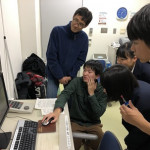大阪YMCAにおいて、普通科グローバルリサーチⅠ(1年)20名と創造科学科4期生(1年)9名、普通科グローバルリサーチⅡ(2年)2名、と3期生(2年)17名が(特活)関西NGO協議会主催「ワンワールドフェスティバル for Youth 2019」に参加した。1年生はボランティアスタッフや高校生レポーターとしてイベントに参加した。2年生は普通科生徒1名が実行委員会に選出されて企画運営に携わり、それ以外の生徒はブースにおいて授業や研究の紹介を行い、海外研修参加者は報告会にて発表を行った。












〈生徒感想〉
高校生実行委員になって私が感じたことは、おもに2つあります。まず1つ目は、私は高校生実行委員会が企画していたものの1つである「ボッチャ体験&クイズ」のプログラムのチームに所属しており、案出しからどんな時間配分でやるのか、や講師の方を呼ぶ場合誰を及びするのか、全て私たちで考え、リサーチし、つくりあげてきました。中では、上手くいかないことや行き詰まったこともあったけれど、プログラムチームの一人一人がそれぞれ違う長所を持っており、みんながみんなを助け合ったり支え合ったりして良いものを創り上げることができました。私は協調性がいかに必要かということを改めて感じました。また、本番では想定できていなかったハプニングがあったけれど、先生方の助けもいただきながらなんとか乗り越えることができました。参加者の方々がボッチャ体験を楽しそうにしていたり、クイズでパラリンピックやSDGsについて学んでいただいている姿を見て、この3ヶ月間楽しくかつ学べるプログラムを創るためにしてきた努力が報われた気がして私の気持ちは達成感でいっぱいです。2つ目は、今回、高校生実行委員会はクラウドファンディングを行いました。SNSで頻度を高くして発信したり、一人一人が知り合いに紹介したりしたことで、最初のゴールであった25万円を半月という予想だにしなかったはやさで達成し、ネクストゴールの35万円を掲げて再び広報を頑張り、見事達成することができました。また、87人もの方々にご支援いただいて、私たちを応援してくれる方がこんなにもいるのかとさらに良いイベントを創りたくもなりました。私は多くの方からのご支援がいかにありがたいかということを知りました。今回の経験で、学校では学べないようなことをたくさん学べたと思うので将来に生かしていきたいと思います。
他の学校のポスター発表を聞いたり、他団体のブース出展でお話を聞いたりして、みんな自分の活動のことをいきいきと話していて、私も他の人たちみたいに自分自身で楽しみながら研究を進めたいと思いました。研究を始めたときは、わくわくするような楽しい気持ちもあったけれど、最近は研究で迷っていたりして、始めたときの気持ちを失いつつあったので改めて、初心に帰って考えてみようと思います。また、最近は校内での発表がほとんどで、まったく初対面の人相手に話すことがなかったので、とても緊張してしまい、うまく話すことができなかったので、次に校外で発表するときには今日の反省をいかして、落ち着いて、相手の目を見ながら話せるようにしたいです。
私と同じ高校生という立場でさまざまなことに目を向けて主体的に活動されている方の話を聞くことができたり、ブースに立って興味を持ってくださった方と話をすることで、私が今取り組んでいる研究を進めるにあたっての刺激を受けることができました。私が聞いたのは海外協力隊に参加された方のお話など直接的に自分の研究に関係するものばかりではありませんでしたが、自分の気持ち次第で周囲からは難しく見えることも実行できたり、一つの課題に対しての取り組み方も着眼点を変えたりするとたくさんの案を出すことができるということがよく分かりました。これからの創造の研究は内容をどれだけ深められるかになると思うので、今回いろいろな組織の取り組みの発表を聞いて感じたことを自分の研究内容の充実に繋げていきたいと思いました。
いくつかのプログラムがあった中で、私は「ボッチャ」という競技を体験しました。これはパラリンピックの正式種目であり、私も名前は聞いたことがありました。しかしパラリンピックはオリンピックに比べメディアで扱われる機会が少なく、競技している様子も見たことがなかったため、あまり馴染みがありませんでした。しかし今回実際に体験してみると、特別な技術は必要とせず、健常者、障がい者関係なく戦えるスポーツであるということが分かりました。これを機にボッチャのみならず他のパラリンピック競技も観戦してみたいと思います。
今日は国際問題の多さに気づかされる1日だった。その上、人権問題、核兵器問題、難民問題などのさまざまなブースがあったが、どこもすぐ解決出来るような問題ではなく、しかも一国の問題でもないので、とても解決が難しいと感じた。このような国際問題を解決していくのは未来の私たちの世代であると考えた時、私は今の高校生の時期から学んでおくことが重要であると思った。高校生なりの視点で考えることができるこの時期にもっと国際問題について興味を持ち、学んでいきたいと思った。
ワンフェスユースで私はベトナムについての発表をしました。他の学校の人に発表をする機会はあまりないので貴重な経験になったと思います。スクリーンを多く見て話してしまったことが今回の反省点なのでこれからの発表ではそこに気をつけたいです。このイベントではお昼ご飯も外国の料理を食べることができ、外国の文化に触れることが出来て良かったです。午後はボッチャの体験をしました。本来はパラリンピックで行われ、健常者は行わないスポーツらしいのですがが、私たちが体験しても十分楽しめました。その後、クイズ大会をして、ボッチャについて知識を深められました。この一日でいい経験が出来て良かったです。
このワンワールドフェスティバルを通して、自分の研究や学科のことを見つめ直すだけではなく、他の団体が活動している内容をたくさん知ることが出来ました。その中でも、高校生が活動している事もたくさんあって、自分の研究している内容を共有し、相手の研究に対して自分なりにアドバイスもすることができ、自分の考えを伝える能力もより高められたと思います。私の考えからは生み出すことが出来ないような視点の考えを知ることが出来たので、その考えを活かして自分のこれからの研究に繋げていきたいと思います。
ワンワールドフェスティバルを通して、国際的な問題など、世界に目を向けている高校生の多さに驚いた。私たちも創造1Lで国際問題に関する研究を行っているが、他の高校の一つには、直接支援を行い、インドなど途上国に学校を建てたり、他にも多くの問題と直面しているところもあったので、とても感心した。まだまだ私たちにもできることがある、と実感することができた。私も自分の研究を通して、実際に一歩踏み出して行動することを忘れないようにしたい。
兵庫高校のブースでは、3人に自分の研究の説明をしました。自分の研究を自分以外の人に伝えるのは難しかったですが、実際に研究を理解してもらう為には重要だと思うので、次の発表までにもっと練習したいと思いました。講義や他の人のブースでは、日本では社会的な問題に携わる組織などに参加している人は少ないと思っていましたが、実はたくさん社会問題の解決に取り組んでいる人がいるとわかりました。自分も将来何らかの形で、そのような活動に携わりたいと思いました。