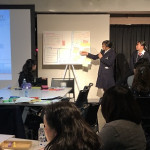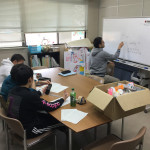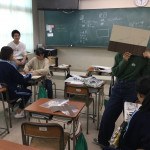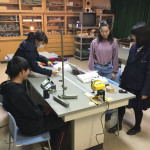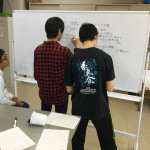三宮青少年会館で開催されたアジア福祉財団難民事業本部主催のセミナーに普通科グローバルリサーチⅠ受講生(1年)1名と創造科学科4期生(1年)1名が参加した。「ハリー神父とインドシナ難民」と題して、兵庫県立大学の乾美紀教授より兵庫県におけるインドシナ難民の受け入れの歴史を詳細に説明があり、今年亡くなられたハリー神父が難民支援に大きな役割を果たされたことを聞いた。その後、賢明女子学院のブイ・ティ・ミン・ヒュウ(平川孝美)さんより、日本における政府の支援と定住生活における苦労されたこと、ハリー神父との思い出を伺った。日本における難民受け入れのあり方や多文化共生について考えさせられるセミナーだった。
<生徒感想>
本日、神戸市青少年会館において、インドシナ難民の日本での受け入れを長年支えてこられた故ハリー神父に関するお話や、実際に難民として日本に来られた方のお話を聞いてきました。兵庫県立大学の乾教授からは、ハリー神父が姫路で行っていた難民支援に関するお話、賢明女子学院の平川先生からは実際に難民として直面した問題についてのお話をしていただきました。お話を聞いて感じたことは、「日本ではまだ難民に対する社会の目が厳しいこと」と、「日本では難民の方々が真に求めている支援がまだまだできていないこと」です。特に平川先生のお話から、日本国籍を取得して、名前を日本名に変えないとビザの発行が遅くなってしまうことや、定住するための支援センターの環境の悪さ、日本語の教育の内容が薄いことと短いことを知り、テレビや教科書などから得ていた自分の知識とはかけ離れている現状に絶句しました。文化や言語の違いがあるとはいえ、日本では難民の方々が日本以外の国に逃れた難民の方より苦労が大きいというのは、日本の大きな1つの課題だと思います。今回貴重なお話を聞くことができ、僕にとってとても大きな財産となったと思うので、これからの2年生での研究や今後の人生に生かしていきたいと思います。
テーマにもなっている、ハリー神父は本当に多忙な中、難民の方を含めいろいろな人に尽くしてきたんだというのを、両方のお話を聞いて思いました。また、私はヒョウさんのお話も強く印象に残っています。ヒョウさんのベトナム時代が私の想像を絶するものだったからです。私は今「努力は必ず報われる」と信じていますが、ベトナムで迫害を受けていたヒョウさんのお兄さんは、学年トップの成績だったにもかかわらず大学へ進学できなかったそうです。迫害を受けるというのは、根本的に私が信じているものを全て覆してしまうのだと思いました。ヒョウさんはものすごく努力して日本語を覚えて、最終的には上智大学にまで合格されていますが、きっと全員がそうであるわけではないと思います。難しい日本語を外国の方が習得するサポートの重要性を感じました。