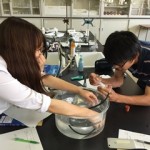本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、「持続可能な未来のための持続可能な都市」をテーマにWHO健康開発総合研究センター 都市部の健康テクニカル・オフィサーの狩野恵美氏からお話を聞きました。おもに国際保健課題としての都市問題について講義をいただきました。これまで健康については自己管理が重視される傾向にあったが、都市間の国際交流が活発化する中で保健の外的要因(住環境、経済状況、政治参加など)に重点が移ってきたことを多くの統計資料をもとに詳しく説明をしていただきました。以下は生徒の感想です。




WHOのことは、保健で少し出てきていたので、定義も今回でより良く理解することができました。また、前に講義をしに来ていただいたJICAの本部?ととても近いところに神戸のWHOの本部があったので、JICAと協力はしていないのかな?協力出来たらもっとよくなるんじゃないか?と思いました。 内容で驚いたことは、「女性の社会進出」の項目がどこの国も不十分だったということです。日本やアメリカなどといった先進国では、もっと進んでいるのかなと思っていましたが、世界共通の問題だったので、余計に早く改善してほしいと思いました。
今日の講義を聞いて、保健にお金をかけることが出来ない国があるということに驚いた。日本は保健や衛生にすごく力を入れている国なので、そのような発展途上国などに高い保険技術を伝えていくべきだと感じた。WHOの他にも民間団体や基金があって、世界規模で保健に感心を持っていることが分かった。日本内でも、健康格差が広がっていることにも驚いた。自分たちも意識して生活していかなければいけないと思った。また、地域ごとの統計をとるためにグラフを有効的に活用していることにすごく感心した。実際にデータをグラフに表すことで、他のデータと比較することができ、より問題が明確に理解できるのだと思った。グラフを有効に利用することは、問題解決にすごく役立つことが分かった。今後、自分たちの探求活動の課題解決に向けて活用していきたい。
多めの資料と詳しいお話を用意してくださっていたので、全く知らなかった情報をたくさん聞くことができました。そもそも神戸にWHOがあることを知らなかったのですが、さらにそこでは神戸のことに関してではなく、ジュネーブにある本部と同じことをしていると聞いて、興味を持ちました。近いので機会があればぜひ見てみたいです。生徒の質問に対しても、丁寧にわかりやすく例をあげて回答してくださり「なるほど」と関心を持つことができました。たばこ税について揉めたことが海外で批判されていると聞いて、国内で協力体制が整っていないことは恥ずかしいことだと思いました。他にも、加盟国の資金援助が得られないだとか、今現在あたまを抱えている問題についてもお話いただけて、とても興味深かったです。
今日のお話を聞いて、高層ビルが立ち並ぶ都市にも、スラムや経済格差が広がっており、幼児死亡率や、妊産婦の検診の受診率も低いままというように、必ずしも、適切な環境が市民に提供されているわけではないことを知りました。私たちは今、豊かな暮らしを送っています。ケガや病気をしたら、病院へ行けますし、気軽に薬局で薬を手に入れることもできます。健康な暮らしを送れる状態にあるといえるでしょう。しかし、世界の多くの国々は違っています。WHOが色々な取り組みをしても、あまり改善されない地域もあります。健康であることは決して当たり前のことではないということに気づかされました。世界中のそれぞれの国々が、様々な問題を抱えているのです。WHOは知識として知っているだけで、遠い存在だと思っていましたが、今日のお話を聞いてより具体的なものへと変わりました。健康に対する意識を高め、私たちにできることは何であるのか、考えていくべきだと思いました。
今回のWHOの方のお話では、初めて知ることがたくさんありました。1つは、昔は地方に住んでいる人が7割、都市部に住んでいる人が3割だったのに、今では都市部に住んでいる人が5割を超えるということです。都市部の人口が増えているだろうとは予想していましたが5割以上とは予想していなかったため、驚きました。2つ目に、投票率が健康に関わるということです。全く別のようで繋がっていることを知りました。WHOも最初は大きな感染症だけを取り上げていましたが、今では感染症だけでなく非感染症や社会的・物理的環境・健康格差の問題などについても取り組んでいるそうです。様々な問題に対応するには、行政部門間の連携が重要だそうです。しかし、今の政府や役所は縦割りのため、なかなか協力することが出来ないそうです。お互いに連携し合えるように改善していくべきだと思いました。
私たちが住んでいる日本などの先進国では、毎日生きていて当たり前だと感じる人が大半だ。しかし、開発途上国では何人の人がそう感じているだろうか??一人ひとりの命の重さは同じはずなのに生きていくための苦労は人によって違うのか、と改めて思った!WHOはいろんな視点から、それらの問題を解決しようとしている。中でも、国民が政府に関心のある国は精神的、身体的にも健康的であるという科学データを元に、国ごとに投票率まで参考にして健康的であるかどうかを判断するというのは素晴らしいと思った。やはり、国や国際レベルの問題はそういった他の視点から物事を考える力が必要だ。また、地域ごとにも肥満者数や失業者数を割り出し、具体的に見ていくことも大切である。いつか世界中の人々が安心して生きていけたら良いと思った!また、この講話を元に長田の町を良くする活動にも参考にしていきたいと思った。
WHOと聞いて今まではどうゆう活動をしているのかわかりませんでしたが今日の講義を通じてWHOの活動内容を知ることができたのでよかったです。世界の都市の裏にはスラムなどという劣悪な環境があるとは知りませんでした。国ごとにいろいろな問題があってそれぞれの国でそれに応じた対応をしていると知りました。WHOが健康について定義している中に社会的に完全に良好な状態でありという部分があり社会をどのように良好にするのか疑問に思ったのでホームページなどで調べてみたいと思いました。
以前、社会や保険の授業で出てきたWHOはその名の通り保健についてのみを職としている機関と思っていました。しかし、お話を聞いて、国際開発にも関わっていることに驚きました。たった1つの問題を解決するのに、様々なことが関連していき大きくなっていく、普通の勉強とは違った新鮮な感覚を持つことが出来ました。それにともない、解決案を出すのにはたくさんの資料、知識、考えがなければ出来ないという不安も出てきました。多様な角度から物事を見極め、1つの目標に向かって研究、考察、創造することにはとても参考になりました。僕たちは創造基礎Bで長田の町の活性化についてそれぞれテーマを決めて解決案を探していますが、今回のお話での『たくさんの課題が出てくるなかで、どこを改善すればよくなるかを表や図に表して欠点を見つけ出す』ということは「なるほど」と思い、自分たちの調査に活用していきたいと思いました。