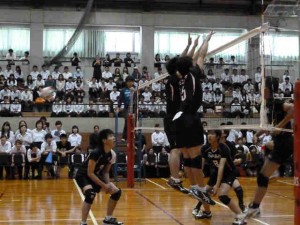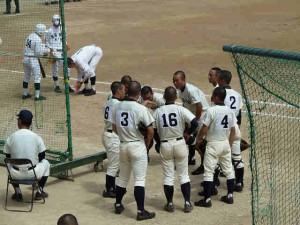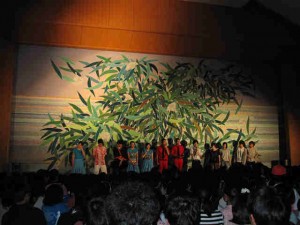本校HR教室において、創造応用ⅠLの授業で「わたしたちの難民問題」というテーマで、難民事業本部関西支部 支部長代行 中尾秀一氏にワークショップをしていただきました。難民の定義や難民の置かれている多様な状況など、世界各地で発生している難民問題について、生徒と対話しながら深めていきました。以下は生徒の感想です。




難民、日本に住む我々にとってはあまり縁のない言葉のようで実は深く関わっている。しかし、現実では日本はあまり難民保護の視点からするとあまり積極的な態度ではない。ということを中尾さんの話を聞いてわかった。しかし、今回のワークショップという形での授業は少しでも難民の考え方がわかるようなものでもあった。自分たちで何をどうするか決めて逃げる、そして回りと比べる。そして、難民と呼ばれるものの現実を知ることによって我々の生活との差がわかる。少しでも、その事がわかったことによって国際社会の考え方のわからなかった一部となった。しかし、まだ能力の低さというものも実感できた。グローバル社会を支える世代として、これからも頑張っていきたいです。
「難民」という言葉は今まで何度も耳にしてきた。しかし授業の冒頭でいきなり、○✕形式で「こういう状況にある人は難民と言えるか?言えないか?」を判断しろと言われて、私は全く分からなかった。講師の方に「なぜ✕にした?」と聞かれても、まともな理由を言うことができなかった。少しショックを受け、その後、難民についていろいろ教えていただいた。まず、「難民」には、明確な定義はないが条件がいくつかある。その条件に照らし合わせてその人が難民かそうでないかの線引きをすることがとても難しいと感じた。そして、今も世界中に難民の方がたくさんおられ、そしてそのうちの多くが幼い子供である。日本にも現在難民の方が多く住んでおられるが、私は特にその幼い子供たちの将来のために、現在行っている日本語教育や社会に適応するためのサポートをより一層充実させるべきだと考えた。
今日の講義で、難民という、自分の中でとても曖昧だったものが、現実的に見えた。内容はどれも初めて聞くものではなかったが、ちょっとしたワークショップで考えながら話を聞くことで、さらに理解を深められたと思う。今回の講義で難民の基礎知識を得たことで、研究してみたいという興味が湧いた。研究テーマを決めていく貴重な材料になった。
今回のお話を聞いて私は難民について少し興味を持つことができました。今までは難民の基準さえ知らず、漠然と生活が苦しい人のことなのかな、という感じでした。しかし、今回のお話を聞いて、しっかりと理解することができました。また、自分が思っていたよりも過酷な世界なんだなと感じました。お話のされ方も、すごく分かりやすく、ただ聞くだけでなく参加型だったので楽しかったです。難民についてもっと知ってみたいなと感じました。
難民についての知識をほとんど持っていなかったので、今日の講義はとても勉強になりました。一番衝撃だったのは難民が国外に逃げるときの船や飛行機などの映像です。すぐに壊れそうな船にたくさんの人が乗っていたり、今まさに飛び立とうとする飛行機にしがみついていたり、本当に命がけだなと思いました。難民を乗せた船が沿岸300mのところで終点だという話はひどいと思いました。人権なんかまるで無いんだなと思いました。命がけで日本に来た人たちには、日本に来て良かったと思ってもらいたいです。日本語を4ヶ月で習得するのは大変すぎるのでもう少し期間を伸ばしたり出来ないのかなと思いました。また、外国人お断りのアパートやマンションも少なくなっていけばいいのにと思いました。
今日の難民についてのお話を聞いてすごく難民に興味を持ちました。自分が思っていた定義とは違うところも多く、一言で難民といっても色々な背景を持つ方々がいることも初めて知りました。日本にいる難民の方はどのような思いで暮らしているのだろう、自国に平和が訪れた時難民の方は自国に帰るのだろうか、と終わってから色々な疑問が出てきたので是非三宮である勉強会に参加しようと思います!
今回の講習で難民という存在を今までより近くに感じられた。まず、迫害の恐れがある、保護を求めない、国外にいるという項目を満たしている人が難民と言われるそうだ。実際に国外へ逃げようとするときに、何を持っていくかということを考えるワークショップも行った。二つのグループに別れて話し合いを行ったが、そのどちらのグループにもスマートフォンを持っていくという意見がでた。しかし、これは私たちが高校生でも当たり前のようにスマートフォンを持っているからこその結果だと思い、実際の難民は地図もなにも無い状態で避難していることも多いと聞き、納得した。また、避難するときの季節や年齢によって持ちものも変わってくると知り、詳しく知りたいと感じた。今年の夏休みに私はベトナムへ行くが、日本が受け入れている難民の中ではベトナム人が多いそうだ。そのような面での日本とベトナムとの関わりも考えながらベトナムへ訪れたいと思う。




















 天気にも恵まれ、69回生2年生が京都を満喫しました。
天気にも恵まれ、69回生2年生が京都を満喫しました。