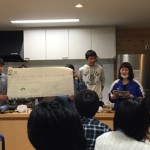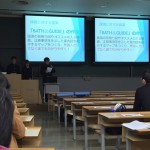本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、未来創造コース2期生(1年)対象に、兵庫教育大学の外国人留学生や教員研修留学生の方々10名(中国・台湾・ソロモン・ガーナ・インドネシア)をお招きし、「The global environmental issues and Japan」とうテーマで口頭発表および交流会を行いました。まず本校生から10分間でテーマに沿った英語の発表を行い、質疑応答を行いました。続いて留学生の国の環境問題について10分間の発表を行い、質疑応答を行いました。そして、残りの時間を使って、日本への留学動機や母国の文化や教育制度などを話題にして交流しました。1学期に実施したときに比べ、声の大きさや早さを意識しながら発表ができ、内容について活発な議論ができました。
外国人留学生の出身国・地域:中国(内モンゴル)、中国、台湾、インドネシア、ソロモン、ガーナ
以下は生徒の感想です。
留学生のガショウさんはとても愛想のいい可愛らしい人でした。中国の方ですが日本語と英語も上手で、どうしたらそんなに上手くなりますかと聞いてしまったぐらいでした。やはり地道に勉強することだとおっしゃっていました。私たちの発表も興味深そうに聞いてくださり、質問の時に上手く伝わってなかった部分を指摘してくださったので、そこを頑張って英語で伝えようとしたりと有意義な時間でした。逆にガショウさんの発表も、難しい単語が出てくると、この意味はわかりますか?と丁寧に解説してくださったので、発表を理解することができました。雑談も結構盛り上がってとても楽しかったです。中国の話を聞くと、ぜひ行ってみたくなりました。また機会があれば、交流させてもらいたいです。
今までの交流会などの行事より、みんな積極的に英語を使って話すことができました。個人的なことを言えば、前回の発表時に休んでいたので、今日原稿のチェックや発表スライドとの読み合わせをはじめてしましたが、とてもすらすらと読めて、自分自身でも少し成長したなと感じました。質問の受け答えもある程度は素早く反応できるようになりました。この1時間で、自分達の成長を感じられ、さらに課題も発見できた、とても有意義な時間になりました。
Today, our group interacted Ms. Joh. She is from Xian China. I saw that Xian’s air is polluted. I have criticized Chinese thermal power generator, in my speech. If I had known that the international student is from China, I wouldn’t have written such a manuscript. We could know the food culture of Xian. For example, the sweets made by green peas (Green peas is 緑豆 in Chinese) . We explained how to spend New Year in Japan. We told about “Hatsumoude”, but I don’t know why people crap their hands twice in front of god in the shrine. We couldn’t solve this question.(今日、私たちの班は常さんと交流しました。常さんは中国の西安出身です。西安の空気は汚れていると知りました。私は自分のスピーチの中で中国の火力発電を批判してしまいました。もし留学生が中国人と知っていたなら、そんな原稿は書かなかっただろうに。私たちは西安の食文化を知ることができました。例えば、グリーンピースから作るお菓子です。私たちは日本の正月の過ごし方について説明しましたが、私はなぜ神様の前で2度手を叩くのか知りません。なので、この疑問は解決できませんでした。)
今回のRREはとても充実した時間を過ごすことができました。テーマが環境問題だったので難しい単語が出てきて、原稿をあまりすらすらと読むことはできなかったけど、留学生の方が頷きながら発表を聞いてくれたのでよかったです。また、留学生の方の発表は所々難しくて分からなかったところもあったけど、中国の大気汚染について深く知ることができたと思います。そのほかにも日本の文化についていろいろなお話をできたのでよかったです。留学生の方と仲良くなれたのでこれからも連絡などを取り合いたいです。
僕たちの班はガーナ人の方と交流しました。ガーナでは、ゴミが重大な問題になっているそうです。ゴミの分別は電子機器のみで、それ以外のゴミは全て同じ所に捨てるのだそうです。だから、リサイクルが全くできていないということでした。ここまでゴミ問題が深刻化した原因は、急激な人口増加により、土地が必要になった。しかし、ゴミの量も急増したので、それまで困らなかった埋め立ての土地の確保が困難になっていったということでした。現在ガーナ政府では、ゴミの分別の徹底や、ゴミの量に伴って増えるゴミ税をという制度を設け、その金はリサイクルの資金に充てられるという政策も行っているようです。今回の発表で、それぞれの国にそれぞれの問題があって、その対策方法も様々だなと思いました。時間内に発表できなかったことや、その事象についての知識が浅はかで、上手く質問に答えられなかったことが反省になりました。僕たちの英語力はまだまだですが、もっとたくさんの方々と発表し、問題解決能力を養いたいと思いました。
公害という難しいテーマのプレゼンで、かたことの英語だったけれどうなずきながら聞いてくれた。留学生の方のプレゼンもとてもおもしろく、その後いろんな話をして盛り上がれた。伝えたい事を英語にできなくてもジェスチャーや絵を描いたりすることでちゃんとコミュニケーション取れたと思う。今回のような発表にも慣れてきたけれど、留学生の方のプレゼンをみて、まだまだ学ぶことが多いなぁと感じたので次回に生かしたい。
私たちの班は、ハタマネ ドロシー ヒックスさんと交流しました。ドロシーさんはソロモン国籍の方で、教師として子供たちに情報を伝えているそうです。公害や野生動物の減少などの日本の抱える環境問題についてプレゼンテーションをしたところ、良い評価をいただきました。また、ソロモン諸島では酸性雨がないそうで、興味を示されていました。ドロシーさんはソロモン諸島について教えてくださり、島が抱える木々の伐採や水質汚濁、ごみ処理問題などについて詳しく知ることができました。終始円満にコミュニケーションをとることができ、また時間も守れて発表できたのでとてもいい時間を過ごせたと思います。
今回の発表は専門的なことが多く、調べるのが大変でしたが上手くいって良かったです。留学生の方の発表から、中国で今起こっている環境問題は日本の高度経済成長期に起こった問題に近いところがあると感じたので、日本の技術などを発信することが出来たらきっと解決に一歩近づくことが出来るのではないかと思いました。他にも、中国の観光スポットや歴史スポット、食べ物など、様々なことについて教えていただきました。個人的には大変興味深いお話を聞くことができ、嬉しかったです。
It was very very good time for us. English is too difficult for us but it is very interesting. Chinese student in our group was very kind for us. So I was happy. And it was good for us to study English. He is very clever. So he taught us about English. I thought I want to use English better. (私たちにとってとても有意義な時間を過ごせました。英語は私たちにとってとても難しいですが、面白かったです。私たちの班に来られて中国人留学生はとても親切で、とてもよかったです。そして、彼はとても賢い人だったので、私たちにわかりやすく英語で説明してくれました。私ももっと英語が話せるようになりたいです。)
台湾の環境問題で1番衝撃的だったのが台風とそれに伴う濁流です。日本でも洪水はありますが、その規模よりも遥かに大きく、日本よりも赤道に近い場所にあるので発生回数も多いそうです。大気汚染も深刻で通常時と比較した写真を見せていただきましたがすぐ近くのビルも見えなくなるほどでした。今回の発表会での個人目標として僕が掲げたのが、~日本語英語からの脱却~です。そのために読む練習を沢山しました。しかし本番になると、舞い上がってしまって原稿を噛まずに読むことに必死になってしまい、発音にまで配慮する事ができなかったです。練習不足だったと終わってから感じました。その後の質疑応答の時間では、何を聞かれてるのかはある程度はわかったのですが、答える時に自分の語彙力が足りず身振り手振りを交えながらでしか伝えられませんでした。同じアジア人の外国人留学生があんなに英語を流暢に話すのにと情けなくなるほどでした。英語力は一朝一夕ではつかないので、地道にコツコツとつけていきたいと熱望しました。