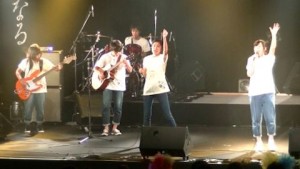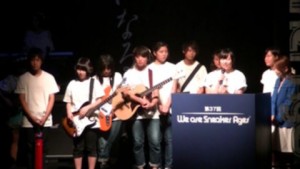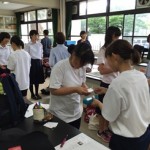2016/8/26更新
・オープンハイスクールの記事を掲載しました
・We Are Sneaker Agesの記事を掲載しました。
ギターアンサンブル部の表紙(トップページ)はこちら
2016/8/20 We Are Sneaker Ages予選会
大阪市の松下IMPホールで第37回We Are Sneaker Ages予選会に参加しました。
健闘しましたが力及ばず、上の大会に駒を進めることはできませんでした。
大きなホールでの演奏はもちろんですが、レベルの高い演奏や応援を直接見られたことは、私たちにとって大変意義のある経験となりました。
皆様の暖かい応援に心から感謝申し上げます。
本校の応援団(中央の黄色のポンポンを持った列です)
全体を撮った画像でも左下に入っています


2016/8/17,18 オープンハイスクール
部活動見学でミニライブを行いました。多くの中学生に見に来ていただき、ありがとうございました。写真は18日の様子です。
2016/7/30 なかざと夏祭り
神戸鈴蘭台高校近くの、中里中公園で行われた「なかざと夏祭り」ステージに出演しました。
たくさんの皆様の応援をいただき、励みになるステージでした。
2016/7/29 神戸甲北高校軽音楽部
第9回定期演奏会
本校は、神戸学院大学付属高校、県立芦屋高校とともに、ゲストステージに出演しました。
2016/7/20 夏ライブ2日目
2016/7/19 夏ライブ1日目
2016/4/28 校内祭
講堂








弦楽部とのコラボレーション






ライブハウス









2016/4/28 武陽祭
ダンス部とのコラボレーション


2016/4/29 一般祭
多数のご来場、心より御礼申し上げます。