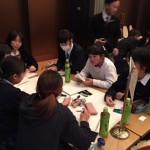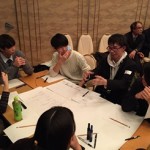本校同窓会館ゆ~かり館において、創造科学科1期生(1年生)40名を対象に、創造基礎Aの授業を行いました。まず、明るい選挙推進協会作成「くらしの中の選挙2」で投票所と投票の方式について学びました。次に、前回の授業で行った模擬代表演説を受け、模擬投票を行いました。投票結果は自民8、民進8、維新6、公明3、共産9、自由1、社民2、白票2(1名欠席)でした。




その後、NPO法人Youth Create 代表 原田謙介氏から「自分の軸と政治」というテーマで講義を行っていただきました。原田氏が高校時代に体育祭実行委員会で教員とやり取りした経験や、学生時代に政治に興味を持ち始め、議員秘書のインターンに参加したことなど、原田氏と政治の接点についてお話をしていただきました。また、選挙は若者の政治参加の方法として大きく取り上げられていますが、投票のみが政治参加の手段ではなく、まだ有権者になる前の年齢の若者が政治参加する方法が数多くあることを学びました。




1)創造基礎A・B(社会科学分野)の授業を通して、あなたと政治との接点を感じたことは何ですか。
新聞ノートを通して新聞を詳しく見ていると、中高生に関する記事が思ったより多くて驚きました。そこで、自分たち学生も社会の一員なんだと感じました。財政教育では、予算配分などの研究活動をしましたが、それを通して地域の図書館で国の財政に関する本を借りたりなどして、政治について考えたりしました。財政教育を通して政治について知ることも自分と政治の大事な接点だと思います。また、地域の課題研究では、大人と関わる中で社会の厳しさや教科書ではわからない生の声を聞いたりして社会参画とはどういうことなのかを考えるいい機会だなと思っています。
財政教育で、日本の課題を解決するために立てたビジョン、それに対するお金の使い方を決めるのも政府のことだし、そう考えるとこれから少子高齢化の問題や人口減少、過疎、過密の問題も政治が進んでいく方向によって大きく左右されるものなので、とても接点を感じる。特に、少子高齢化は普段暮らしている中でも身近に感じることであり、この状況も政府の予算案によって、ビジョンによって変わるかもしれないと思うと、政治というのは日々の生活の中でとても重要なものだと分かる。
長田区の駒ヶ林地区で実際に活動を行ってみて、区役所が行っている町おこしの多さにびっくりした。町の政治について知らないことがたくさんあったし、こんなに地域についての政治が行われていることを知るきっかけとなった。国の政治だけでなく、地方の政治を身近に感じられるとてもいい機会だったし、もっと地方政治について目を向けようと思えた。
政治を動かすのは18歳以上の有権者や政治家だが、政策には18歳未満の私たちも関係するということを感じた。私たち学生の視点で財政について、予算について考えると教育費が多くなるが、高齢者なら福祉を重視するなどの世代によって考えが全く違うことを感じた。
国会や世界で起きている出来事が自分から遠いものという認識がなくなりました。たとえ、日本から遠く離れたところで起こっている戦争や事件、国の動きなどもめぐりめぐって日本にも影響が出るんだということが分かりました。国会の中で決まったことでも、すぐに私たちの生活に出てくるものもあれば、これから先の未来で大きな変化をもたらすかもしれないこともあります。今までは他国の大統領が変わると聞いても少しの興味もなかったけれど、今ではとても気にするようになったし、他国同士の変化のつながりも自分で少しは考えられるようになりました。
2)あなたが投票した政党の決め手は何ですか。また、模擬選挙の授業に参加して感じたことは何ですか。
この政策が実行できてから、次の政策を実行するということを行おうとしている政党で、自分の考えに合った政党を選んだ。同時進行で政策を進めていくことも大切だとは思うが、それで政治が不安定になってしまってはいけないと思うからだ。模擬選挙の授業に参加してみて、選挙は公正に行われるということを改めて感じた。だから、本当の選挙で投票するときも、しっかりと自分の意思を持つことが大切だと思った。
私が一番力を入れてほしいと思っている、福祉政策の中の保育分野に関して認可保育園を増やしていくという形で力を入れてくれると思ったから。また、その財源がどこから来るのかというのをしっかり示せていて安心できた。その財源が富裕税や環境税など新しいものでよいと思った。ただ外交の面に関しては消極的になっているので、TPPとかは参加してもよいと思う。消費税UP反対はやめた方がよい。今は確かに楽かもしれないが、日本の借金は増える一方で、未来の子どもたちのためにもできるだけ借金は減らしておいてあげるべきだと思う。
私が投票した政党はどこよりも現実味があり、また多岐にわたって政策が練られていると感じました。また、政策がどこよりも私の意見と一致していたと思いました。模擬選挙の授業に参加して、とてもワクワクしました。紙に工夫がされていることや見張る人がいることなど、体験してみないとわからない仕組みをたくさん知れてよかったと思いました。こうした一人ひとりの小さな行動が日本を前に進めるのだなと思うと、小さなことでもしっかりこなしていくことが大切だなと感じました。投票率がどんどん下がっていく中で個人個人が社会の一員としての自覚をもっていかなければならないと感じました。
決め手は演説の時の党首の語り掛ける話し方が印象的だったからというのが一番の理由です。他にも、一つ一つの政策の内容を具体的な数字などを交えながら話していたので分かりやすかったし、信頼できるかなと思ってその政党に決めました。今回の授業を受けて、今までまだまだ先だと思っていた選挙が実際に模擬投票をすることで身近なものなんだと感じることができました。また、投票結果で白票があったと聞いて、こういう事が今問題になっている「投票率の低下」みたいなものなのかなと感じました。
政党の決め手は、党首の演説での話の筋が通っていることだ。どれだけ良い理想論を語っていたとしても、何かをやるには必ずお金が必要になってくる。そのお金の出どころが不透明な政党は信頼できないと思った。また、政策を行ったとして、自分に良くも悪くもどんな影響があるかも考えた。増税などで自分に負担がかかったとしても、身の回りや国の状態がよくなれば良いなど、様々なことを考えた。模擬選挙を通じて実際の選挙に対する不安が少しなくなった。そして、同じ演説を聴いても人それぞれ価値観が違い、票もばらけたことが興味深かった。
3)あなたは、18歳に向けて、どのように「主権者としての責任」を果たす準備をしますか。
日本の若者は、他国と比べ、選挙の意識が低いと言われている。しかし、今日まで政治のことについていろいろと勉強してきて、国が変わるには私たちも変わるしかないのだなと感じた。他人に任せっぱなしでは何もよくならないし、自分たちのことは自分たちで決める、という意志がなければせっかく取った権利も弾圧される日が来るかもしれない。主権者として、自分の意志をしっかり持って、他人に左右されず善悪を見極めて票を投じることができるように、今から新聞、TVなどのメディアを賢く使い、世間で何が必要とされているか認識しておきたい。
今の日本だけではなく、未来の日本を考えて投票することが主権者としての責任だと思うので、身近のことだけではなく、大きく日本という国を考える必要がある。そのためにすべき準備は先を見据える習慣をつけて、多くの意見の中から同じように考えているであろうものを選び、日本をより良い国へと発展できる党への信頼が大切になる。すべての意見を受け入れるのではなく、自分に必要な物なのか自分で区別できる力をつけることが主権者になったときに国を考えるうえでとても重要なものになると思った。
私は普段、新聞を読んだり、ニュースを見たりする習慣がないので、正直政治に関する基本的な知識が足りていないことを痛感しています。また、18歳に選挙年齢が下がったこともあり、今まで以上に私たち若い世代が率先して政治に関心を向けないといけないと思います。私にできることはまず私が今日から習慣を始めることであり、これは今の若者に託された使命でもあると思います。
4)原田氏の講義の感想
原田さんは若いのに何にでも挑戦され続けていてすごいなと思いました。現在の社会に自ら発信していくというのはとても大変そうだけど講演に呼ばれたり、議院に呼ばれたりなどしてご活躍されているところが印象に残りました。また、「選挙では選ぶ側が大変だからそれを少しでもかえていきたい」とおっしゃっていたのが耳に残りました。自分も積極的に社会に参加していく必要があると感じました。そのために今日おっしゃっていた家に届く議員だよりを読むなどして、工夫して社会の動きを知りたいと思いました。
「若者と政治」をつなぐことはとても大切なことだと思った。私は政治に対する印象としては「難しそう」、「信頼できない」という気持ちが多かったけれど、今回お話をいただいて、このように若者が政治に関心が持てるよう動いている組織もあると知って、私が抱いていた印象は先入観だと分かった。そして、選挙権はまだないけれど、別の形で政治にかかわることはできると気づいたので、これから家に届く地方紙のようなものであったり、駅や区役所においてあるちらしに目を通すなど、もっと政治というものに関わっていきたいと思う。また、投票率は私は低いと思っていて、なぜなら20代・30代と比べてというより10代がいかに投票に行くかだから、もっと10代が選挙に行けばどんな形であっても政治は変わると思う。そうすれば20代・30代も10代に刺激を受けて行くようになるのではないかと思う。政治への関わり方について学ぶことができ、改めて政治というものにしっかりと関わっていきたいと思った。
私はあまり日本の政治に興味を持ったという経験はない。しかし、案外高校生でも政治に関われる機会がたくさんあるのだということを学んだ。自分一人の少しだけの力でも身の回りの環境を変えるチャンスがいくらでもあると知り、ワクワクした。自分の生活について深く考えることは面白いことであると思う。今後、私も政治についてきちんと考え、もっと積極的に関わっていけたら良いなと感じた。
実際に政治家などと会っている人の話で、どこか身近に感じた。どうしても政治=選挙であると考えてしまっていた僕にはとても新鮮な話だった。「選ばれる>選ぶ」という構図はたしかにおかしいと思っていたので、同じことを考えている大人の人もいるんだなと思った。自分の軸が強みでありよりどころであり夢中の源であるという最初の話を聞いて、自分の好きな「話すこと」、強みだと言われる「明るさとうるささ」を軸にして、これからの日本の政治、また、自分の住まう地域の政経に向けて生活していきたいと思う。
私はこれまで、日本人の投票率はとても低いと思っていたが、実はそうでもないんじゃないかという考えを持つことができた。投票率が低いからと言って、選挙に行くことを強制してしまったら意味がない。日本がより良い国になってほしいという思いがあれば、自然と投票するようになるのだと思う。私は一度神戸市長にもお会いしたことがあるし、今回の講義で知ったツイッターを利用した取り組みなどもあるので、まだ高校生だからと言って日本の政治に消極的になる必要はないと思う。
私的には“政治”というワード自体が堅い雰囲気でとっつきにくいようなイメージがあります。政治家も威厳のある年配の方が多く、有権者の私たちが敬っているように思えます。アメリカには若いイケメン議員がいるそうです。日本でもイクメン議員さんがいましたが、不正が発覚してしまいました。原田さんがおっしゃっていたように私たち若者はネットの情報すべてを見ているわけではないので、興味があることなら自ら調べに行くし、なければ目の前にあったとしても見逃してしまうと思います。“イケメン”と“議員”というワードに引っかかる人はたくさんいると思います。人々に知ってもらうためにはネットを使えばいいのではなく、単純に言葉の組み合わせ方を工夫知ればいいのだと思いました。
自分たち一人ひとりが世の中の主役であることを改めて考えさせられる機会だった。複雑に見える政治だが、根本的にはいかに意見を主張できるか、それを実行してもらえるかなんだなと思った。これから政治に関わることが何かと増えてくるだろうが、今日話していただいたことを心に残して、18歳になってから投票に行きたい。Youth Createの活動も興味深いと思った。何より、「若者」に対して自分たちこそ日本を動かす人々なのだという意識を与えられる素晴らしい取り組みだと思う。特に「Vote Bar」に参加してみたいと思った。
一番記憶に残ったのは「地方議員と話す場を設ける」という話です。世間一般に知られているのは代表などの地位が高い人だけなのであまり知られていない人達と話す機会というのを設けてもらえるのは高校生など実際に政治家と関わることが少ない人からしたらいいことだなと思いました。また、メディアは多くの人に見てもらいたいというのが本心だと思うけれど、その時の政治のキーワードになんでもくっつけてしまうのは良くないのではないかと思います。報道を見ている側からすると、起こったことを変に編集しないでまっすぐ伝えてほしいなと思いました。原田さんの話を聞いて、若い人から高齢者まで多くの人が政治に関わってほしいというのが伝わってきました。私は選挙権だけではなく、被選挙権も関わることのできる年齢を下げたらいいのになと思いました。