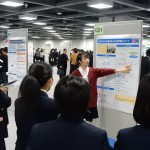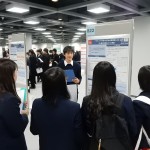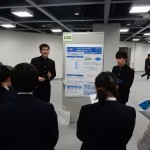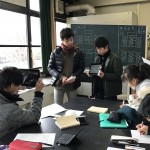神戸ファッションマートにおいて、創造科学科1期生(2年)8名と普通科グローバルリサーチⅡ受講生(2年)4名が、兵庫県教育委員会・大阪大学・WHO神戸センター共催の第5回高校生「国際問題を考える日」に参加し、ポスターセッションにて発表を行いました。また、創造科学科2期生(1年)文系選択者9名が、来年度に取り組む探究活動の参考とするために、見学者として参加しました。このイベントには、SGH指定8校(県内5校・県外3校)およびSGHアソシエイト指定3校(県内2校・県外1校)を含めた、計30校、約400名が参加しました。その内の18校、66タイトルが参加するポスターセッションを見学しました。講義やパネルディスカッション、他校生徒の発表に対して、積極的に質問する様子もみられ、大変有意義なイベントとなりました。イベント内容の詳細は以下のとおりです。
《基調講演》
「2050年の世界と日本 ~世界がうらやむ幸福社会~」
WHO神戸センター上級顧問官 野崎慎二郎氏



《パネルディスカッション》
テーマ「2050年の世界と日本」
座 長 :WHO神戸センター上級顧問官 野崎慎二郎氏
パネリスト:4名(神戸高校・明石北高校・篠山鳳鳴高校・加古川東高校)


《ポスターセッション・以下は、本校生徒発表タイトル》
創造科学科1期生
「これからのイギリスの通商政策の予測」
「拡散するテロ~フランスにおけるテロ対策を考える~」
「学校における教育格差をなくすための教育」
「日本における高校生の社会参画について」
「地域における外国人住民の課題解決について」
「ベトナム ハ・ザン省への日本企業誘致によるモン族の所得向上への考察」
「学校に求められるトイレとは」
「なぜ日本の国会はクオータ制を導入することができないのか?」
グローバルリサーチⅡ
「セプティックタンクを浄化槽に」
「フィリピン・ブキドノンにおける教育格差改善の方法について」
ポスター発表の様子







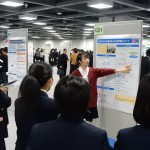


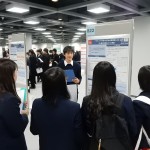
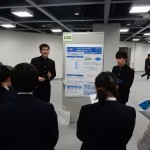
他校生徒の発表に積極的に質問をする様子




《講評》
大阪大学全学教育推進機構特任講師 柿澤寿信氏
なお、本校放送委員会の生徒が、本イベントの司会進行を担当してくれました。


また、本校創造科学科2期生(1年)が受付案内を行いました。

〈生徒の感想〉
私は「日本における高校生の社会参画」というテーマで教育に着目してポスターセッションをした。発表の中で、根拠や論理が定まっていない部分に多く気づかされた。なぜ、投票率は下がっているのか。グラフは本当に若者の政治離れを表すものなのか。具体的にどのような教育を行うべきなのか。自分の中では綺麗にまとまっておらず、非常に曖昧な応答をしてしまった。今回の発表で自らが見えてない視点からの質問があったため、視野を広げることが出来た。これから研究をさらに進めていく中で、自分の研究で着目した点だけではなく、なぜその問題は起こっているのか、グラフの示す値はどのような意味を持っているのかということ、また、自分が主張する提案の具体例をより深く考えていきたい。
2月3日国際問題を考える日 指摘されたこと
・先行事例 :教育制度の向上と人口流出が繋がらない
・提案:モン族が農業から離れるとベトナムの国全体に影響は無いのか
・自動車会社にこだわる理由
・初等〜中等の教育を改善する必要は
・大都市、富裕層とどうしても結びつきやすい営利企業を地方都市、貧困層とどうやって結びつけるか→何か強烈なメリット
・ベトナムを日本で暮らす我々が研究する意義、日本との繋がり、日本社会との類似点
評価項目の研究内容の欄は12分の7の人が丸をしてくれました。
・理念法の導入が持つ効果の分析を韓国の事例から行う
・女性団体の圧力という言葉は悪い印象を受ける
・なぜ女性議員がそもそも少ないのか明確にする
・女性議員が増えるメリットを言うことで説得力が上がる
・女性議員が少ないことによって起きる現在の問題を明記すると説得力が上がる
・日本でクオータ制を広め、女性団体の動きを活発にするにはどうすればいいか説明すればより良い
・提案内容が堂々めぐりになっていないか
まだ詰めの甘いところが多かったので、必要な部分のリサーチを少し足そうと思う。
今日の発表は、日本語での最初で最後の発表でしたが、論文完成に向けて何か手に入れたいという気持ちで発表に臨みました。私の今の段階の研究では、学校内格差を縮小している学校を知りたいのに、学校を特定することが難しいという理由で、都道府県ごとの成果を調べています。自分でも問題があることはわかっていましたが、やはりそれについて問題視して質問してくださる方が何人かいました。しかし、大人の方は、ただ単に突っ込んでくるだけではなく、私のコメントを誘導してくれたり、どこがどう悪いのかをわかるように質問してくださったので、これからの足がかりになりました。現段階で、私のテーマに文句なしにぴったり当てはまる先行事例は秋田県しかありません。しかし、秋田県を調べるだけではただのリサーチになってしまうというのが難しいです。東京都に関しては、23区にわけてその中から秋田県のような貧困に打ち勝っているところがないか探すことも考えています。
今回は国際問題を考える日に参加してポスター発表をしてきた。外部のイベントでこのように正式に自分の研究について発表したのは今回が初めてだったが、たくさんのことを知れたので良かったと思う。例えばこれまでは日本企業の対策についてイギリスに留まるか撤退するかの二択しかなかったが、それに他国への拠点の移転を考えるとどうなるか、EU以外の国との通商政策についても多少触れるべき、というものである。他にも非常に効果的なアドバイスがたくさん得られたのでこれからの研究に活かしていきたい。
今回で2度目のポスター発表、前回よりも多くの指摘を受け、様々な課題が見えた。1つは証拠の不確実さ。発表の中で挙げたフランスのイスラム教徒が抱えているトラブルは、あくまで間接的な証拠に過ぎない、証拠になっていない、という指摘を頂いた。また、それがフランスだけに当てはまることなのか、他の国についてはどうなのか、言及が不十分な部分もあった。2つ目に対策への言及が不十分だったこと。本番の時間配分を失敗したのもひとつの要因だが、対策が十分な根拠を持っておらず、まだ仮説の段階だとご指摘を受けた。そもそも本研究の一番の目的はテロの原因を探ることなので、そちらの方に重きを置いて、対策への言及はなるべく少なくしたい。その他にも、発表の中でイスラム教徒が皆テロリストかのような言い方をしてしまったり、仮説の段階であるにも関わらず「テロ=ジハード」であると言いきってしまったりと、細かいミスも多かった。国際公共政策カンファレンスまでには必ず改善する。しかし課題の背景のなどは順序立てて説明でき、分かりやすかったと感じてもらえたようなのでよかった。また岩橋さんからもたくさん助言して頂いたので、発表が落ち着いたら論文を必ず訂正して、研究を完成させたい。
ポスターセッションの評価に、結論が見えにくいというのと、何に焦点を当てているのかわかりづらいという評価があった。たしかに和式も大事だという結論になっているし、トイレ全体に焦点を当てていて、床や壁の素材とか、掃除方法とか便器以外のものの話が多いなと自分の研究を見て思った。また、最後の講評でおっしゃっていた仮説をちゃんと立てれていなかったのも反省点である。最終発表まで残り少ないけれど、今回頂いたアドバイスを参考にして情報の取捨選択をしていきたいと思う。
今回の発表では、最初に外国人住民からの聞き取りで言語の壁が大きな問題と言ったのに提案でそこについて直接的に触れていないことについて多くの意見があった。やはり提案の内容と同様に説明不足になってしまったようなので、もっとわかりやすいつながりを考えておきたいと思う。また、提案に対する質問でも思いもよらないところへの質問があり、そういうところも必要なのかという大きな参考になった。今回の発表を最終発表での質疑応答に活かしたいと思う。
今回、初めて学校以外の場所でポスターセッションをして、今まで思いもよらなかった質問や意見をいただき、とても良い経験となりました。私たちのグループ内では、普通に使われている言葉も他の人からしたら、初めて聞く言葉であり、説明が必要だったと分かって、これからのポスター、論文の作成にとても役立てられると思いました。また、講師の方のお話は、現在の日本を世界と比較したときの現状や未来について、とても考えさせられるものでした。パネルディスカッションでは、私と同じ学年の人たちが、こんなにも広い視野で、日本と世界を見つめているのかと驚かされました。中でも、一番心に残っているのは、「日本人の心の豊かさを世界へ」という発言でした。日本人のことをそのような見方で見たことはなかったので、すばらしいものだと感じさせられました。参加して本当に勉強になりました。また参加したいです。
学校じゃない場で発表し、多くの質問を受け、アドバイスシートをもらうことで、自分の研究について見つめ直す良いきっかけとなりました。まず、セプティックタンクという水処理槽に加えて浄化槽を作るのは手間もお金もかかるし、セプティックタンクが普及していない地域に作ることにしたら、そんな地域はもともと少ないのだからあまり意味がないのではないか、ということを考えさせられました。また、他の国、地域とも比較してほしいということも、アドバイスシートに書かれていました。これらの改善点として、僕はこれからのGRの論文で、各国、地域の河川の汚染状況、一人当たりの所得などの比較をもとに、最も浄化槽が必要な場所はどこかというのを、徹底的に調べようと思っています。悪い意見ばかりでなく、質問の受け答えがしっかりしていたなどの良い意見も多くあったので、そういうところは活かしながら、もっと研究を深めていければと思います。
午前中は、2050年について考えた。なかなか考えたことがなかったので、聞いていておもしろかった。とくに、日本経済に起こる変化を様々な面で見られたのがよかった。高齢化によって、外国人が労働者として働きに来ることを考えていかなければならないと痛感したし、これは自分が書こうとしている論文の重要なポイントになりうると感じた。また、初めて聞いたUHCということも、今後、世界でますます重要になってくるとわかった。日本では、比較的整っていると思ったし、これを維持する重要性を感じた。午後からのポスターセッションでは、フィリピンの教育という僕たちとほぼ同じテーマを研究している人と情報共有できたのがよかった。発表は、今までのグループ研究のすべてを出し切れたと思う。また、ここでも自分の研究で参考になることをたくさん知れた。今後は、論文作成だが、今日得たことをしっかり活かしたい。
今年の国際問題を考える日は、収穫の多いものとなった。パネルディスカッションでは、積極的に質問に行くことができ、同世代のたくさんの参考になる意見を聞くことができた。基調講演は、日本の将来についての話が主だったが、2050年に対する様々な主張を知ることができたのがよかった。ポスターセッションでは、事後評価で「論理的でわかりやすい」、「比較がよくできていた」などのコメントを生徒と共有することができ、とても嬉しかった。個人研究に向けて、今日の課題を整理し、より良いものになるよう努力していきたい。
国際問題を考える日に参加しました。今思えば、社会・国際系の本格的なポスターセッションに参加したのは初めてでした。その中で私が学んだことは、自分の言葉で伝える力がもたらす聞き手への影響です。発表の中で、相手の目を見ていても原稿に書いてある堅苦しい言葉を使っていたり、終始同じトーンで話されると話の内容が頭に入りにくいことがありました。理科系の研究だと、結果や考察ははっきりしていますが、国際問題には答えが無いためその人の考えが軸になっています。その”考え”がより聞き手に伝わるのは、原稿ではなくその人の言葉だと感じました。実際に、分かりやすい言葉でジェスチャーや声の抑揚、アイコンタクトがある人の発表はとても理解しやすかったです。私もそんな発表ができるように、ここで学んだことを来年度の個人研究でも活用していきたいと思います。
「高校生国際問題を考える日」に参加して、周りの高校生の意識の高さに驚きました。パネルディスカッション・ポスターセッションでは自分の意見を自信を持って発表し、質問や意見にも淡々と答えている姿を見て私と同じ高校生なのにレベルが高いな、と感じました。また、発表の方法も様々な工夫を凝らしていてとても理解が深まりました。1日という短い時間ではありましたが、世界にはまだ解決されていない様々な問題があることを改めて感じさせられました。それと同時に、解決されていない問題にこれから直面するのは私たちで、解決しなければならないのも私たちであることを強く感じた、貴重な1日となりました。