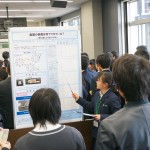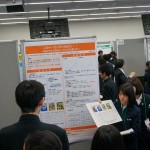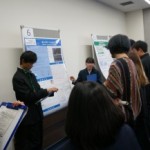甲南大学ポートアイランドキャンパスにおいて、本校創造科学科2期生(1年)40名が神戸高校総合理学科1年生とともに、合同交流研究発表会を行いました。兄弟校である両校の生徒が、互いに科学技術分野に関する探究活動について発表しあうことで、交流を深め、科学技術への興味関心を高める機会となっています。今年は明石北高校自然科学科1年生も参加し、例年以上に活気のある発表会になりました。本校生徒は、創造基礎B自然科学分野の探究活動において研究してきた内容を、ポスターセッション形式で発表しました。当日は、これまで指導していただいた神戸大学の大学院生さんや両校の保護者の方も来られており、質問やアドバイスをする光景も見られました。また、発表後はお互いに健闘をたたえながら交流会を行い、交流を深めました。
今年の研究テーマは以下のとおりです。
1班 「このテーピングに決めた!!~高分子から見るテーピングの選び方~」
2班 「楽器の表面は何でできている?~蛍光X線による成分の分析~」
3班 「鳥が好きな果実は?~柿に来る鳥から~」
4班 「浪漫 in the moon~クレーターから探る月の歴史~」
5班 「アジはどこに!?~環境DNAによる分布調査~」
6班 「謎の生物“P”の生態とは?~環境DNAによる外来プラナリアの分布調査~」
7班 「Good Bye ゴキブリ!~数理生物学で奴らの気持ちを解析~」
8班 「星のDying Message ∼X線で超新星の元素を調べる∼」
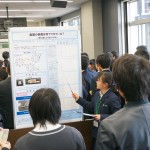

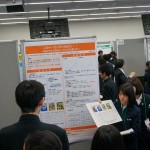




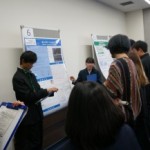




〈生徒の感想〉
1班 今回の合同発表会では、ポスターセッションが僕以外2回目であるということもあり、班全体が少し慣れた感じで発表できたと思う。時間配分等に少し課題も残るが最後に表彰状も頂けてよかった。とても良い形で今回の発表を終えることが出来たのでこれからしっかりと固めていって最終発表に備えようと思う。
2班 私たち2班は、合同研究発表会で発表しました。最初は、質疑応答のところでどんな質問をしてくるのだろうと心配していました。実際に発表すると、時間配分も、質疑応答も、前回の関西学院大学三田キャンパスでの発表に比べると、進歩しているところが見られたと思います。研究に協力させてくれた丸嶋さんからは、多くのアドバイスをいただきました。また、ポスターのグラフのところの縦軸(個数)の目盛りの間の差が、四つのグラフがそろってなかったという改善点も、私たちの班の発表を聞いてくださった方から、意見をいただきました。今後の校内発表に向けて、実験のほうでは、クラリネットとトランペットの成分を詳しく調べることと、発表のほうでは、聞いてくださった方の印象に残るような発表になれるように頑張っていきたいです。
3班 この合同研究発表会ではたくさんの質問やアドバイスをいただくことができました。また、他の班の発表からも多くのことを学ぶことができました。いただいたアドバイスの中で特に実践したいと思ったのは、鳥と果実の関係を研究するにあたり、柿に塗る塗料として植物性である食紅を使うことと、柿に直接ではなく木の枝に塗料を塗るということです。時期的にもう一度実験するのは難しいかもしれませんが、とても参考になったのでよかったです。また、グラフをもう一度整理し直したりするなどして、次の発表が今回よりもよいものとなるようにしたいです。
4班 今回の発表会で、私自身は実際に発表してみて、発表のときに人が集まらなかったり、なかなか質問が出なかったりと悔しさが残りました。もっと人を引きつけるテーマ設定や分かりやすい話し方などの工夫が必要だと感じました。また、今回は兵庫だけでなく、神戸高校、明石北高校の研究発表も聞くことができました。他校の発表を聞いて、聞き手の興味を引きつける話し方や研究内容の深さに刺激をうけました。特に発表者が研究をきちんと理解し、伝えたいことを分かりやすく説明しているところがすごいなぁと思いました。吸収できるところは吸収して自分たちの発表のレベルを上げていけるようにしたいです。
5班 1月27日に神戸高校、明石北高校との合同発表会に参加した。ポスターセッションをするのは関学に引き続いて2回目であったため、あまり緊張はしなかった。しかし、研究している側ではわかっていることでも初めて聞く方には伝わりづらく、わかりにくいことも多く質問を受けるたびに新たな発見があった。自分は質問に受け答えをしたりできなかったので、次の機会には頑張って答えられるようにしようと思った。また、発表するだけでなく他の高校が研究している発表を見ることができ、とても良い刺激を受けることができた。自分達では中々思いつかないような研究内容を行なっていてすごく面白かったし、話し方や質問の受け答えなどもすごくしっかりとしていてもっと見習おうと思った。発表するだけでなく、聞く側からもたくさんの知識を得られたので今後に活かせるようにこれからも一生懸命頑張りたい。
6班 今日の合同研究発表会ではこれまで研究・練習してきた成果を発揮することができました。発表の面では、ほとんど紙を見ずに自分の言葉で発表することができました。しかし、思っていた以上に周りの発表の声が大きく、聞いてくれている人に伝えることが難しかったです。また、発表はうまく出来たとしても、質問にすぐに答えることができませんでした。勉強不足だと痛感する中、班員に助けられてなんとか乗り切ることが出来ました。質問されることを予測してこのような発表会に臨むことも大切だと感じました。神戸高校や、明石北高校の発表を聞いていると分かりやすいように実験に使った道具などを実際に持ってきていて理解が深まり、良い方法だと思いました。また、重要な部分ではポスターの文字の色を変えるだけでなく、言い方も変えていてすごくよくわかりました。今回、このような発表会に参加させていただいて、自分に至らない点が多く見つかったので改善し、聞いている人にわかりやすいような発表にしたいと思いました。
7班 今回のポスター発表で課題がたくさん見つかった。主に2つある。1つ目にポスター発表の時間配分ができてなくて3回とも質疑応答の時間まで及んでしまった。次の最終発表会では8分しか時間がないので、時間配分をしっかりしたいと思う。また今回、重複表現が多かったのでそれも無くしたい。2つ目に式の中でバルサンの式には発見効率が含まれていないという矛盾が生じていることを指摘していただいたので、それも直したい。最後に今回のポスター発表で意見を下さった方々に感謝してこれからも研究して最終発表会に繋げられたらいいなと思います。
8班 神戸高校と明石北高校との合同発表会が終わり、今の研究の改善点と私たち高校生の無限の可能性を感じた。まず、発表の際は緊張で言葉が詰まってしまったり、質問にうまく答えられなかったりもしたが、3度目の発表の時には今までに出た質問も踏まえて説明することができた。次に、高校生の無限の可能性についてだが、3校の様々な研究は、テーマは違えど大変面白く、未来につながるものであった。また、交流会を通して高校生同士のつながりもでき、良かったと思う。合同発表会を準備してくださった先生方、また神戸高校と明石北高校の皆さん。お忙しい中足を運んでくださった大学院生さん、保護者様。すべての人に感謝し、これからも研究活動に励んでいきたい。