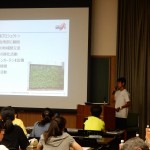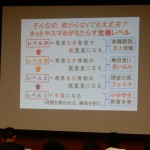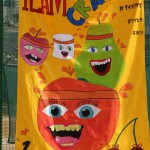創造科学科2期生(2年)理系選択者は各班に分かれて研究活動をおこなった。
<数学>
まず,統計学で頻出するシグマ記号Σの意味とその使用法について,数学B教科書を参考にして授業を行った。その後,稲葉教授のテキストに従って,サンプリング方法,ヒストグラムの作成とその見方,中心の値(平均値,中央値,最頻値),ばらつき(平均偏差,分散,標準偏差,範囲,変動係数),数値変換,標準化,偏差値,歪度,尖度の解説を行った。また,省末問題を解かせて,その後,解説をした。2名だけなので授業はやりやすかったが,教えるべき内容が多くて時間が足りず,丁寧さに欠ける授業になったかもしれない。
<物理>
物理を選択した8名を対象に、本校教員がテーマ決定のための話し合いを実施した。夏季休業中に課題として考えてきたテーマ案を出し合うことで、合計約50のテーマが出てきた。各テーマについて、課題研究としての妥当性や実現可能性に関して議論し、生徒自身が興味をもって取り組めるもの、限られた環境の中で実現できると考えられるものを選び、10のテーマに絞り込んた。
<化学>
化学の探究活動2回目は神戸大学大学院理学研究科の大堺利行准教授に来校していただき、今年のテーマである「泥燃料電池」について研究を行うにあたり、電池の仕組みや電気エネルギーについて講義を受けた。その後、昨年の先輩の研究を参考に泥燃料電池を作成し、泥が本当に燃料になるのかを確かめる実験を行った。負極側にKClaq、正極側に(COOH)2aqを入れ、泥を入れない場合はほとんど計測できなかった起電力が、泥を入れると約0.2 vになることを確認し、泥が燃料になっていることを実感できた。次回は、各自がいろいろな種類の泥を持参し、研究を進める予定である。
<生物>
今年度の研究として生物を選択した生徒6名と研究室を訪問した。昨年度の研究論文をもとに、研究目的や実験内容等の質問、説明を受けた。その後、今年度の研究テーマを検討するために研究室で飼育、培養している生物(主に原生生物)の観察を行った。生徒たちが普段あまり目にすることのない生物種を観察することができた。原生生物の特徴やまだ解明されていない点、細胞内共生がどのように行われていくのかなど、現在の研究テーマに関する説明も受けることができた。
都市工学班は、まず、都市工学を選択した動機を含め各自が自己紹介をおこなった。その後、夏休みの課題の実施状況についての確認と各自の考えを発表して全員で共有化した。つぎに、澤木先生より「ピクチャレスクな街並み景観に関する研究」に関連して景観印象評価についての講義があり、印象評価実験を全員で体験した。それから各チームの進め方について議論をおこない、チームAの景観研究は、アニメとそのもとになった現実の場所の調査をし、その差異から受ける印象について考えること、また、音楽と景観の関連についてどのように取り組むかについて考えることとした。一方、チームBの集団ねぐら研究は、名谷駅や西神中央駅付近でみられるムクドリの集団行動について確認することと、後日先生よりお送りいただく先行研究についての論文から次の進めかたを考えることとした。次回は、それぞれのチームで方向性の議論を深めていく予定で、次々回に先生に実施計画についての確認・ご指導をいただく予定だ。