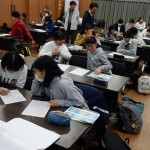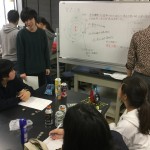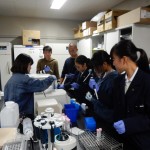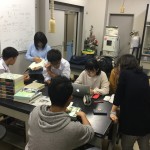-
最近の投稿
最近のコメント
アーカイブ
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年7月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年9月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年1月
- 2012年9月
- 2012年6月
- 2011年12月
カテゴリー
メタ情報
平成30年11月26日 RRE校内発表”The Effects of an Aging Population”
本校同窓会館ゆ~かり館において、本校創造科学科3期生(1年生)40名がパワーポイントを用いて”The Effects of an Aging Population”をテーマに校内発表会を行った。データを活用しながら、課題や課題解決に向けての取り組みの提案ついて発表を行った。
それぞれ他の班の発表を評価しあった。
カテゴリー: 創造科学科3期生
平成30年11月26日 RRE校内発表”The Effects of an Aging Population” はコメントを受け付けていません
平成30年11月22日 第9回高校生鉄人化まつり実行委員会(1)
長田区役所大会議室において、第9回高校生鉄人化まつり開催に向けた第1回会議が開かれた。このまつりは、平成22年度に長田区主催の「第2回鉄人まちづくりイベント」に応募した本校総合科学類型1期生(創造科学科の前身)の提案が最優秀賞を受賞し、長田区に所在する高校のさまざまな活動発表の場としてが実施されるようになったものだ。本校からは創造科学科1期生5名、育英高校からは生徒会4名、神戸野田高校からは生徒会3名が実行委員として参加した。自己紹介のあと、役員決め、今回のテーマ、今後の大まかな予定について話し合われた。今年度は実行委員長を神戸野田高校と本校生徒が共同で担うことになった。次回会議は12月13日(木)の予定。
カテゴリー: 創造科学科3期生
平成30年11月22日 第9回高校生鉄人化まつり実行委員会(1) はコメントを受け付けていません
平成30年11月21日 創造基礎A 講義「国民が納得する『やさしい社会』を実現する方策とは」
本校同窓会館ゆ~かり館において、創造科学科3期生(1年生)を対象に、「国民が納得する『やさしい社会』を実現する方策とは」というテーマで講義を行いました。講師として、財務省大臣官房地方課広報連絡係長の内村裕幸氏をお招きし、またグループワークのサポートとして近畿財務局神戸事務所から2名の方に来ていただきました。まず、内村氏から「今の日本、これからの日本について考えよう」というテーマで、日本の財政に関わる課題について講義をしていただきました。次に、財務省が作成したシミュレーション教材を使って事前に作成した予算案について、財務省職員の方々と質疑応答を行いました。最後に、予算案のポイントを視覚的に説明する「ポンチ絵」を作成して発表しました。
神戸新聞NEXT「兵庫高で全国初 財政と金融講座を同時実施へ 神戸財務事務所」
サンテレビ「財務大臣になったつもりで 高校生が国家予算編成を体験」
〈生徒感想〉
僕はこの予算を作るときに多角的な見方をする力を少し身につけることができたと感じています。税の増減、予算の振り分けの増減で影響が出る人を考えなければならず、様々な見方が必要となりました。また、その予算のメリット・デメリットを考え、その対策を一つずつ考えていくことが大切だと学びました。これからは一つの問題には多角的な見方をして、様々な解決法をメリット・デメリットから考えるべきだとわかりました。
立場の違う人たちが利益を得られて、みんなが納得できるような方法を考えることの難しさを痛感しました。だからこそいろいろな人の立場になって考える力が少しは身についたのではないかと思います。しかも、立場が多いだけではなく、国際関係などの国を超えた環境や税金によって社会保障が出されることなど、複雑な立場も視野に入れて活動したので、それらの関係を見越した視野も養われたのではないかと思います。
今回の授業で、対象の立場になって考えることの重要性を学びました。この予算案にしたら誰がどんな風に困るのか、誰にとってありがたいのかということを考えて、国民全員が納得する政策を作らなければいけないとわかりました。このことは、次回の授業の模擬選挙や創造基礎の地域活動、また、社会人になってからも大事なことだと思うので、日々相手の立場になって考えることを心がけようと思います。入学したときから目標にしていた複眼的思考力を身に着けることは、相手の立場になって考えることからも鍛えられると思うので、努力したいです。
今日の授業で、内村さんが国は政府と国民しかいないわけではなくて、家族、企業、学校などさまざまな団体や組織で成り立っていると言っていたことが心に残っています。そのことに気付いて、国の予算を色々な立場で見ることの大切さを学びました。この予算を考えることを通して、私は自分の国を客観的に見る力がついたと思います。
カテゴリー: 創造科学科3期生
平成30年11月21日 創造基礎A 講義「国民が納得する『やさしい社会』を実現する方策とは」 はコメントを受け付けていません
平成30年11月21日 GRⅡ 「植物の機能性評価」
本校化学実験室において、グローバルリサーチⅡで「植物の機能性評価」をテーマとする3班の5名が、ニンニクの抗炎症作用・殺菌作用はニンニクの種類により違いが出るのかを調べるために3種類のニンニクの抽出作業を行った。日本産の白ニンニク、日本産の黒ニンニク、ベトナム産の黒ニンニクをそれぞれエタノールを用いて抽出を行った。
カテゴリー: グローバルリサーチ
平成30年11月21日 GRⅡ 「植物の機能性評価」 はコメントを受け付けていません
平成30年11月21日創造応用ⅠL「ポスター発表会」
本校クラス教室・選択教室において、創造科学科2期生(2年)文系選択者12名が6名ずつに分かれて、自身の取り組む課題研究について、ポスター発表(発表8分・質疑応答4分)を行った。大阪大学大学院国際公共政策研究科松繁寿和教授および大学院生2名、岡山大学法学部の本校卒業生に発表後の質疑応答や講評をしていただいた。生徒からもたくさんの質問があり、大いに盛り上がった。今後の研究の方向性を考える上で貴重な時間を過ごすことができた。
生徒の今回の発表テーマは以下の通りです。
「若者の意見表明に関する考察~英国と日本の比較を通して~」
「日本でヒアリを対策するには?~発見者は子供」
「ベトナムにおける給食制度改善への考察」
「ソーシャルビジネスの可能性」
「日系ブラジル人のアイデンティティ教育」
「イギリスからの訪日外国人を増やすには」
「日本で難民を受け入れるためには」
「外国人労働者に多く来日してもらうために」
「ロヒンギャ難民問題」
「もっと知ろう、北方領土のこと」
「タックス・アムネスティを用いたグローバル・タックスについて~格差の小さな社会を目指して~」
「日本で電気時自動車を普及させるためには」
カテゴリー: SGH(学科2期生), 創造科学科2期生
平成30年11月21日創造応用ⅠL「ポスター発表会」 はコメントを受け付けていません
平成30年11月17日 関西学院大学総合政策学部リサーチ・フェア2018
関西学院大学三田キャンパスにおいて、普通科グローバルリサーチⅡ(2年)7班2名と、創造科学科3期生(1年)社会科学分野5班と6班の9名が、同大学総合政策学部主催「リサーチ・フェア2018」に参加し、大学生や大学院生とともに研究の成果を発表した。
2年生は「条約難民への日本語教育支援の改善策」というテーマで口頭発表し、大学の教授から多くの質問をいただき、議論して研究を深めることができた。1年生は5班の「親子ハッピーフェスティバル」と6班の「源平歴史街道ツアー」いうテーマで口頭発表し、大学教授からテーマ設定や研究の進め方について講評をいただいた。2テーマとも大学生の研究に交じって、堂々と発表した。
なお発表会後、関西学院大学総合政策学部の卒業生でコンサル会社の人事担当や市会議員の方々から大学の学びや就職、仕事についてお話を伺うことができた。
<生徒の感想>
11/17日に関西学院大学三田キャンパスで関学リサーチフェアがあった。これまでの校内発表とは違い、初めての校外での発表で、また、他の高校や大学の生徒も参加していたので今まで以上にパワーポイントなどの準備を入念にした。
当日は早めに現地に集合し、発表練習をした。今回の発表時間は15分と今までの発表の約二倍の長さだったので、時間にゆとりがある一方でより深い説明をしなければならなかった。
発表本番は練習の成果もあり原稿を余り見ずに発表を行うことができた。その後の質問時間では大学の先生方の核心をついた質問や指摘を頂いた。質問に上手く答えられなかった点もあり、私は自分たちの提案内容がまだまだ不完全であることを実感した。
昼食の後関学のOB,OGの方々からの話を聞く会があった。そのなかで私は大学や高校での活動は姿を変えて将来役に立つという言葉に特に印象を持った。
発表の結果としては一つも賞をもらうことはできなかったが、大学の先生方のアドバイスや他の高校や大学の生徒を見て自分たちの提案内容に活かせる多くの事を学ぶことが出来た。この事を3月のツアー開催などに役立てたいと思った。
カテゴリー: SGH(学科2期生), グローバルリサーチ, 創造科学科3期生
平成30年11月17日 関西学院大学総合政策学部リサーチ・フェア2018 はコメントを受け付けていません
平成30年11月19日GRⅠ「地元企業の海外進出とその課題~グローバルリーダーの資質~」
本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、普通科グローバルリサーチⅠ受講者(1年)40名を対象に、三ツ星ベルト株式会社の人事部長 倉本信二氏に「地元企業の海外進出とその課題~グローバルリーダーの資質」をテーマに講義をしていただいた。初めに三ツ星ベルトの概要と海外進出の現状についてお話を頂き、実際に三ツ星ベルトのインドネシア工場であったトラブルについて、ディスカッションした。その後(1)「グローバル人材」とはどんな人材なのか、(2)「グローバル人材」になるためにはなにが必要かについて、グループで話し合った。各グループ発表の後に、倉本氏から補足説明をいただいた。最後に米中貿易摩擦が日本企業にどのような影響を与えているかについて考え、知識を得る機会となった。
〈生徒の感想〉
今回の講義では、三ツ星ベルトの海外進出の状況を知り、海外ではコストの上の面で利益が大きくなるというので良い事ではあるが、逆に長期休暇後には、人が3分の2しか出勤してこないことがあったり、ストライキが起こったりといった日本人の考え方にはないようなことが起こってしまうので大変だと思いました。また、グローバル人材に一番大事なのは、コミュニケーション能力だと思いました。現地の労働者の声に耳を傾け、労働環境をよくしていかなければ経営に響いてくることにもなるので重要だと思いました。グループの発表を聞いてみて「グローバル人材」というものにも、さまざまな考え方がありおもしろいと思いました。現在国会で審議中の外国人労働者の受け入れに関する法律が施行されれば、さらに「日本のグローバル化」が進んでくるのですべての人に「グローバル人材」になる必要があると思いました。
今日、日本の企業が多く、海外に進出していることは知っていたが、進出する具体的な理由は初めて知ったし、グラフで見たり、関連するもの、また特に海外での賃金が予測つきづらいことを初めて知った。現地で起こる問題は新しく複雑で、日本人には理解しづらいその国の特性によるものだったり、労働環境や賃金によるものだったりと様々であると学んだ。これから選ばれるグローバル人材となるために、グループの人やほかの生徒の意見を聞いて、新たな発見があり勉強になった。GR生として今回のワークショップは最もよく考えなければならないことだと思った。必要とされる人材となるために高校生のうちに多くのことを経験していきたい。また、専門外の知識をつけ、視野を広くし、色んな人と会って、自分のもっていなかった考えを頭に入れていきたい。
今日は、実際に海外進出している企業である三ツ星ベルトの倉本さんから貴重なお話をしていただきました。神戸のゴム産業の歴史から海外進出の話まで様々な話を聞くことができました。ASEANの国の最低賃金が年々急激に上昇しているということに驚きました。これからさらに賃金が上昇していけば、1つ目のディスカッションのように企業を離れていく人が増えるのではないかと思いました。そうならないようにするためにも物事の先を読む力が大切なのではないかと思いました。最後のワークショップでは、他の班の意見なども聞きながら、「グローバル人材」について考えることができました。倉本さんがおっしゃられたように、考えるなかで出た意見はすべて「グローバルな人材」のために必要なことだと思うので、私もそうなれるようにがんばろうと思いました。
カテゴリー: グローバルリサーチ
平成30年11月19日GRⅠ「地元企業の海外進出とその課題~グローバルリーダーの資質~」 はコメントを受け付けていません
平成30年11月17日・18日 第12回全日本高校模擬国連大会
国際連合大学において、第12回全日本高校模擬国連大会が開催され、本校創造科学科3期生(1年)の2名が参加した。本大会は、全国各地から集まった高校生が各校2人1組となり、
<生徒感想>
今回、模擬国連に参加し、次の三つのことを考えた。ひとつは、英語と定められた公式発言(スピーチや動議)を以前の灘高校での練習会議のときより少しだけ聞き取れるようになったことだそのおかげで、各国がどういう立場で何を思っているのかを把握しやすくなった。次に、他の国の大使が政策などを述べて、それを一旦は理解した”つもり”になってメモもするが、改めて見たり他人に訊かれたりすると分からなくなるということがあった。それは、自分の中では納得できたとすぐに思ってしまって、相手の意見の十分でないところへの指摘、疑問が思いつかないことが原因の一つであると思う。だから、来年の模擬国連に向けてのこの1年で、話を整理するのを得意になるというのを目標にして努力したい。最後に、グループのリーダーとなって、他の大使の意見も尊重しつつも自国の意見も上手く入れこんだという点が良かったのだと思う。また、一方はリーダーとなり、もう一方は会場を見て回り、情報収集を良くしていたのが印象に残っている。
今回の全日本模擬国連大会でできたことは、3つあります。文言を入れ込んだ決議案を通せたこと、スピーチをできたこと、議論を深めることができたことです。一方で課題は、主に2つあります。1つ目は、政策が浅かったことです。2つ目は、もっと積極的に発言して存在感を示すべきだったことです。政策が浅かったことで、積極的に発言できなかったとも言えます。ニューヨークに行きが決まった他校生の議場行動が評価されたと思われる点は、リーダーシップです。ペアと効果的に役割を分担し(1人はグループでのリーダー、もう1人は外交)、グループのメンバーの意見を尊重しながら主導したチームが、評価されているように感じました。また、モデで積極的に発言しているチームは、選ばれているところが多かったです。これは、モデで発言することで、全体に自分たちのことを認知してもらう効果があったと思います。
カテゴリー: SGH(学科3期生), 創造科学科3期生
平成30年11月17日・18日 第12回全日本高校模擬国連大会 はコメントを受け付けていません
平成30年11月13日 創造基礎B 自然科学分野「神戸大学実験実習」
神戸大学大学院人間発達環境学部において、創造科学科3期生(1年)の生徒39名が、各ゼミの大学院生の指導のもとで実験実習を行いました。高校では使用することができない施設や実験機具を使ったり、専門的な内容について半日かけて学習しました。
1班 山元ゼミ 「りんごと大根の糖度解析」
2班 中村達・河野ゼミ「植物の酵素の反応速度に関する研究」
3班 邑上ゼミ「ありの生態観察」
4班 中村元・山本ゼミ「X線を使った物質の非破壊元素分析」
5班 勝原ゼミ「テストで点取り大作戦-頭を使って点数を取ろう!-」
6班 速水ゼミ「環境DNA分析手法を用いた環境改善方法の調査」
7班 矢井田ゼミ「身近に生きる植物たち」
8班 中村崇・松田ゼミ「身の回りの放射線」
カテゴリー: SGH(学科3期生), 創造科学科3期生
平成30年11月13日 創造基礎B 自然科学分野「神戸大学実験実習」 はコメントを受け付けていません