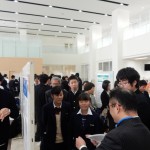兵庫教育大学において、創造科学科3期生(1年生)40名が同大学に留学している外国人留学生・教員研修生10名と英語を用いて交流会を行った。2回目の交流となる今回は、「人口問題」をテーマに話し合った。アイスブレーク活動とお互いの自己紹介の後、高校生は「現状の日本の人口問題の課題点と改善案」について同様にプレゼンテーションを行い、留学生から「自国の人口問題」についてパワーポイントを用いたプレゼンテーションを行っていただいた。難しいテーマではありましたが、この一年間で培った経験を活かし、積極的に英語で議論する姿が印象的であった。




留学生の出身国は以下の通りです。
クロアチア、ベトナム、中国、韓国、ウズベキスタン、マラウイ、イタリア
〈生徒の感想〉
I found that Croatia has been becoming the aging society like Japan in the exchange meeting with an international student. I heard that aging is a problem in the world as well as Japan. In addition, there is a problem that decline the population of Croatia. I learned it is caused by economy, decreasing of the workplace and so on. From this, I found that various things generated issues which each country has. When I look back on my action of this exchange meeting. I think that I made a better presentation than the last announcement. However, I could not remember English words and grammar immediately. Therefore, I thought that I should learn English words and practice speaking English to talk in English positively.
I learned a lot today. Firstly, I learned difficulty of expression with English. I thought that I must memorized English words harder. However I could communicate with body language, so I will attempt using body language at my speech. Secondary, I knew difference in the cause of aged society with countries. In China, it starts with one house one child policy. However there are things. China and Japan in common. For example, people who won’t have a child hope to work and spent their partners. Also, people who want children do not have money enough to grow up their children. I noticed many points for important during today. I must not be afraid of making mistakes in particular. My English was not good but I expressed what I wanted to communicate with you. Because of this, I could talk with a student from China. I want to express my thoughts more and understand their thoughts. So, I try studying hard and I would like to communicate well.
There are two things I learned. Firstly, I learned problems Uzbekistan has. There are five main issues in Uzbekistan. First is the environmental issue. Uzbekistan has lakes, but it is being dried-up. So, salty wind blows. Second is the employment issue. There is not enough jobs in Uzbekistan. So, many people go abroad to work. Third is the industrial issue. Uzbekistan used to be colonized by Russia. So, agri- business is its main industry now. It has to change it to second industry. Fourth is the medical issue. Its population is becoming larger, but many people die from disease. Fifth is the educational issue. The opportunity of education is not equal. There is not aging population issue. Issues in Uzbekistan are different from that in Japan. Secondary, I learned that education in Japan is expensive in foreigner’s view. So, we thought that the government should make kindergartens. Then, parents who have little children can raise their children move easily, and work. I tried to do two things this time. To listen with good reactions and to talk positively. I think I could do both the two things. So I feel satisfied with it. And I could understand most of the presentation the international student made. But I could not understand some words, because he spoke English with a few accent and fast. Next time, I want to understand all.