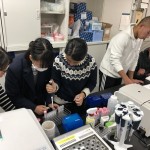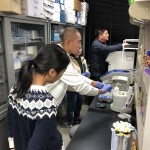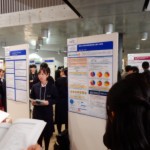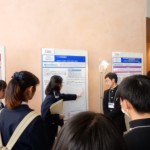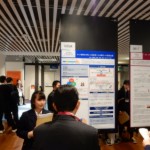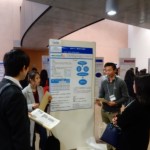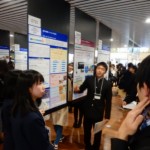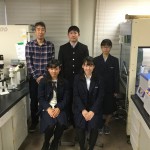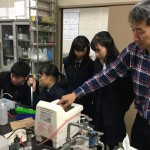3学期もよろしくお願い致します。
インターナショナルデー
2月7日、神戸大学、関西国際大学、神戸情報大学院大学の留学生を迎えて実施しました。
前半の全体会では、カンボジアとギリシャの高校生活、お祭り・食べ物などの習慣や風習のお話を伺いました。
後半は各クラスに分かれ、ガーナ・モンゴル・中国・タンザニア・フィリピン・台湾のお話を伺ったり、遊びの体験をしました。
(全体会)


(クラス別)






2・3月行事予定
2月
2(土)土曜教室・数学特別授業
7(木)インターナショナルデー(午後)
8(金)全校読書会
9(土)土曜教室
14(木)3限まで授業・大掃除
15(金)推薦入試のため休校・模試(希望者)
26(火)卒業式式場設営・大掃除
28(木)卒業式
3月
1(金)~7(木)学年末考査
7(木)通学路清掃
8(金)人権学習
11(月)大掃除
12(火)~14(木)生徒休業日
15(金)教科書販売・個人写真撮影
18(月)学年集会
19(火)生徒休業日
20(水)球技大会
22(金)終業式・大掃除
カルタ大会
1月24日、カルタ大会を実施しました。各クラス代表の大将戦・副将戦と
一般戦に分かれ、白熱した大会となりました。
結果は以下の通りです。
優勝 6組
2位 8組
3位 5組





カルタ大会(練習)
1月24日のカルタ大会に向けて、LHRを利用してクラスで練習をしました。
句を覚えている人も多く、練習とはいえ、かなり熱の入ったものでした。


1月行事予定
1/8(火)始業式・課題実力考査
1/9(水)課題実力考査・4限から授業
1/17(木)震災追悼行事(黙祷・校長講話)