3月7日に未来創造コース2期生6人とグローバルリサーチ選択者2名が駒ヶ林駅から兵庫高校まで震災前の地図、震災の被害状況、現在の地図をもってまちを歩き、フィールドワークを行いました。大阪大学の澤木先生と松本先生に同行していただき、都市工学の観点から、法律の話も含めてまちづくりに関することを解説していただきました。
兵庫高校に到着してからは、学んだことを話し合いました。今後は今回学んだことを生かし、テーマを決定し研究を継続していくことになります。
〈生徒の感想〉
駒ヶ林から真野、御菅まで歩いて探索をしました。何回か行ったことのある駒ヶ林は、路地がたくさん入り組んでいるどこか懐かしい雰囲気のまちでした。次に真野に行きました。真野でも路地などがあって駒ヶ林と同じ印象を受けました。最後に歩いた御菅は、道が広く、建物もビルや新しい家などが多く、現代のまちだなと感じました。これらの違い背景には、阪神淡路大震災の影響がありました。駒ヶ林や真野に比べて〇〇は、火事の被害で焼けてしまいました。そのため、昔の家の面影はほとんどなく、最近建てたような家ばかりでした。歩いてみて私は、駒ヶ林や真野のようなまちの方がいいなと思いましたが、震災の背景を聞くことによって、仕方がなかったのだなと少し悲しくなりました。散歩をするだけでも、色々なところに気が行って、とても楽しかったです。これからの活動も楽しみなので、頑張っていきたいです。
今日はまち歩きを行った。三つの地区を歩いたが、いろんな観点から考えることができ、面白かった。その中で気になったことが3つある。1つ目は災害と都市計画の関係だ。駒ヶ林のまちなか防災空地、御蔵地区の震災復興後の町並みを見ると、2つの関係は深いと感じた。2つ目は境目についてだ。都市計画の地図を見ながら歩くと、産業ごとや住宅地によってはっきりと違いがあることがわかった。何気なく歩いていた町も違って見えた。3つ目はその土地に住む人だ。道やちょっとしたものから特徴が見えるような気がした。しかし行政が行っているものも多い。だからもっと地域の人が主体的に行うまちづくりが進めばいいなぁと思った。私が感じたのはこの3点だか、今日の参加した人の意見を聞くとまた違ってみえてくるものがあった。これをまとめて来年度へつなげたい。
今日は、長田の町を歩きました。初めて歩くところもあり、長田の新たな1面を感じたように思います。また、駒ヶ林には、これまでの創造の授業で訪れたことがありましたが、いつもとは違う目線で見てみると、感じるものもありました。全体的に、防災についてよく考えた町だと感じ、長田の町は地域の方々の繋がりが強いのだと感じました。兵庫高校に帰ってからのワークショップでの皆の意見は、自分と違うものもあり、面白かったです。これまで、町歩きをする機会もなかったので、今日はいい発見がたくさん出来ました!
今回長田の街を探索して、長田について知っていると思い込んでいたけれどまだまだ知らない事が沢山あるのだと発見できました。特に、狭い路地にいろいろな店があったりと、地域に根ざした物を多く見つけることが出来ました。これから色々な地域を探索してみたいと思いました。最後のまとめであまり積極的になれなかったのでそこを改善したいと思います。
今日のフィールドワークでは多くのことを感じることが出来ました。まず、今日歩いたような町並みは自分の家の近所には無く、とても新鮮でした。また、歴史を感じさせるような雰囲気が漂っていました。まとめのワークショップでは他の人が気付いたことも知ることが出来ました。例えば、震災当時の民家がそのまま残っていることに関して、残しているのは良いことだという意見と、崩れる危険性があるのであまり良くないという意見が出ました。一つのところをとっても、このように人それぞれ感じ方が違うということが分かりました。今日の活動を通して、町という漠然としたテーマを、道や防災といった細かいテーマに分けて見ることが出来て、この授業の具体的なイメージを掴めたと思います。
前回参加ができず、今回が初めてとなった大阪大学の都市工学フィールドワークですが、とても良い経験になりました。長田の町中を歩きながら気づいたところを書き出すという作業を通して、普段は気づかないいろいろなことを発見することができました。町中には震災などの被害を最小限に押さえるための工夫などを凝らした場所があった反面、使われてない空き地もたくさんありました。このような点を改善すれば、もっと良い町が作れると思います。最後のまとめ作業では、他のメンバーの意見もしることができ、よかったです。
今回初めてフィールドワークをやってみて普段座っているだけでは気づかないようなことをたくさん見つけることができたと思います。都市開発について調べていっている中で、実際身近な所で行われている計画を見ることにより、興味や関心がより深まりました。今回は長田の町でフィールドワークを行いましたが、知らないことばかりでした。神戸にはまだまだ昔ながらの町並みが残っていることに僕は一番感動しました。震災を経験し、復興した神戸のもう一つの〝カタチ″を見ることができたと思います。また、先生方がおっしゃっていたとおり区画整理についてもよく学ぶことができました。あそこまではっきりと分かれているとは思いませんでした。そして最後に行った意見の出し合いでは自分とは別の視点からの意見が多くあったので勉強になりました。意見の共有の必要性が分かりました。これからも続いていく都市計画についての研究で今回のフィールドワークの経験をいかしていけるようにしたいです。








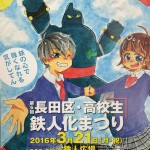
 1組 思い出作り
1組 思い出作り 2組 自習!
2組 自習! 3組 絵しりとり
3組 絵しりとり 4組 体育館でドッジ
4組 体育館でドッジ 5組 焼いも班
5組 焼いも班 5組 グラウンドでサッカーに興じる班
5組 グラウンドでサッカーに興じる班 6組 グラウンドでドッジ
6組 グラウンドでドッジ 7組 講堂で卒業式の会場設営
7組 講堂で卒業式の会場設営 8組 体育館でバスケ
8組 体育館でバスケ


















