今年初めての実施となった”Science Conference in Hyogo”に未来創造コース1期生(2年)4名が参加し、創造応用で行った探究活動の成果を英語でプレゼンテーションしました。このプログラムは、サイエンスフェアをさらに発展させ、科学技術の分野での英語運用能力を控除いさせることを目的とし、県内の理系に研究を入れているSSH校を中心に10校が参加しました。本校からは理系で3つ、文系から1つのテーマを発表しました。All Englishでのカンファレンスということで、最初の基調講演、生徒の発表、そして発表後の質疑応答まで全て英語を活用することが義務付けられ、参加した生徒たちも英語漬けの1日に大変な思いをしながらも、充実した1日になったようです。
〈生徒発表タイトル〉
The relationship between sleeping time and efficiency of studying(睡眠時間と学習効率の関係)
Vietnamese drug resistant germs problem seen from water(水から考えるベトナムの薬剤耐性菌問題)
The relationship between factors of sounds and annoyance(音の要素とうるささの関係)
Using Euglena to Check Water Quality(水質検査におけるミドリムシの利用)
〈生徒の感想〉
I think, it was the great chance to “USE” English!! To be honest, explaining the scientific words is very very difficult for me. Besides, to understand statistics is also very difficult for me. So,I checked my script again and again to make my study understood easily. In fact, questioning and answering was more difficult than presentation. I sometimes forgot English word even it was a easy word. I felt I have to study English more harder. And also try to USE English is really important way to study English. I’m going to try to use English aggressively from now on.(今日のイングリッシュカンファレンスは、「英語を使う」というとても貴重な経験でした。正直なところ、理系の専門用語の説明は日本語でも難しく、それを英語にするのは本当に大変でした。また、統計学は自分で自分の研究内容を理解するので精一杯なくらい難しく、それらをいかに分かりやすく伝えるのか、発表の直前まで原稿を必死に確認しました。実際、原稿の内容は英語科の先生に確認してもらえるのでまだよかったのですが、質疑応答は、聞かれたことにすぐに自分で英語を組み立てて答えなければならず、経験の浅さを痛感しました。 これから先、英語を使う必要はどんどん高まっていくと思います。今から、「英語を使う」練習を繰り返し行い、経験を積んでいきたいです。今回、私はサイエンスカンファレンスに参加した。自然科学の研究内容を英語で発表するというものだ。沢山の高校生、ALTが参加していて、とても活気のある会だった。発表の準備をしてはいたが、実際に英語で質問が来ると、適切な答えを返すことができず、英語でのコミュニケーションの難しさを感じた。また、他の人の研究内容を英語で聞くということは、大変だが、とても貴重な経験となり良かった。)
第一回サイエンスカンファレンスin兵庫は私にとってとても貴重な経験になりました。まず、事前準備でお世話になったALTや先生に感謝の気持ちでいっぱいです。原稿を何度もチェックしてもらう中で自分の語彙力も深まりました。原稿の大半はそのまま英語に直すだけでしたが、日本語では通じる言葉が英語では理解しづらく、言語の差というものを痛切に感じました。よりわかりやすく伝えるにはどうすればいいのか、と試行錯誤しながら研究への理解を深められたと思います。また、質疑応答では、自分の拙い英語がALTを含む聞き手の方々に通じたので、英語で伝えるということを身近に感じられました。しかしそれと同時にスピーキング能力の不十分さや語彙力のなさを痛感し、今後は長文の英語を声に出して読むなど、もっと英語に親しんでいきたいと思いました。















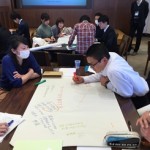








 T先生より諸注意
T先生より諸注意 男子はドッヂ
男子はドッヂ 女子はバレー
女子はバレー 出場クラス以外は応援_女子
出場クラス以外は応援_女子 出場クラス以外は応援_男子
出場クラス以外は応援_男子 表彰式
表彰式 学年主任から講評
学年主任から講評




