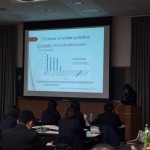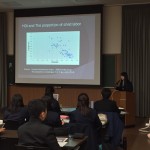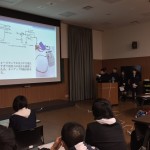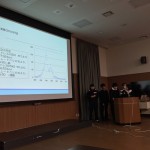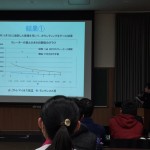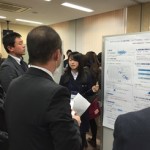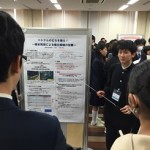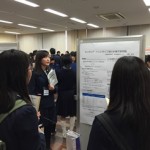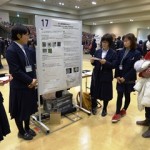本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、未来創造コース1期生(2年)の文系選択者が国際問題に関する課題研究を英語で発表しました。発表時間7分、質疑応答3分で行いました。今回お世話になった大阪大学大学院の院生3名も出席いただいて、質疑と講評をしていただきました。以下は生徒の発表タイトルです。
・「Water problems in Ethiopia」(エチオピアにおける水問題について)
・「Measures for tuberculosis in Papua New Guinea」(パプアニューギニアに於ける結核対策)
・「The project to improve teacher’s academic ability in Guatemala」(グアテマラ教員学力向上プロジェクト)
・「Water pollution in Tonle Sap Lake」(トンレサップ湖における水質汚染について)
・「The role of the government and NGO for child labor in Nepal」(ネパールにおける児童労働についての政府とNGOの役割を考える)
・「Japanese support of refugees by “Resettlement Programs”」(第三国定住で進化する日本の難民支援)
・「Drug resistant germ problems in Vietnam」(ベトナム農村部の水環境改善による薬剤耐性菌蔓延防止への考察)
・「The refugees acceptance in Japan」(日本の難民受け入れのあり方を考える)
大学院生のふりかえり
まず、プレゼンテーションの注意点として、1)参考文献の書き方は型通りにすること、2)専門用語が多かったので常用の言葉で表現すること、3)示した表が小さくて見えないので拡大するか自分で作り直すこと、4)スライドとペーパーは同じものにするべきでアニメーションの多用は禁物。提案について、自分なりの提案となっているか、すなわち高校生ならではの発想や文化を取り入れたものにしてみると面白い。また、身近なことや地域での取り組みを発展させるのもいいかもしれない。ただし、論議の文脈にそった提案でなければいけない。さらに、日本の取り組みが必ずしも正しいわけではないので、当事者や当事国の視点に立てるように自分の視線の位置を変える必要がある。院生自身にとってよかったことは、自分の課題テーマを振り返るきっかけになり、やはり本当にやりたい課題に取り組むべきだと感じたことや、教える側の気持ちがわかり授業の楽しさを感じることができた。