夜には東京大学に在籍中の理数科の先輩2名に来ていただき、話を伺いました。
大学生活の様子、高校時代の勉強方法など、活発な質問を交わしながら充実した時間でした。
講演終了後も先輩を取り囲んで、次々と質問をしていました。
また、宿泊しているホテルの窓からは、ライトアップされたスカイツリーが目の前に見えます。
明日はつくばに行き、研究施設で研修をします。



夜には東京大学に在籍中の理数科の先輩2名に来ていただき、話を伺いました。
大学生活の様子、高校時代の勉強方法など、活発な質問を交わしながら充実した時間でした。
講演終了後も先輩を取り囲んで、次々と質問をしていました。
また、宿泊しているホテルの窓からは、ライトアップされたスカイツリーが目の前に見えます。
明日はつくばに行き、研究施設で研修をします。



東京駅から、みんなで山手線に乗って国立科学博物館まで移動しました。
初めて東京に来た人もいて、人の多さやビルの高さに驚いていました。
次々来る電車の本数も、加古川線の15倍だ!と計算していました。
上野公園では、ロダンの考える人に遭遇!一緒に何かを考えてみました。
国立科学博物館は科学の様々な分野の研究成果が分かりやすく展示されています。
真剣に興味津々で見学をしていました。
見学時間は約5時間ありましたが、まだまだ見足りないようでした。




72回生理数科が東京研修に出発しました。
以下の内容で2泊3日の研修を行います。
1日目 国立科学博物館
東京大学に在学中の先輩の講話
2日目 農研機構 果樹茶業研究部門
筑波宇宙センター(JAXA)
高エネルギー加速器研究機構
課題研究の研究テーマを考えるための夜間研修
3日目 東京大学理学部
東京大学地震研究所


自然科学部地学班と物理班による、小中学生対象のオープン・ザ・研究室が開催されました。
子どもたちは、高校物理の内容など少し難しい説明にも熱心に聞き入り、高校生に教わりながら顕微鏡での観察や実験をしました。
終了後も、夏休みの自由研究のアドバイスをもらったり、自然科学部の研究について説明を聞いたりして高校生とふれあいました。いっぽう本校自然科学部の部員達にとっても、大変有意義な時間となりました。





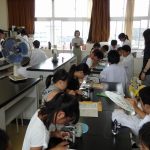
1年生理数科が夏休みの東京研修に向けた事前研修で、スマートフォンを使ったデータ収集、整理方法を学びました。研修先でのメモや写真等の効果的な整理方法を学び、東京研修だけではなく、今後の課題研究にも活かせそうです。



理数科1年生が理数科の教育活動に早く慣れるように、理数科2、3年生との交流会を行いました。
はじめに2、3年生の自己紹介と取り組みについての発表があり、続いて出身中学の地域ごとに6グループに分かれて理数科1年生と交流しました。
入学してから多少不安な面もあった1年生ですが、先輩達との交流により、探求活動に取り組む心構えができてきたようです。


第7回つくば中高生国際科学(サイエンス)アイデアコンテストが3/21(火)、3/22(水)、つくば国際会議場でおこなわれました。
口頭発表、英語ポスター発表、日本語ポスター発表の各分野で2日間にわたり発表会が開催され、本校からは、自然科学部物理班微小重力チームの頃安祐輔(2年)・荒谷健太(2年)の2名が、発表テーマ「校内で使用・再現可能な微小重力実験の確立」で出場し、日本語ポスター分野で142件の発表中、第3位を獲得しました。



平成28年度英語による課題研究発表会(兼「理数英語プレゼンテーション」発表会)が行われ、2年生理数科の生徒が課題研究を英語で発表しました。他校の先生方やALT(外国語指導助手)も発表を見に来て下さり、ALTと英語での活発な質疑応答が繰り広げられました。
発表のあとは各研究班で先生方と研究の協議と交流会が行われました。
平成28年度SSH研究発表会が加古川市民会館で行われ、2年生理数科と自然科学部が今までの研究の成果を発表しました。発表会には本校生徒、保護者に加え、中・高・大学の先生方も参加され、盛大に行われました。
小ホールで課題研究の8班、自然科学部の7班、計15班のポスター発表を実施し、それぞれの研究の成果を披露しました。
中ホールでは、先日のクラス内発表会で選ばれた課題研究班3班と、自然科学部の2班、計5班が口頭発表を行い、活発な質疑応答が行われました。また、活発な質疑応答を通じて今後の研究の課題を見つけることができたようです。
口頭発表の各班のテーマは以下のとおりです。
2年生理数科の課題研究クラス内発表会が行われました。
司会・計時・マイク係は生徒が行い、合計8班の課題研究班がパワーポイントを使ってプレゼンテーションを行いました。
各班の発表後は活発な質疑応答が行われました。
各課題研究班の研究テーマは以下のとおりです。