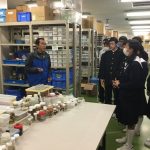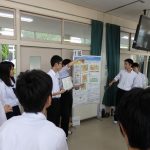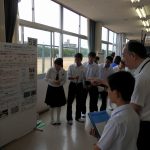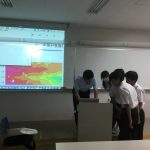1年生理数科が先日行ったミニ課題研究の実験結果を分析し検証して、発表資料の作成をしました。
実験で得た数値データを打ち込んでグラフ化し、仮説との整合性を分析しました。
実際に分析してみると、数値データが本当に正しいのか、仮説の設定が適切であったのかなど様々な問題に四苦八苦している様子が見られました。より説得力を持つ研究をするためにはどうすればいいのか。今回のミニ課題研究の経験を、来年度に取り組む課題研究に活かしてもらいたいと思います。
また、実験で得たデータを、物理や数学の授業で学んだ知識と結びつけて分析している班もありました。日々の授業で学んだいることを積極的に応用する姿勢も見られました。