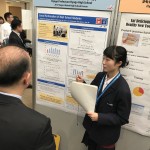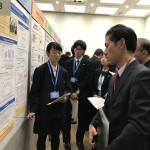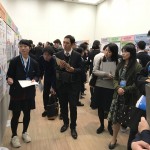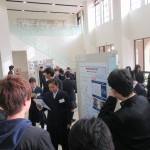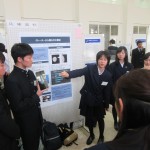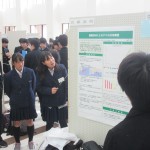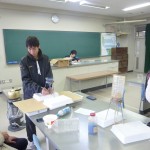-
最近の投稿
最近のコメント
アーカイブ
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年7月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年9月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年1月
- 2012年9月
- 2012年6月
- 2011年12月
カテゴリー
メタ情報
71回生_2年2学期_修学旅行
平成29年11月25日 グローバルリサーチⅡ FW「神戸コミュニティフォーラム プレイベント」
神戸サンボーホールにおいて、「災害弱者を救え」をテーマに研究している普通科グローバルリサーチⅡ受講生(2年)1班の4名が、神戸国際協力交流センター主催「神戸コミュニティフォーラム プレイベント」に参加しました。今回は「Creating a Resilient Kobe: How Can We Use The Talented People And Abundant Resources In Our Community To Make Kobe Healthy, Socially Connected, And Resilient For Everyone?(つよいまち神戸を創る:誰にとっても健康的で、つながりがあり、つよいまちにするために私たちになにが出来るか)」というテーマで、住民や神戸在住の外国人がおよそ80名が集まり議論しました。今回はプレイベントで、1月20日に久元神戸市長を迎えて本イベントが開催されます。
カテゴリー: グローバルリサーチ
平成29年11月25日 グローバルリサーチⅡ FW「神戸コミュニティフォーラム プレイベント」 はコメントを受け付けていません
平成29年11月25日 SGH全国高校生フォーラム
パシフィコ横浜において、文部科学省・筑波大学主催「2017年度スーパーグローバルハイスクール全国高校生フォーラム」が開催されました。全国のSGH、アソシエイト校から代表生徒が集まり課題研究の発表を英語で行いました。本校からは、「Social Participation of High School Students ―Comparison between Practical Education in Japan and Citizenship Education in the UK ―(高校生の社会参画について ―日本の実践型教育と英国のシティズンシップ教育の比較―)」というテーマで、創造科学科1期生(2年生)がポスター発表を行いました。
〈生徒の感想〉
SGH全国高校生フォーラムに参加し、悔しいという思いを抱きました。4月から研究をしてきた内容を初めて外部で発表する場だったのですが、4分という限られた時間の中で、英語で伝えることはとても困難でした。思うように内容を伝えられず、質疑応答も深い内容の話ではなく上辺だけの説明で終わってしまいました。更に、周りの学校は英語がとても上手で、劣等感さえ抱きました。しかしながら、他校の発表を見ていると、内容の濃さは大方負けていないのではないかと思いました。そこは自信に変えたいと思います。今回の経験から、研究というのは単に調べ、深く考え、論文を書くといった流れだけでなく、伝える力も非常に大切であることがわかりました。私にとってネックとなったのは、英語運用能力、プレゼンテーション能力の2つでした。特に英語で自分の言いたいことがうまく伝えられず、苦労しました。最終発表ではもっと使える英語を増やし、良いプレゼンテーションにできるよう努めます。九州から関東までさまざまなところから来た高校生と交流し、さまざまな方言が聞けて楽しかったです。
カテゴリー: SGH(学科1期生), 創造科学科1期生
平成29年11月25日 SGH全国高校生フォーラム はコメントを受け付けていません
平成29年11月25日 SCI-TECH RESEARCH FORUM 2017
関西学院大学神戸三田キャンパスにおいて、創造科学科2期生(1年)の自然科学分野2・4・5・7・8班が、関西学院大学理工学部主催「SCI-TECH RESERCH FORUM 2017」に参加し、ポスター発表を行いました。兵庫県内外の高校から課題研究に取り組んでいる生徒が集まり、現時点の研究の概要について説明を行いました。以下は各班の発表タイトルと生徒の感想です。
2班 丸嶋ゼミ「蛍光X線による成分の分析 ~楽器の表面にふくまれているものは?~」
<感 想> 今回、僕たちは関学で「蛍光X線による成分の分析」をテーマに発表した。楽器の表面のメッキ元素を調べることが目的だ。放射線を出すAmをクラリネットにあてることで発生する蛍光X線を分析し、クラリネットに含まれる元素を調べる実験だ。発表することで、大学生の人や大人の方、自分たちと同じ高校生、様々な方にアドバイスや意見を頂いた。今回は明るい部屋で実験をしたので、それでは発生するエネルギー量が正確に測れないのでは、AgとCuしかクラリネットには含まれていないのか、クラリネットに限らず他の楽器を分析してみては、など色々な意見があった。今回の発表で学んだことは2つある。1つは、何も知らない相手にでも、わかりやすく伝えること。2つ目は、多くの意見を頂いたように、ひとつのものでもたくさんの見方、捉え方があり、立体的に見ることが大切だということ。立体的に見るための多くの側面を見つけることが出来たのが今回の機会だったのだと思う。今回学んだことを、これからの研究に繋げていきたい。
4班 勇惣ゼミ「クレーターから探る月の歴史」
<感 想> 私たち4班は“クレーターから探る月の歴史”というテーマでポスターセッションしました。まず、はじめは緊張していたものの、リハーサルもあったおかげか、みんな落ち着いて話せていたことが良かったと思います。私自身、ちゃんと自分の言いたいことを話せるかな、途中で頭が真っ白になって止まってしまったらどうしよう、という心配をしていたのですが、話し出すとなんとか自分のパートを喋り切ることができました。また、他の人の発表を聞く時間も充実していたと感じています。私は1回目の自分の発表のあと反省をしていたので話はあまり聞けていないのですが、それでもひと通りポスターを見ることはできました。やはり1番印象に残っているのは最後まで聞けた“ゴキブリ”です。私が院生さんのプレゼンを聞いたあとはじめにやりたいと思っていた研究がこの数理生物学だったのですが、私だったらこんなにおもしろいテーマは設定できなかったんじゃないかな〜と感じました。私が最近やっと使い方を理解できてきたExcelを用いて発表をしている仲間の姿はかっこよく見え、結果をはやく知りたいと思わせてくれるような内容でした。他の高校生も様々な研究を行っていることがわかり、また、英語で発表している人もいて本当に感心させられる時間でした。今日学んだことはこれだけではありません。自分がやってきた研究について、見直していかなければならない点がたくさんありました。一つ目に発表のしかたです。1度目の発表で、大学生のときに月について研究をしていたという方・太陽について研究したあとJAXAに入り、今は関学の研究員をしているという方に質問をうけたのですが、イントロダクションと最後のまとめの関係性が分からない、とのことでした。私たちが思っていた研究目的とは違うように受け取られてしまっていたのです。自分達で作ったポスターであり、自分達は目的を理解していたために全く疑問に思わなかった所を突かれ、どう答えればいいか分からなくなりました。2度目の発表では説明を補ったものの、やはりこんな発表では相手にちゃんと伝えることができないのではないか、と思い悔しかったです。二つ目には、月についての知識不足です。予想していた質問の斜め上を行く質問を投げかけられ、全員が数秒の間黙ってしまう、ということがありました。これではダメだと感じています。もっともっと調べて院生さんに質問もして、これからの発表は自信を持って挑めるようにしていきたいです。詳しくお話を聞くことができた二人の方とは名刺を交換できたので、この出会いは大切にしたいと思っています。これからも頑張ります!
5班 冨田ゼミ「環境DNAによるアジの分布調査」
<感 想> 11月25日関西学院大学三田キャンパスで開催された、リサーチフォーラムに参加しました。社会科学の最終発表会が終わり、自然科学での最初の発表会の場であり、多くの大学生、先生方、高校生がいる中で発表をするのは少し緊張しました。しかし、今回のこのリサーチフォーラムで、今後の展望や、指針を決められるようなアドバイスをいただくことが出来ました。例えば、5班の環境DNAの研究については、調査期が限られていては、海流と環境DNAとの関係を結びつけるのは難しいのではないかということや、実験方法についてもネガティブコントロールと呼ばれる実験の正確性を確かめるために、水ではなく対象の魚に似たDNA配列を持つ魚の環境DNAを使った方がより良いのではないかなどです。今回ご指摘や、ご教授頂いたことは今後の実験活動や考察、展望を考える際頭に置いておくべきだなと感じました。色々な方に学ばせてもらった半日となりました。
7班 勝原ゼミ「ゴキブリの出没」
<感 想> 今回のポスター発表は、私たちの研究の一番最初の発表で、正直不安が大きかったです。前日までポスターも出来上がらなくて、不完全な部分もあったかもしれませんが、発表の時には首を伸ばしてまで聞きに来てくださる方もいて、とても嬉しかったです。その分、発表も頑張ろうと思えました。緊張もしましたがこんな機会はなかなかないのでとても良い経験になったし、この発表をしたことで自分自身、少し自信が持てるようになりました。発表を終えて見つかった課題もあり、兵庫高校の先生方を含めた多くの人から指摘を受けました。これらの指摘は私たちにとって、大切な第三者からの意見であるので、参考にしながらこれから研究を進めていこうと思います。
8班 中野ゼミ「X線で観測する宇宙」
<感 想> 私達の班は、赤色矮星が元となる超新星「ティコの超新星」の主成分をデータより推測するという内容の発表を行いました。神戸大学院生にサポートをして頂いたこともあり、何とか発表を行えるデータも揃えられたのですが、まだまだ知識が浅かったところもあり、今後の課題も見つかりました。現場では、活気のある質疑や指摘を頂き、より自分達の研究内容を深めることができました。今後、この場で見つかった課題を修正し、研究の精度を高めていきたいと思います。。
カテゴリー: SGH(学科2期生), 創造科学科2期生
平成29年11月25日 SCI-TECH RESEARCH FORUM 2017 はコメントを受け付けていません
平成29年11月24日 創造基礎B FW「柿の回収と質量測定」
神戸大学鶴甲第二キャンパスにおいて、「鳥と果実の関係性」をテーマに研究をしている創造科学科2期生(1年)自然科学分野3班が先日の神大実験実習で設置した柿の回収と鳥に食された柿の量を調べるための質量測定を行いました。日没までのわずかな時間で、設置した24個のすべての柿について、写真と地面からの高さのデータ採取を行いました。また、ご指導いただいている神大院生の邑上さんから、発表用ポスターの作り方や今後の研究方法について、アドバイスをいただくことができました。この実験データをもとに、鳥と果実の関係性に迫ります。
カテゴリー: SGH(学科2期生), 創造科学科2期生
平成29年11月24日 創造基礎B FW「柿の回収と質量測定」 はコメントを受け付けていません
平成29年11月24日 RRE「グループプレゼンテーション」
本校同窓会館ゆ~かり館において、本校創造科学科2期生(1年)がRREの授業で、パワーポイントを用いたプレゼンテーションを英語で行いました。2学期は、環境問題をテーマに、12月中旬に行われる外国人留学生との交流会に向け、原稿及びスライドの準備を進めてきました。今回のグループプレゼンテーションは交流会に向けての発表練習として、発表8分、質疑応答2分で行いました。
カテゴリー: SGH(学科2期生), 創造科学科2期生
平成29年11月24日 RRE「グループプレゼンテーション」 はコメントを受け付けていません
平成29年11月22日 創造応用ⅠS 探究活動(9回目)
<数学>
前回までの経験を元にして、各自の研究を進めていきました。記憶をテーマにした実験では実際に他のメンバーに実験に参加してもらうことで新たなデータを集めました。また、野球の球種のカウントをテーマにした研究では、実際にどのようなことを調べたいのかを突き詰めて、目的に合わせたデータの再整理を始めました。山登りと脈拍の関係について調べるテーマと、将棋の戦型についての勝敗を調べるテーマについては、データの数がある程度そろってきたところなので、知りたい情報をどのように分析していくのかの試行錯誤が始まっています。
<物理>
ダイラタント流体班は、使用しているダイラタント流体と同じ粘性の液体を準備し、それぞれの液体を滴下した際の現象を観察しました。水あめや、小麦粉などを用いた複数の液体を用意し比較実験をすることで、ダイラタント流体とほかの液体で起こる現象の違いを整理し、ダイラタント流体の特性を調べました。砂時計班は、引き続き、データの量を増やす一方、シリカゲルを砂時計と同様に落下させる実験を行いました。シリカゲルとは、乾燥剤として使用される物質で、水分を吸収する性質があります。そのシリカゲルの性質を利用し、徐々に含ませる水分量を増加させ、落下時間にどのような変化が起こるのか、実験を行いました。
<化学>
化学9回目の探究活動では、塩橋の抵抗が大きいために溶液抵抗が大きくなっているところを改善するため、新たに塩橋を作成するとともに、ペットボトルを用いて抵抗の小さい電池を考え、実際に溶液抵抗が小さく、0.2 Vの起電力が取れることを確認できました。今後は、さらに溶液抵抗を小さくする工夫をしながら、できる限り大きな起電力を得られる泥を見つけ出し、経済的でかつ効率の良い泥電池の作成を目指すことになりました。
<生物>
本校生物教室において、グリーンヒドラの採食行動を観察、捕食時の触手の反応時間を測定しました。餌となるアルテミアを与えた場合と、アルテミアを与えずにグルタチオン溶液(0, 10, 50, 100, 200 μMの各濃度)中での触手の収縮反応をスマホ顕微鏡で観察、撮影しました。反応時間の数値化と考察は、後日に行うことになりました。
<都市工学>
本校PC教室で実施。先週入力をし忘れていた、印象評価実験に用いた写真セット11枚に対し、順位付けを被験者にしてもらっていたデータをデジタル化する作業から開始しました。
カテゴリー: SGH(学科1期生), 創造科学科1期生
平成29年11月22日 創造応用ⅠS 探究活動(9回目) はコメントを受け付けていません