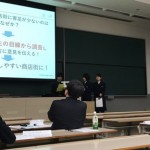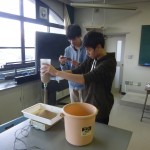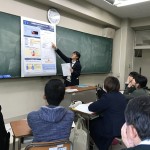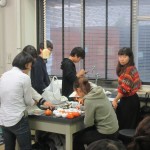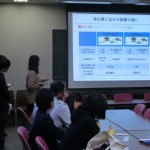神戸大学大学院人間発達環境学部において、創造科学科2期生(1年)の生徒40名が、各ゼミの大学院生の指導のもとで実験実習を行いました。高校では使用することができない実験機具を使ったり、専門的な内容について半日かけて学習しました。以下は生徒の感想です。
1班 長濱ゼミ「テーピングに含まれる物質について」


〈生徒の感想〉
今日は、大学においてある機材を使って実際にテーピングを測定しました。赤外線分光法の中でも全反射法というものを使いました。今まで化学の授業でやってきた内容からさらに進化した内容で、知らないことが多くあり面白かったです。また、ただ研究をするだけでなく研究をするにあたってのどういうところに気をつけたらいいかや発表についてのアドバイスもくださり、とても勉強になりました。実際に研究では機材にテーピングを置いて、抑えつける。測定が終わればその台をエタノールで拭く。という極めて単純な作業でしたが、そこから得られたデータは見たことのないもので、このデータを読み取って処理して行くと考えると自分たちできちんとできるか不安になりました。ここから先は、自分たちでデータをきちんとした形にしてそれを実践的に使えるようにして行くことが最終目的なので、そこまでたどり着けるよう残りの研究を頑張っていきます。
2班 丸嶋ゼミ「身の回りの物質を構成する原子を放射線で観測する」


〈生徒の感想〉
私達2班は神戸大学発達科学部にて、蛍光X線による、楽器に含まれる原子の分析をし、楽器はどんな成分でできているかについての実験をしました。今回、実験に使われた楽器は、班員が持ってきたクラリネットで、まずは、アメリシウム241という入射X線をクラリネットの、表面にあて、そこで反射した蛍光X線を電子の流れとして、半導体検出器でとられ、そのX線の最大値を、Excelで統計をして、グラフで表し、アトレース一つに対して、エネルギーがただ一つに決まるため、y=ax+bの形の式で、エネルギーの値を求めた。表を参考に、求め出したエネルギーの値と一番近い値を探し、成分を推測することができた。ほかにもまた何個かの楽器が神戸大学の実験室で、x線にあてられています。それらのデータをこれから分析する時に、より正確な結果になるように、みんなで頑張っていきたいと思います。
3班 邑上ゼミ「鳥と果実の関係性について」

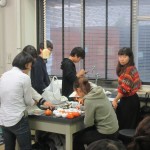
〈生徒の感想〉今回は柿の計測・設置を行いました。前日にオレンジ・茶・白の三色に塗ったものと処理していないもの(コントロール)を神大に持っていきました。計測では、糖度・質量・大きさ・色を調べました。糖度は神大にある糖度計を用いて、コントロールのみを測りました。その際、同じ種類の柿なのに違いが4つ以上あり驚きました。また、質量では測りを用いて調べました。大きさはノギスという定規のような道具を使って調べました。普段見る定規とは違い、デジタルで測れたりサムローラーが付いていたりして、柿の大きさが細かいところまで測ることができました。色は色彩見本を使いました。柿は場所によって色がまばらなので鳥から見た柿、つまり上から見た色で決めました。計測が手際良くできたので、本来はできなかったはずの大きさまで測定する事ができたました。また、色を塗った柿の絵の具が多少はげていたので、そこを工夫できればなお良かったと思います。柿の設置では、1つの木に低い・高いの2つに柿を分けて、設置しました。設置後、インターバルカメラを設置しました。暗くなる前に全ての作業を終わらせることができましたが、低い・高いの柿の高低差があまりなかったことが反省点です。
4班 勇惣ゼミ「クレーターから探る月の歴史」


〈生徒の感想〉
今日はまず月についてと、勇惣さんの研究内容のお話を聞いた後、実際にクレーターカウンティングをしました。講義では前回の観察で使用した器具の詳しい説明やジャイアントインパクト説や、湯惣さんの研究内容で聞いたこともないような細かい話を聞くことができました。その中で湯惣さんの「月についての研究はひたすらパソコンの前での狭い作業だけど考えていることは1番大きい」という言葉が心に残りました。そして、私が特に印象に残っているのは望遠鏡を宇宙に作るメリットと地上に作るメリットについてです。今までそのようなことを考えたこともなかったので、全然思いつきませんでした。でも、お話を聞いて違いが分かったし、そのような根本的なことから疑問を持つことが大切なのだと実感しました。クレーターカウンティングはただただクレーターを数え続けるという地道な作業でした。しかし、実際にやってみると想像以上に楽しかったです。同じ面積を数えても場所によってクレーターの数は全然違っていて驚きでした。今日は一時間ちょっと数えたけれど、それでもほんの一部だったのでほかの場所も数えてみたいと思いました。クレーターカウンティングを通して、湯惣さんが、研究者が華々しい研究の発表をしている裏では地道な作業を積み重ねていると言っていたように、研究者の方はこのような作業を何度も何度も繰り返していて本当に素晴らしいなぁと思いました。次からは今回のカウンティングを考察してクレーターが形成された年代や場所による数の比較などさらに細かいところまで踏み込んでいきます。
5班 冨田ゼミ「環境DNAを用いたアジの分布調査」


〈生徒の感想〉
5班では環境DNAを用いたアジの分布について研究している。そして今回神戸大学に行き、事前に淡路・須磨のそれぞれの3地点で採取した海水に含まれているアジのDNAがどれくらい含まれているのかを調べた。まず、事前にろ過・DNAを抽出していただいた海水をマイクロピペットで分けていく作業から始めた。個人的には細かい作業で少し難しく感じた。その後PCRというDNAを増幅させる技術を用いて、アジのDNAが各試料水に含まれているのかどうかを確認した。含まれているものも、いないものもあることが確認でき、それらにどのような関係があるのか、これから詳しく調べていきたい。また、対数を用いて含まれているDNAの量も計算し、アジの生態や海流などから分布・およその生息数についても考察していきたいと思う。
6班 高島ゼミ「環境DNAを用いた外来プラナリアの分布調査」


〈生徒の感想〉
僕達6班は環境DNAの抽出実験を行いました。PCR実験や、電気泳動など、専門的な機械を使って、作業をさせていただいて、とても貴重な経験をすることができたし、実験のしんどさや大変さを知ることが出来ました。大学院生の方々が丁寧に説明してくださったので、しっかりと取り組むことが出来ました。実験自体はうまくいかなかったので、後日高島さんがもう一度試して、結果を送っていただくことになりました。今回このような実験を行った目的や背景を改めて考え、後日送られる結果をもとに、これから考察していく予定です。
7班 勝原ゼミ「ゴキブリの出没」


〈生徒の感想〉
今日は式の説明を受けて、活動のゴールを決めることをした。コンバットとバルサンの性能を評価し、比べることと、マンションと一軒家におけるゴキブリの侵入率の高さを比べることをゴールとした。今日教えていただいた式はとても難しく、理解するのが大変だったが、丁寧に説明していただいたおかげでほかの人に説明できる程度までは理解できた。どうやって他の人に短時間でわかりやすく説明するかが鍵なので、よく考えて発表まで行けるようにしたい。
8班 中野ゼミ「星の観測」


〈生徒の感想〉
今日は、神戸大学でフィールドワークを行いました。行く前までは、テーマについてもまだあやふやなところがありましたが、今日は詳しく聞くことができました。最初に、望遠鏡の種類についての話を聞きました。それぞれの利点などを学ぶことができました。次に、星の直径をソフトを使って図ったり、超新星爆発のかけらの速さを求めたりしました。三角比などこの前習ったようなことで計算できることが驚きでした。最後に、グラフを使って爆発のかけらに含まれる元素を求めるという作業をしました。簡単な公式を使って求めることができました。前までは、全然理解できていませんでしたが、分かりやすく教えていただいたので理解を深めることができました。今回のことを活用して今度の関学での発表に向けてポスターを作っていきたいと思いました。