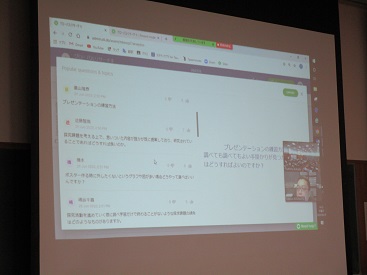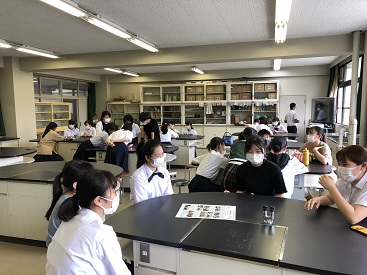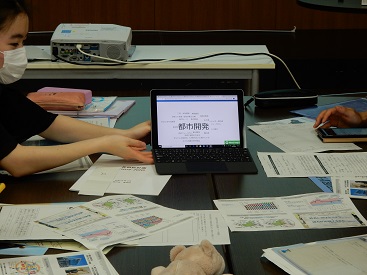各HR教室において、普通科74回生(2年1~7組)が6月15日から7月13日までの月曜6限(計5日間)、各テーマに分かれて新聞ワークに取り組んだ。各日の取り組み内容は以下の通りである。
6/15 新聞ワークの取り組み方についての説明、新聞ワーク1回目(ワークシート①の記入)
6/22 班内での新聞ワーク用ワークシートの回し読みの仕方の説明、前回のワークシート①の回し読みをし、ふりかえりシート①に記入。
6/29 新聞ワーク2回目(ワークシート②の記入)
7/6 前回のワークシート②を回し読みし、ふりかえりシート②の記入。今回ワークシート作成者にふりかえりシートに書いた内容を伝えるべくコメントシートの記入も追加(ふりかえりシートの内容を転記)。さらに、班内で回し読みした記事の感想を1人1分程度で発表し、班ごとにベストレポートを選出。
7/13 新聞ワーク3回目(ワークシート③の記入)。その後作成したワークシート③を回し 読みし、ふりかえりシート③の記入。コメントシートの交換。
テーマ
A:貧困と飢餓 B:健康と福祉 C:教育とジェンダー平等 D:水 E:エネルギー F:持続可能な経済 G:まちづくり H:自然環境 I:平和 J:パートナーシップ