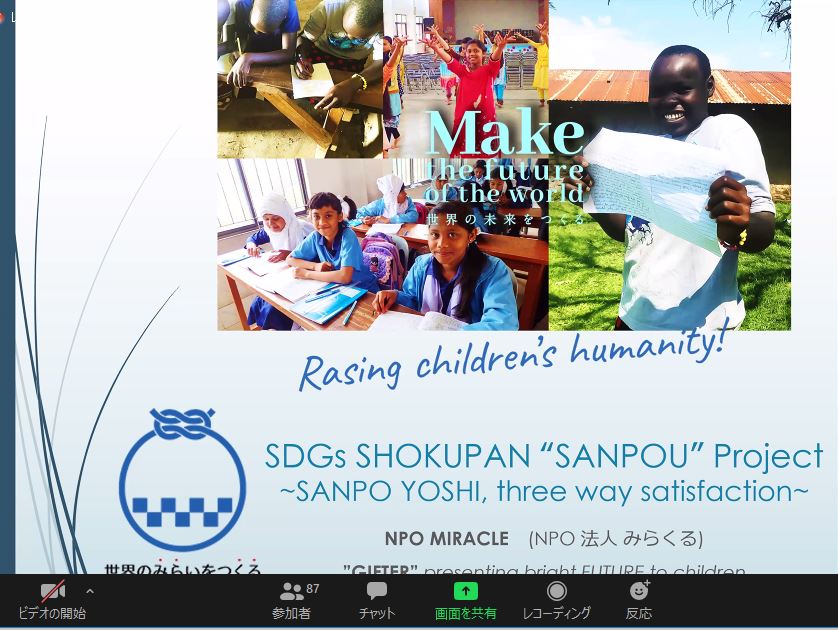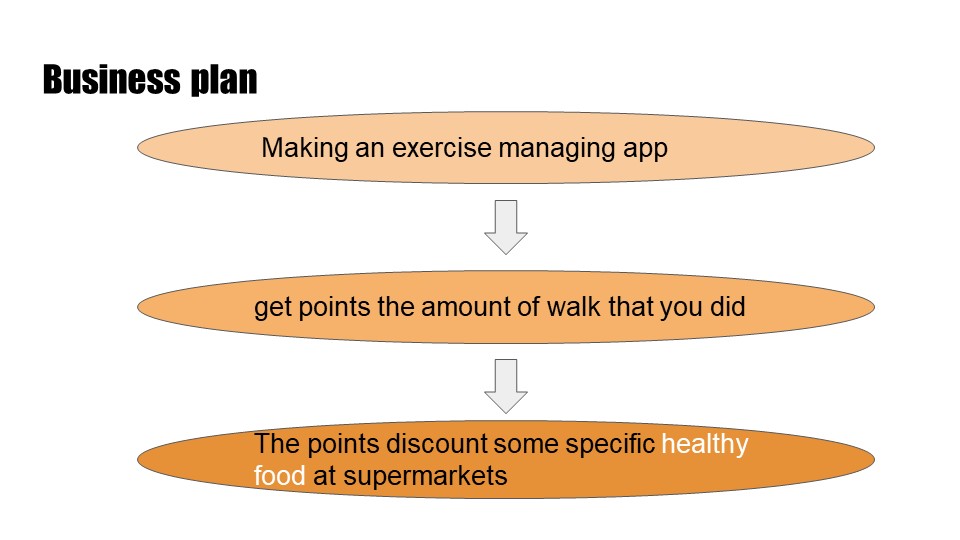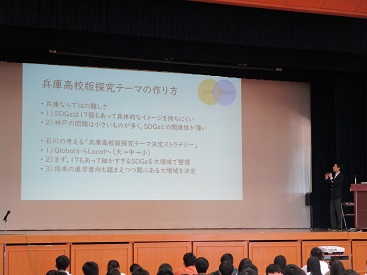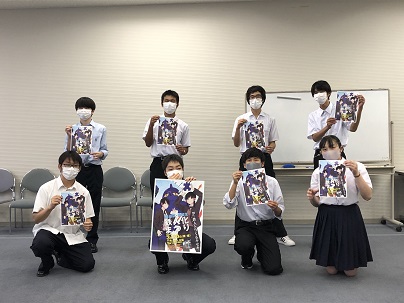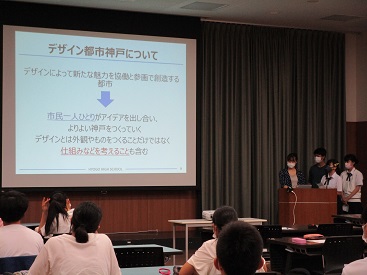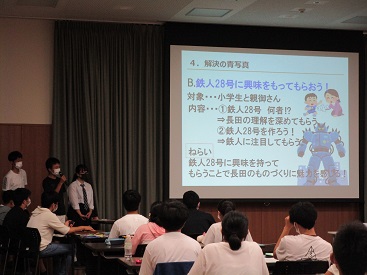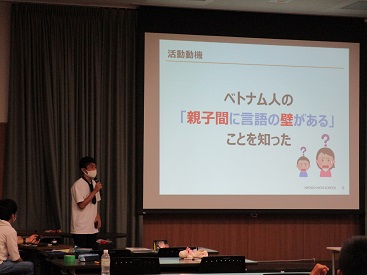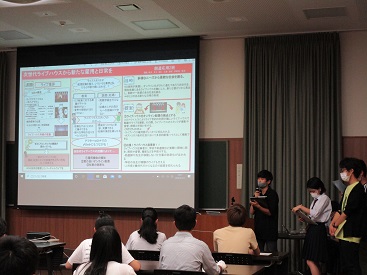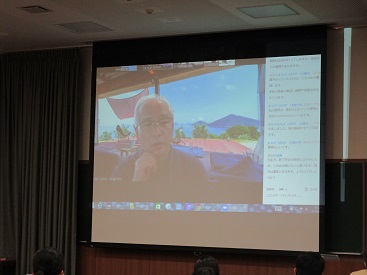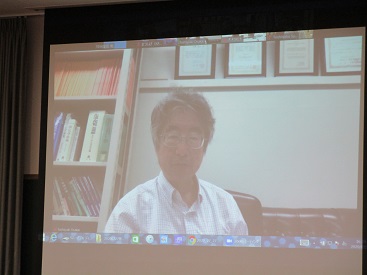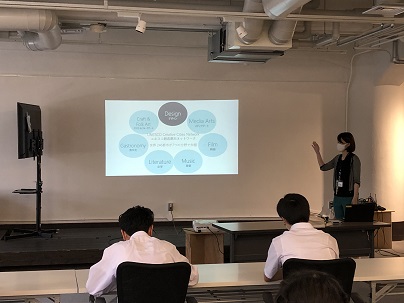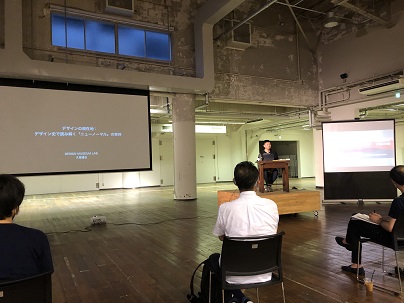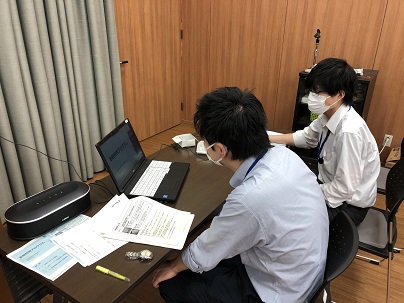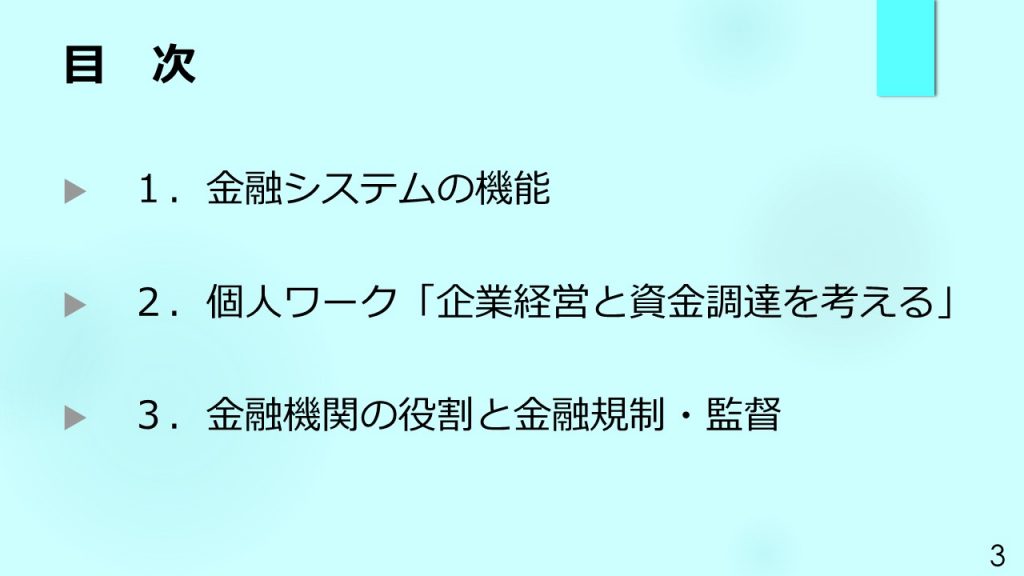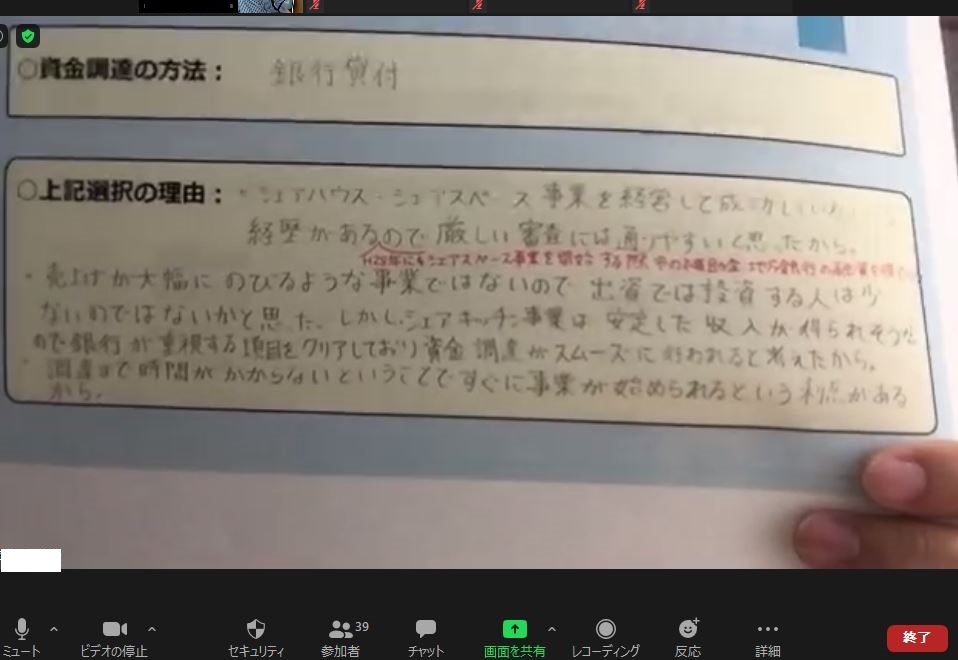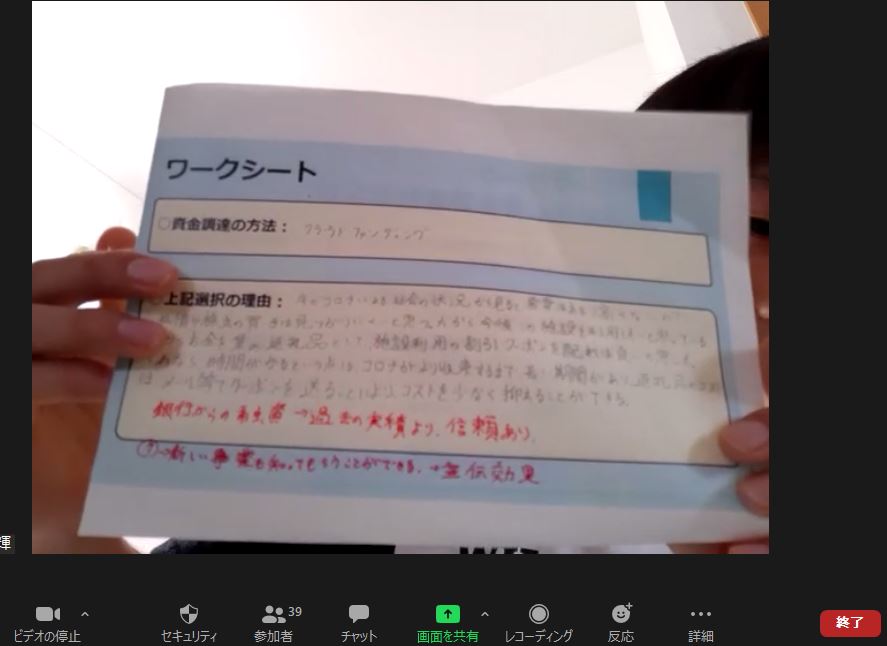長田区役所702会議室において、第10回高校生鉄人化まつりのふりかえりを行った。本校から創造科学科4期生5名、神戸野田高校生徒会3名が参加した(育英高校生徒会は欠席)。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、本まつりは中止となった。また、緊急事態宣言にともなう休校措置によりふりかえりも延期となっていた。今回、まつりの準備を通して、どのような学びがあったのかや、これからにどう役立てたいかについて各自が話した。
〈生徒感想〉
去年の秋頃からずっと準備してきたことが新型コロナウイルスという不測の事態によって水の泡になってしまったことは非常に悔しいです。しかしその中で、人と人のつながりの大切さや、私たち人類がウイルスという見えない敵に対してどれほど無力であるかも学ぶことができました。もちろん、悔しかったが学ぶことがあったという結論だけで綺麗事にして終わらせるつもりは全くありません。私たち実行委員には鉄人化まつりがこのまま廃れてしまわないように次の世代にどうにかして引き継いでいく必要があります。感染防止対策をとることやソーシャルディスタンスを保つことなど様々な制約がありますがその中でできることを「新しい様式の新しいまつり」として開催したいと思います。10年前、鉄人化まつりが始まったのは本校の先輩の提案がきっかけだと聞きました。今回新型コロナウイルスの感染拡大の影響で鉄人化まつりが中止になったのは、10年という節目に与えられた試練なのではないかと思います。新しい形でまつりを発展することができるのかは私たちの手にかかっています。先輩方から引き継いだ伝統を来年以降に繋げられるように、そして私たちの活動が少しでも社会に良い影響与えられるように頑張りたいと思います。
一から祭りを自分たちの手で作るということがとても難しく感じました。自分自身で長田を盛り上げるという目的を持って取り組みましたが、やはり自分自身で考えて発言し、兵庫高校以外の人たちとコミュニケーションをとっていくということも、企画を考えていかことも初めての経験でいい経験になったのではないかと思います。ここまで考えたにもかかわらず、この鉄人化祭りを実行することができず本当に残念な思いを感じるとともにやりきれなさがあり悔しいです。しかし、自分たちが行動してきたことは経験として自分にしっかりと残っています。この経験を生かして次に次にとどんどん歩んでいけたらいいと思います。
今回鉄人化祭りの企画に携ったわけですが、とても楽しく活動することが出来ました。自分たちのふざけたアイデアを実現の可能性と擦り合わせて少しずつ形にしていく活動は特に面白かったですし、そういったふざけたものが思いの外良い形におさまるという経験は今後にも活きていきそうです。残念ながら今回の第10回鉄人化祭りは中止という形で幕を閉じました。企画の段階でものすごく楽しかっただけに、本番を経験できなかったことはすごく残念で、大きな心残りがありますが、それもまた貴重な体験として得るものは大きかったと思います。
そして、来る(?)第10.1回鉄人化祭りでは、鉄人スクエアのマス目を活かして、コロナ禍で制限されている中でギネスのようななにか大きな記録を打ち立てればと思います。総参加型で、世の中が暗い雰囲気な今、多くの人の手でひとつのものをつくりあげることで人間の文化的活動やその意欲がコロナなんぞに負けないということを示せれば、それは大きな意義になるのでは、と勝手ながらワクワクしています。
第10回高校生鉄人化祭りの振り返りを長田区役所で行った。蜜回避のために今までとは座席配置も変え、少し変な気分だった。会議では皆一人ずつ感想を言い合った。皆、祭りができなかったことは悲しく、今まで努力してきたにもかかわらずこんなにそっけなくなるのは悔しい気持ちもあるが、この委員会で様々なことを学べたと思う、という内容だった。その後に、窪田先生から、新たな提案をするという案をいただき、
鉄人化祭りがなくなったことはとても悲しいが、これから新しいことの企画ができると聞いてとてもワクワクしている。兵庫高校でその案を夏季休業中に考え、提出することにしたい。部活動に協力していただいて祭りらしいことをする案や、新しいギネス記録に挑戦する案など、とても面白そうな案がたくさん出た。これからさらに案を練っていく予定だ。第10回高校生鉄人化祭りにご協力いただいた、鉄人プロジェクトや長田区役所、育英高校、野田高校、兵庫高校の先生方、出演予定でした各部活動の方々、本の回収等に快く協力していただいた方々に本当に感謝申し上げます。ありがとうございました。
新型コロナウイルスにより中止になってしまった鉄人化祭り。本当に悲しいし、悔しいです。みんなで何時間もかけて話し合い、そして多くの人の協力の元で計画されていたお祭りがなくなるなんて思いもよりませんでした。しかし、育英や野田の生徒会との話し合いの中でたくさんの刺激を貰ったり、そして、イベントを作る難しさや裏側を知れて本当に良い機会になりました。この学びを今後の活動や生活にも活かしたいと心強く思います。しかし、まだチャンスは無いわけではないので、コロナウイルスで様々な制限がある新しい社会における新しい祭りを、みんなでこれから相談出来たらなと思います。