本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、未来創造コース2期生(1年生)対象に、創造基礎Aの授業で「模擬投票」を実施しました。長田区選挙管理委員会から記載台と投票箱、模擬投票用紙をお借りし、模擬投票所を設置しました。まず、「くらしの中の選挙2」のDVDから1)投票の原則、2)投票所について学習しました。次に、投票所の係を役割分担し模擬投票を行いました。そして、DVDから3)投票方式、4)投票の記載事項と当選人の決定)を学び、最後にふりかえりを行いました。今回の模擬選挙(全4時)のしめくくりとして、創造基礎Bの地域課題解決活動を通して、「政治」に対する期待や「主権者としての責任」を果たす準備について考えました。以下は生徒の感想です。
私が投票した政党の決め手は、国民のことを身近に考えた政策だったから。また、地域を中心とした政策だったので好感が持てたからだ。政策が具体的だったので分かりやすかった。実際に模擬投票に参加してみて、意外に細かいルールがあることを知った。また、選挙が公正に行われるように多くの人が関わっていることが分かった。選挙演説では、政党ごとに反対していること、推進していることがあり、特に集団的自衛権に関しては賛成、反対がはっきり分かれていて、おもしろいと感じた。具体的な政策が示されていない政党が多く、国民に伝わりにくい部分がたくさんあったので、直したほうがよいと思う。
私が投票した政党は、奨学金をできるだけ負担するという政策が素晴らしいと感じました。以前からお金が無いという理由だけで学校に行きたくても行けないというのは不平等なのではないかと思っていました。だからもっと奨学金を増やすことでより多くの子どもたちを救ってくれそうな奨学金を負担する次世代の党に投票しました。授業に参加をして多くの人の監視下で投票する本番では、もっと緊張感があるのだろうなと感じました。また、最初に箱が空であることを確認したり、順番に行ったり、ここまで徹底的に不正がないようにしているのかと驚きました。
今の政権に反対しているだけの政党は具体性に欠けていて、実際に何をしたいかがよくわからなかったが、選んだ政党は具体的な政策がわかった。また、具体的なプロセスも分かったので現実味が感じられた。母の投票について行ったことはあるけれど、実際にするのは初めてで、模擬だけど本当に投票用紙が折っても元に戻ることや、横が全く見えないと分かり感動した。選んだ政党については、外交政策で拉致問題や移民の抑制について言っていたので良いと思った。特に移民は今ヨーロッパで問題になっているので気になっている。また、奨学金がより手厚くなれば良い学習を受けられる人が増え日本の社会に貢献できる人も増えるのではないかと感じた。他の政党で上がった軽減税率も良いと感じたけれど、日本は国民が多いから導入が大変そうだと思った。
発表が上手かどうかではなく、内容のみで判断しました。具体的な政策、大まかな政策共に、現状の否定のみでなく独自の着地点を見出し、あるいは模索しているように感じました。また、具体的な政策について、比較的庶民を意識した内容が多いように感じたことも決め手になりました。授業に参加して感じたのは「投票の際にもっと判断基準がほしい」ということです。今回は党の掲げる政策のみに焦点があてられていましたが、実際は政党内での派閥や候補者の人格、過去の言動、党の政策実行力や党と企業のつながりなど、判断すべき内容はたくさんあるわけです。18歳以上から投票可能となることを見越した授業にしては、あまりにも情報が絞られており、本番では情報に振り回されないか心配になりました。
私たちが過ごしやすい世界にするには、私たち自身が積極的に動くことが大切だということが分かりました。立候補者になって、改革を行うのもいいですが、有権者として、立候補者を選ぶことでも政治に関わることはできます。自分なりの関わり方で政治に関わり、今の世界も未来の世界もすべての人が過ごしやすい世界を作っていきたいと思いました。すべての人が過ごしやすい世界にするために国民1人1人の意見を大切にした政治が行われてほしいと思いました。




地域にもっとやさしい政策、住んでいる人の意見が取り入れられるような仕組みが必要だと感じました。国の選挙では国を動かす人を選びますが、その前にできる小さなことがあると思います。まず、地域のつながりを強くすること。強くすればいろんな人の意見が取り入れられると思うし、地域単位で動きやすくなると思います。次に地域を強くすること。少子高齢化が進んでいるので、産業も衰えていると思います。地域の特色を生かしたものが進めば強くなると思います。「政治」に期待するということは自分も参加してみんなで参加することが大事だと思います。
何をすれば地域が発展するかということに正解はないので、立候補する人は何をすれば地域がより発展するかをよく考え、それを地域の人々に伝え自分が何をしてどうしたいのかを理解してもらうことが大切だと思った。投票する人は、自分の地域の特長や問題などをよく知っておきそれを踏まえてどうすれば地域が良くなるかを考えることによってもっと活発な政治が行われるのではないかと思う。現在の政治はとりあえず席を無理やり獲得してから動くという形になりつつあるので、もっと正しい政治となっていけることを願っている。
解決が難しいそうな課題が地域にはたくさんありますが、それらを見逃さず、しっかりと向き合っていくべきだと考えます。課題の解決を急にするのが無理でも住民の意見をちゃんと取り入れた取り組みをしてほしいです。そのためにはやはり自分たちが地域の課題を知り、主体的に考え、意見することが必要だと思いました。地域に住むひとりひとりを混きこんだ政治ができたら素晴らしいと思います。
各党の詳しい政策を知り、それが自分の意見と合っているかどうかを考えていくべきだと思いました。周りの人達の意見にながされず、自分の意見を主張できることも大切だと思います。テレビやマスコミは自分たちに都合のいい情報しか流していないかもしれないので、情報を見極める力も大切だと感じました。決して私たちの1票は軽くないので、1票の重さを知り、投票するべきだと思います。
1つ1つの政党の政策をちゃんと知る必要があると思います。今は与党が強い力を持っており、国民の中にも政策を知らずに知名度で書いている人が多いと思います。それではただの人気投票で、政治に参加しているといえないと思います。だからこそ政策や横領を調べて自分の意見に合った党を選ぶべきです。それらをする上でよい政策があるのに選ばれていなかったり、選ばれていることに不思議に思うことがあるかもしれません。しかしそれには理由がちゃんとあると思います。そのためしっかりと考えなければなりません。情報を集めるにはインターネットや、テレビなどのメディアから集めることが基本になってくると思います。それらの情報を見極める力も必要になってくると思います。ちゃんと勉強して責任を果たしたいです。
自分はこの授業を受けるまでどの党がどんな政策をしているのか、ほとんど知らなかったし、特に気にもならなかった。でもよく考えるとあと2年すれば自分も有権者となり、大人たちと同じ権利を得る。今の段階でこの党はダメだなどいうことはわからないから、まずはニュースや新聞を読む習慣をつけて社会に目を向けたいと思う。
自分には関係ないとばかり思わないようにしたいです。政治とか授業で少しやったりしたけど全然わからないし、投票もめんどくさいなと思っていたけど、それではダメだなと思いました。自分の1票がどれだけ大切か考えるようにしたいです。まずは、なぜ選挙権を18歳に引き下げたのかから知りたいです。そして2年後の18歳にそなえようと思います。




















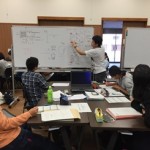



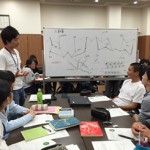








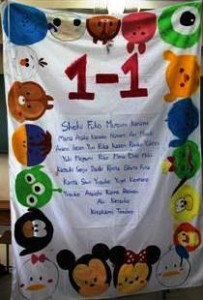


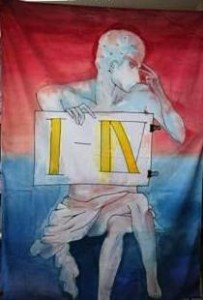


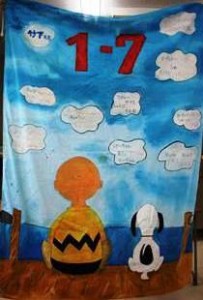

 朝食
朝食 集合
集合









































 ラジオ体操で始まる朝
ラジオ体操で始まる朝 朝食
朝食 バスで登山口へ
バスで登山口へ Daisen!
Daisen! 到着!
到着! いざ!
いざ!

















































