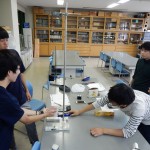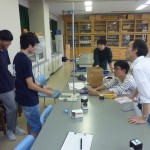創造科学科2期生(2年)理系選択者は各班に分かれて研究活動をおこなった。
<数学>
本日は、「検定の考え方」について稲葉教授の講義を受け、学習した。前々回の授業の続きで、「検出力を高めるためにはどうすればよいか」という内容を扱い、仮説検定に関して理解を深めた。ランダマイズテストの考え方など、生徒にとって理解しにくい内容ということもあり、演習では苦戦している様子だった。しかし、統計を扱う上で必要な知識なので、一生懸命取り組む姿勢がみられた。



<物理>
大阪大学の大学院生に来ていただき、アドバイスをいただきながら物理教室で探求活動を行った。
「摩擦力ゼロ班」では、物体の速さを測定する必要があるので、まず速さを測定する装置の精度を調べた。物体の自由落下を利用し、速さ測定器に表示される数値と理論計算から求められる数値を比較して、いくつかある測定器の中で精度のよいものを実験に使用することにした。
「足裏圧力班」では、実験に使用する紙粘土の上に重さの異なるおもりを順番に乗せていき、紙粘土のくぼみの深さを測定し、重さと深さの関係をグラフ化した。そして、おもりの重さと窪みの深さの間には比例関係があるとして仮定し定式化した。
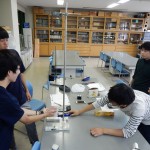
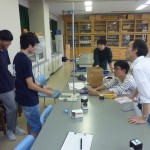

<化学>
化学の探究活動4回目は、先週作成した泥を用いて、実際に起電力の測定を行った。今回は、発酵しやすさに目を向け、納豆、味噌を含む泥を燃料にして実験を行った。結果的には、納豆よりも味噌を入れた泥のほうが高い起電力が得られ、それぞれの食品と泥の割合も変えて計測すると、変化がみられることもわかってきた。しかし、昨年同様、測定値がかなり不安定で再現性があまりないと考えられ、今後の課題も大きく残った。次回は、大堺先生に指導していただく予定である。



<生物>
今回も引き続き原生生物を利用した実験をするに当たり、自身の興味の持てる研究内容を調べる活動を行った。特に、原生生物とはどのような生物か、それらを利用した実験はどのようなものがあるのかを調べ、勉強した。次回からは、やりたい実験のプレゼンテーションを作成するため、パワーポイントを使用していきたい。



<都市工学>
都市工学班は、澤木先生のご指導の下、チームに分かれて目的と進め方を議論した。チームAの景観研究は、アニメとそのもとになった現実の場所を具体的にあげるなかで、高校生目線で「美しい景観」に関しての仮説を想定しながら選定した。関西地区を中心に実際に足を運ぶ計画も今後立てて実行する予定だ。印象評価実験を11月に行う準備も並行して進めることにする。一方、チームBの集団ねぐら研究は、先日の名谷のフィールドワークの結果をもとに、その場における建物や道路の幅、木々の様子など、空間特性と集団ねぐらの関係を調べていくことが必要となった。西神中央や大阪の各地域など調査数を増やす中で環境要因の共通因子を見出すことが大切になってくるようだ。次回以降、いずれのチームも進め方を確定し、フィールドワークなども順次行っていく予定である。