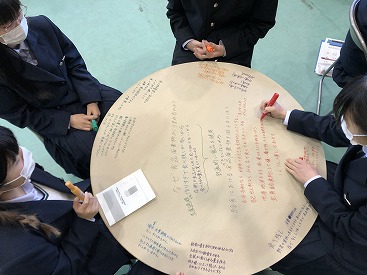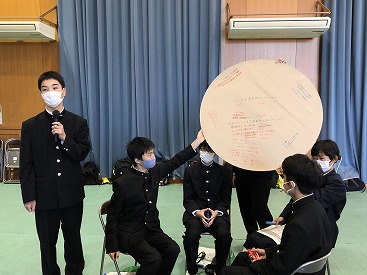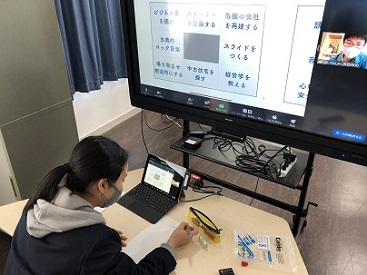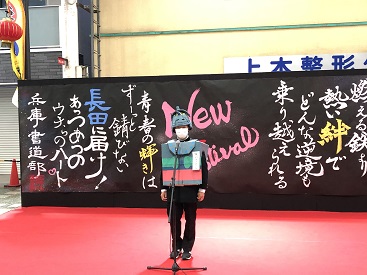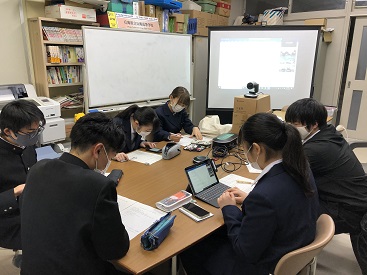本校講堂において、本校創造科学科5期生(2年)が創造科学科6期生(1年)を対象に、新入生オリエンテーションを行った。初めに、学校設定教科「創造」のうち、「創造基礎A」「創造基礎B」「RRE」について概要を説明した。次にアイスブレイクのために、自己紹介ゲームやビンゴをして雰囲気づくりをして、名刺交換の練習を行った。続いて、ワークショップ「フードロスを減らすには?」を行い、1年4人組に2年1名がファシリテーターとして参加し、「えんたくん」を活用しながら議論した。フードロスに関連する問題の広がりと絞り込みをして、議論した内容についてワールドカフェ形式で他班と共有した。最後に、「給食の残飯を減らすには?」というテーマで同様に議論し、各班の代表者が発表を行った。入学間もない1年生に対して、創造科学科で必要なエッセンスを詰め込んで伝えることができた。
-
最近の投稿
最近のコメント
アーカイブ
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年7月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年9月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年1月
- 2012年9月
- 2012年6月
- 2011年12月
カテゴリー
メタ情報