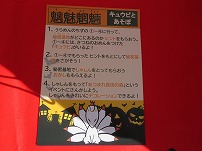本校において、創造科学科6期生(2年生)の理系生徒(26名)が創造応用Iの授業で、数学/物理/化学/生物/都市工学の5分野での七回目の探究活動を行った。
数学班は前回、神戸大学の稲葉先生からいただいた助言をもとに、実際にデータの収集を開始した。人気漫画を統計学的に研究するなど身近で興味をひく内容でデータを収集、分析を行っていく。
物理班は、プロペラの形状による涼しさの違いを研究しているグループは、様々な扇風機を用いた送風による水の温度変化について実験を行った。液状化現象について研究を行っている研究グループは、液状化現象を再現するための模型の作成に取り組んだ。
化学班は、前回までに作製した消臭機能を持たせたバイオプラスチックの消臭効果を検証するために容器内のアンモニア濃度の測定方法について実験を繰り返した。測定できる濃度範囲が限られているため、容器内の濃度をその範囲に保つ条件を細かく調べた。
生物班は「長田神社」、「神鉄長田駅」、「高速長田駅」、「新湊川周辺」と調査範囲を広げ、ハトの分布調査を行うとともに次回の中間報告会に向けてスライド作成を行った。授業時間内だけでなく登校前にも調査を行うなど、時間や立地によるハトの分布を調べそこから人間生活とハトの分布の関りについても調べていく。
都市工学班は、PCのソフト「Cities」を用いて研究対象都市の作成を開始した。現実に存在する都市をできるだけ忠実に再現し、そこで交通手段の違いが環境負荷にどのような影響を及ぼすのかを検証していく。