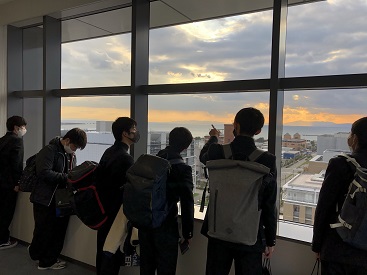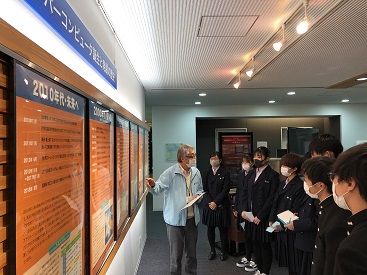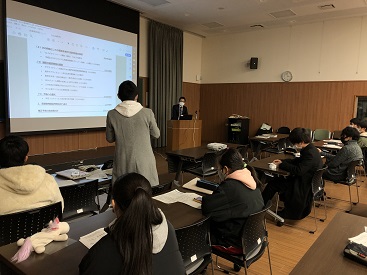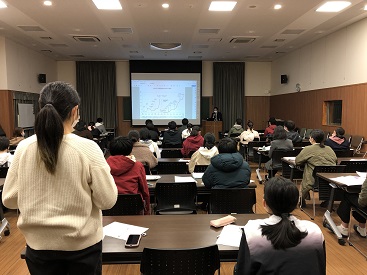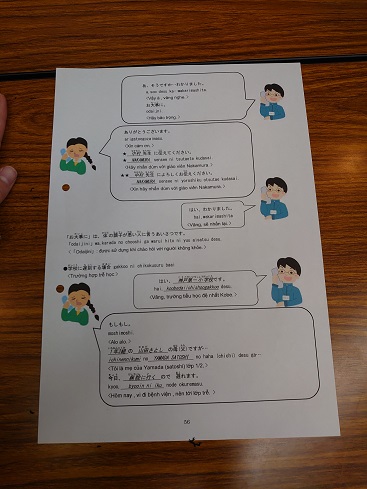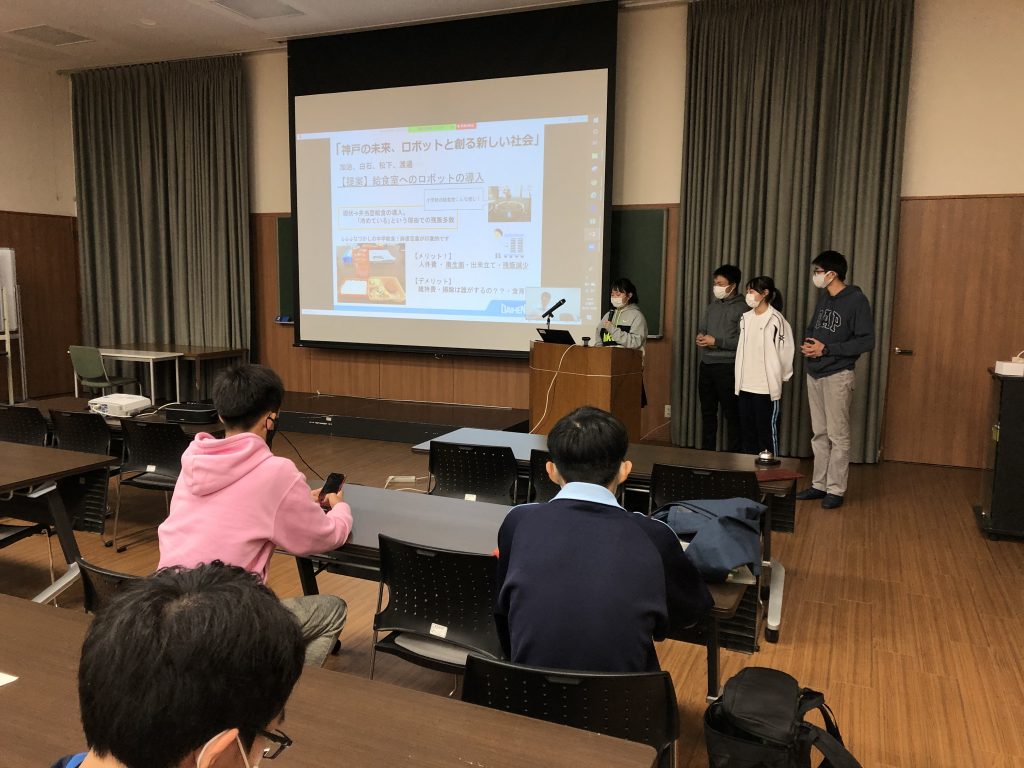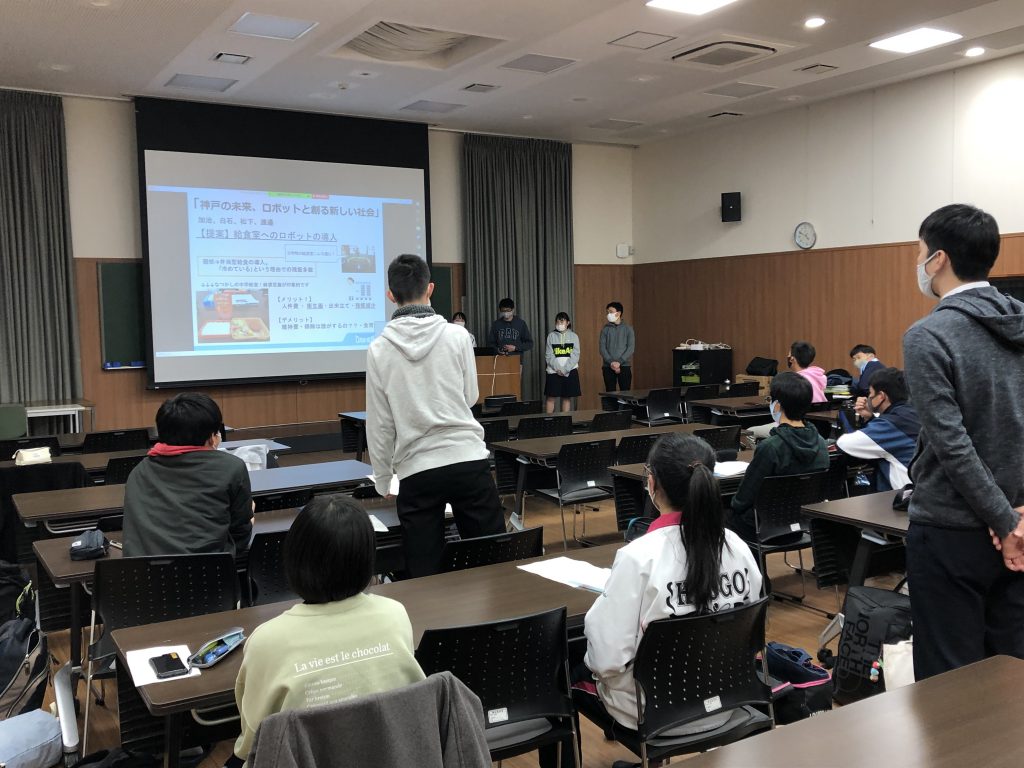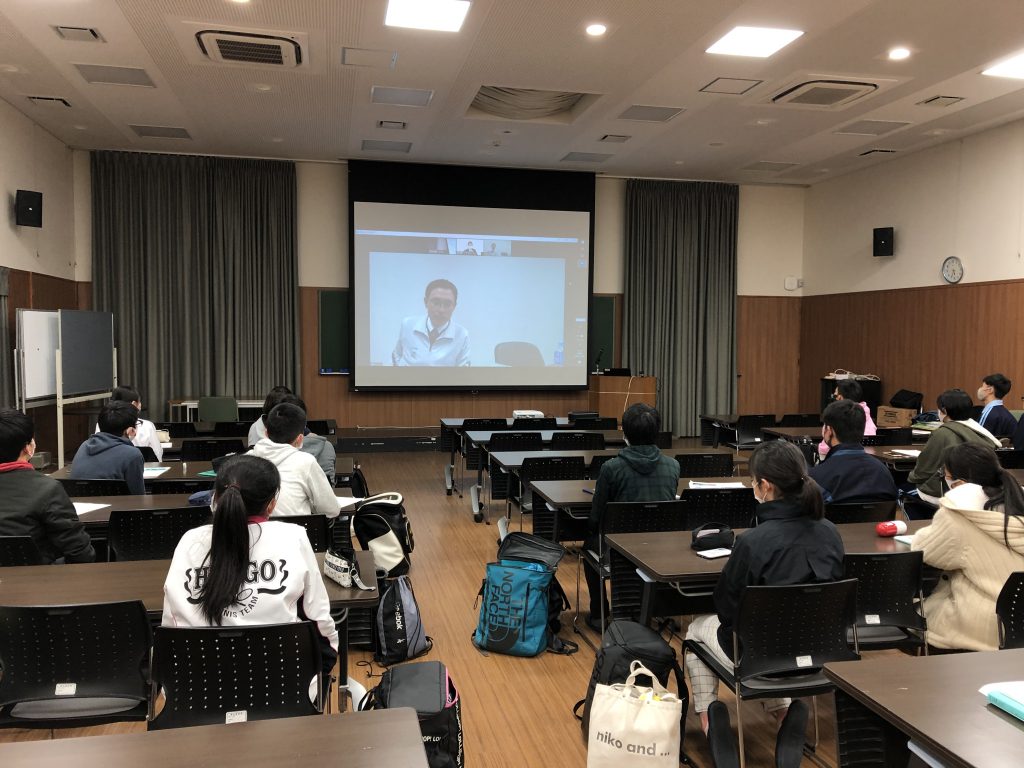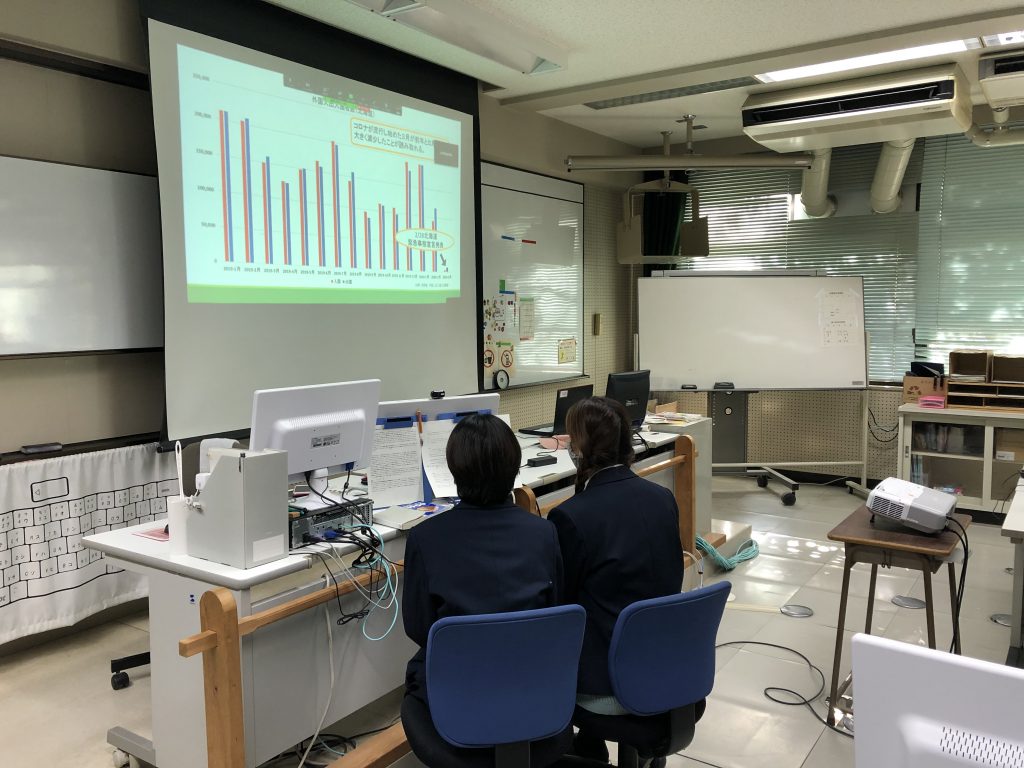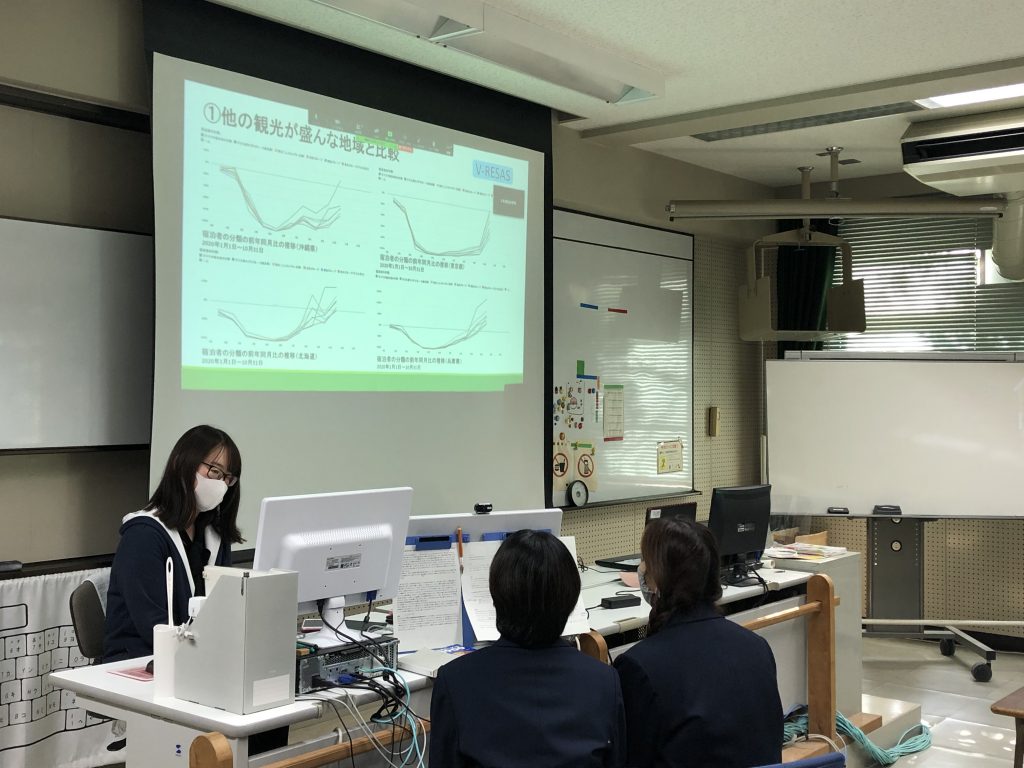キメックセンタービル10階会議室において、普通科グローバルリサーチ受講生(1年)10名と創造科学科5期生(1年)7名を対象にKOBE研修情報分野を実施した。はじめに、国立研究開発法人理化学研究所計算科学研究センター副センター長の佐藤三久氏から「スーパーコンピューター『富岳』~『京』から『富岳』へ~」というテーマで講義をしていただいた。次に、公益財団法人神戸医療産業都市推進機構クラスター推進センター都市運営・広報課課長代理の西田浩之氏からポートアイランド2期の医療・バイオ・情報クラスターについて説明をしていただいた。また、展望室にて各クラスターを確認した。続いて、公益財団法人計算科学振興財団(FOCUS)に移動し、同財団普及促進グループ長の中谷景一氏からシミュレーションクラスターとFOCUSについて説明をしていただいた。同担当課長髙橋太一氏から事前学習をもとにスーパーコンピューター活用事例について講義をしていただいた。最後に同施設の「スーパーコンピューター誕生と発展の歴史」と「世界一を獲得した日本のスーパーコンピューター」の展示をもとに説明をしていただいた。
-
最近の投稿
最近のコメント
アーカイブ
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年7月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年9月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年1月
- 2012年9月
- 2012年6月
- 2011年12月
カテゴリー
メタ情報