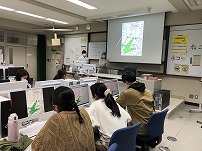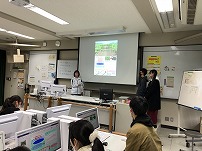神戸市公式note「県立兵庫高校に久元市長 まさかの「子ども医療費」をめぐる白熱議論!」https://kobe-note.jp/n/n68736fd5c1f5
〈生徒感想〉
今回のディスカッションでは主に、子育て支援の拡充はまだ余地はあるが、本格的に取り組むには大都市の果たすべき役割である産業発展による国全体の経済活動の活性化を優先し、資金を確保しなければならないという面があると知りました。しかし、それでは人口が増えることによる経済発展は難しく、産業投資と子育て投資のどちらを優先するべきか悩ましいと思いました。僕は一時的に産業で世界に遅れをとっても、人が増えれば巻き返しを図ることもできると思うので、子育て支援、教育の拡充を、産業への投資を削ってでも行うべきなのでは無いかと考えましたが、それでは現状の財源である税を払う現役世代にリターンが少ないので、実現可能性は低いと思いました。
自分の住んでいる地域や関係のある地域について講義を聞き、実際に行動し、それを多くの人に伝えるという一連の流れをもってはじめて地域に貢献したと言えると思う。有難いことに私たちはその講義の機会を与えていただいているので、それらが無駄にならぬよう自分の頭で考え行動できる人になりたいと思った。例えば選挙の投票率が低いことはおそらく大半の人が認知しているだろう。そのため選挙に行こうという呼びかけはあまり人々の耳に入っていないように思う。だから大学や会社など人々の所属組織単位で投票する意識を高めることが1つの解決策であると考える。
ある課題に対して解決策やより良い案を探るのにあたって、他の視点から探ってみることが重要だと思いました。今日の市長とのディスカッションでは、神戸市の現状や課題について討論しましたが、この考え方もあるのかという場面がありました。例えば、自分が市長に質問し、回答していただいた地下鉄と他の私鉄の直通構想についても、最初はメリットしかないと考えていました。しかし、市長にご説明いただいたなかで、優等種別を設定したとしても通過駅が発生し、主要駅からしか利用者を拾うことができないということがありました。これは、自分の考えには全くなかったものであり、大変勉強になりました。このように、こうすればよいのではないかという意見が出たとしても、他の視点から考えて問題はないか、よりよい案はないかと考えることで合理性を高めることにつなげられると感じました。
いろいろな境遇の人の気持ちになって考えてみるのはもちろん、さまざまな人の意見をなんらかの形で市や県に伝えるべきだということです。神戸市内だけでも子供からお年寄りまで、小さい子供を連れている人や障がいを持っている人がいるように、さまざまな人が住んでいます。もちろん1番理想的なのはすべてのひとが幸せに暮らせることですが、お話を聞いていてやはり当事者と当事者以外との捉え方や考え方には大きな違いがあるのではないかと思いました。私達が今回市長に直接お話しできる機会を頂けたように、是非もっと多くの人の意見や考えが伝わる必要があるなと思いました。
本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、創造科学科7期生(1年)40名を対象に、久元喜造神戸市長とディスカッショを行った。まず、久元市長から「環境問題から考える民主主義-SDGs貢献都市 神戸-」のテーマで、神戸市における環境保全を中心に、SDGsの取組みについて講義をしていただいた。続いて、生徒から事前学習を含めてディスカッションテーマを発表し、複数の班が提示した子育て医療に関するテーマで議論した。生徒からは自身のアイデアや経験にもとづく意見を久元市長にぶつけ、市長からは政令指定都市の規模と役割の観点から政策面においてやるべきこととやるべきではないことがあるという説明があった。生徒からはさらに質問をかぶせたりして、白熱した議論が繰り広げられた。
神戸市公式note「県立兵庫高校に久元市長 まさかの「子ども医療費」をめぐる白熱議論!」https://kobe-note.jp/n/n68736fd5c1f5
〈生徒感想〉
今回のディスカッションでは主に、子育て支援の拡充はまだ余地はあるが、本格的に取り組むには大都市の果たすべき役割である産業発展による国全体の経済活動の活性化を優先し、資金を確保しなければならないという面があると知りました。しかし、それでは人口が増えることによる経済発展は難しく、産業投資と子育て投資のどちらを優先するべきか悩ましいと思いました。僕は一時的に産業で世界に遅れをとっても、人が増えれば巻き返しを図ることもできると思うので、子育て支援、教育の拡充を、産業への投資を削ってでも行うべきなのでは無いかと考えましたが、それでは現状の財源である税を払う現役世代にリターンが少ないので、実現可能性は低いと思いました。
自分の住んでいる地域や関係のある地域について講義を聞き、実際に行動し、それを多くの人に伝えるという一連の流れをもってはじめて地域に貢献したと言えると思う。有難いことに私たちはその講義の機会を与えていただいているので、それらが無駄にならぬよう自分の頭で考え行動できる人になりたいと思った。例えば選挙の投票率が低いことはおそらく大半の人が認知しているだろう。そのため選挙に行こうという呼びかけはあまり人々の耳に入っていないように思う。だから大学や会社など人々の所属組織単位で投票する意識を高めることが1つの解決策であると考える。
ある課題に対して解決策やより良い案を探るのにあたって、他の視点から探ってみることが重要だと思いました。今日の市長とのディスカッションでは、神戸市の現状や課題について討論しましたが、この考え方もあるのかという場面がありました。例えば、自分が市長に質問し、回答していただいた地下鉄と他の私鉄の直通構想についても、最初はメリットしかないと考えていました。しかし、市長にご説明いただいたなかで、優等種別を設定したとしても通過駅が発生し、主要駅からしか利用者を拾うことができないということがありました。これは、自分の考えには全くなかったものであり、大変勉強になりました。このように、こうすればよいのではないかという意見が出たとしても、他の視点から考えて問題はないか、よりよい案はないかと考えることで合理性を高めることにつなげられると感じました。
いろいろな境遇の人の気持ちになって考えてみるのはもちろん、さまざまな人の意見をなんらかの形で市や県に伝えるべきだということです。神戸市内だけでも子供からお年寄りまで、小さい子供を連れている人や障がいを持っている人がいるように、さまざまな人が住んでいます。もちろん1番理想的なのはすべてのひとが幸せに暮らせることですが、お話を聞いていてやはり当事者と当事者以外との捉え方や考え方には大きな違いがあるのではないかと思いました。私達が今回市長に直接お話しできる機会を頂けたように、是非もっと多くの人の意見や考えが伝わる必要があるなと思いました。