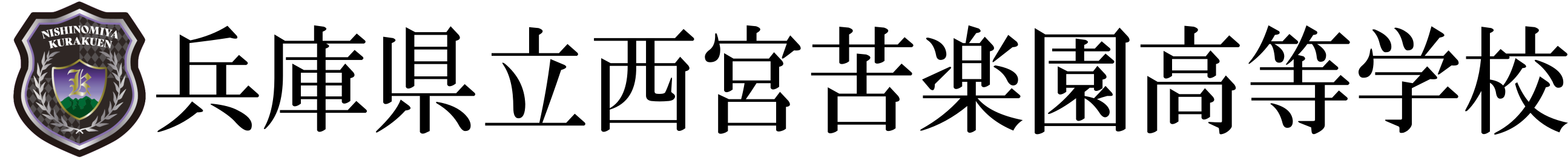令和7年度 学校経営の重点
1 授業実践力・授業改善力の向上による生徒の学力向上及び非認知能力の育成
(1) 新時代に生きる力を育成するため、AI やアプリ等を含むICT の利活用や、「主体的・対話的で深い学び」の授業研究と実践に、全ての教職員で取り組む。
(2) オープンルーム等での互見授業、近隣の小・中・高校への公開授業への参加、本校における公開授業研究会の実施等により、更なる授業改善に努める。 (新任で着任している先生による研究授業の毎年度実施)
(3)自己の進路に見通しをもって学習に取り組めるよう、必要な情報や体験活動等の機会を早期に適切に提供し、組織的・体系的に進路指導・キャリア教育を進める。
(4) 学校行事や部活動などの実践的・体験的活動はもとより、授業の中で「思考力、判断力、表現力」の他、忍耐力、協働性、自主性等の非認知能力を養う。
(5) 「何を学ぶか」に加え、「どのように学ぶか」「何ができるようになるか」の視点から観点別学習評価をさらに改善し、指導と評価の一体化を進めるとともに、シラバスを提示し評価に対する説明責任を果たす。
2 探究的な学びのカリキュラム開発と教科横断による学びの充実
(1) 「Global View 」「Local Communication 」「DX Experience 」の3 つのフィールドを念頭に、「総合的な探究の時間」を含む探究学習等のカリキュラム開発を進め、わくわく探究部が核となり、全職員体制で展開できる組織的・体系的な指導体制を構築する。
(2)各教科との関連性を重視しながら、育成する資質・能力を明確にして取り組む。
(3)自然体験や就業体験活動、ボランティア活動などの社会体験、ものづくり、生産活動などの体験活動、観察・実験・実習、調査・研究、発表や討論などの探究活動を、生徒の興味関心や進路に合わせて積極的に取り入れる。
(4) 中間発表会、探Qグランプリなど、全学年が参加する発表と意見交換の機会を設ける。
3 コミュニティ・スクールを視野に入れ、地域や小・中学校、大学等の教育機関と連携・協働しながら、「社会に開かれた教育課程」の実現に努める。
(1) 夏祭りやコンサート等の地域行事に積極的に関わり交流を深めるとともに、校内行事を地域に公開し、地域貢献の意識を涵養する。
(2)本校の教育活動や特色についてHP や学校説明会等あらゆる機会に発信し広報活動に努める。 ( 探究的な学びを支える大学等とのコンソーシアム形成を目指し、連携協定を結ぶことができる大学を引き続き模索する。
4 生徒と教職員との信頼関係を基盤とした安心・安全な授業、行事、部活動等の実施
(1) スケジュール管理、生活習慣の確立など、社会人として必要な基礎素養を身につけさせ、教育活動全体を通して人格の陶冶を図る。
(2) 自他を尊重する精神、共生の心を育み、「いじめは決して許されない」という決意のもとに、いじめの早期発見・解決に組織的に取り組む。
(3) 生徒、保護者、教員で組成する校則検討委員会を立ち上げ、校内ルールの改善を随時進める。
5 ウェルビーイング(Well beingbeing)の実現に向け、教職員の働き方改革をさらに推進する
(1) 適度な休息がとれるよう、全ての部活動において、「いきいき運動部活動」で示された平日は1 日休み、2 時間以内、土日は1 日休み、3 時間以内の練習時間を遵守する。
(2) 無理のない働き方ができるよう、育児や介護等個々の事情に対応できる職場環境づくりに努める。
(3)DX 委員会等の提案を積極的に実践し、ペーパーレス化や業務のスクラップ&ビルドを進める。
(4)「デジらく」等採点システムを活用し、採点業務等の負担軽減を図る。