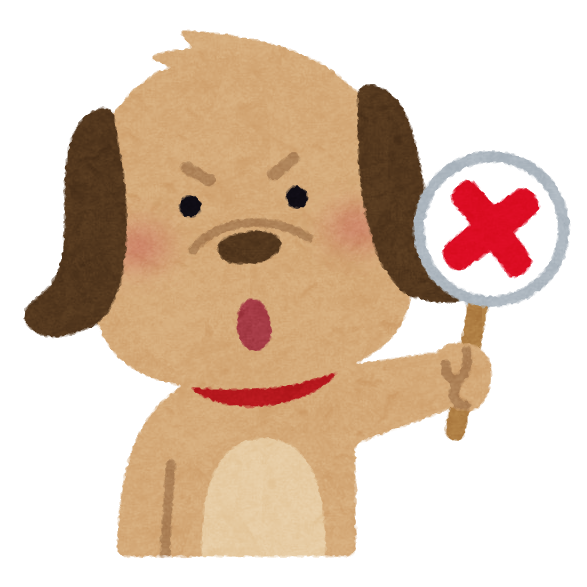有名な話だが、「情けは人のためならず」という言葉の意味を、間違って捉えている人が大勢いるという。本来は「人に情けを掛けると、巡り巡って自分に戻ってくる」という意味だ。一人の善意でもそれが広がれば、誰にでも優しい世の中になるという教えだが、世知辛い現代では、「甘やかすとその人のためにならない」と受け取る人が多い。
「役不足」という言葉があるが、これも使い方を間違うと恥をかく。大役を仰せつかったときに謙遜して「私では役不足ですが」という人がいるが、本来は役者が、「自分の実力にふさわしくないつまらない役」という意味で不平不満を表すときに用いた。「役不足」は「力不足」の意味にはならない。
「当たり前」という言葉があるが、これも、誤用から生まれた。よくよく考えればわかることだが、「当たり前」そのものに意味はない。当たっていないのだから、何も起こっていない。意味のない言葉が生まれる道理はない。
実はこの言葉、「当然」の誤用から生まれた。「当然」の「当」は再読文字で「まさにしかるべし」と読み、「全くその通りだ」という意味になる。おそらく誰かが「然」と同じ音の「前」とを書き間違えたのだ。
誤用が市民権を得ると、辞書に掲載され、新しい言葉として認知される。言葉が「生きている」と言われるゆえんだ。